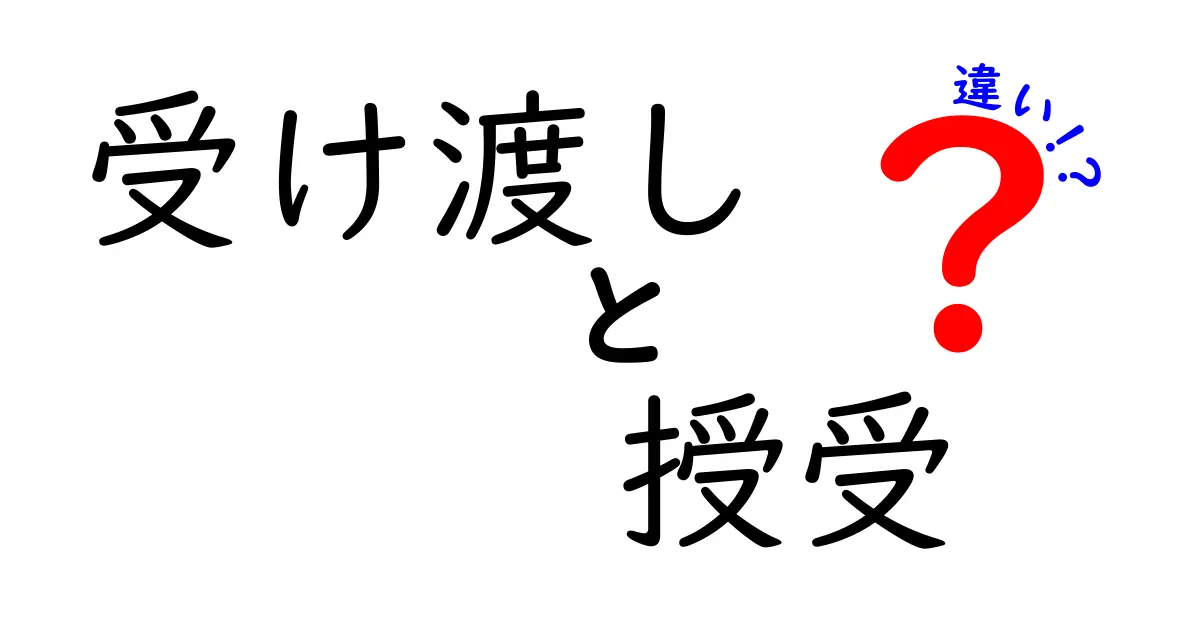

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
受け渡しと授受の基本を区別するポイント
この2つの言葉は見た目が似ているようで、使われる場面や意味のニュアンスがかなり違います。まず"受け渡し"は、物品や書類などを実際に渡すこと、渡した側と受け取った側の動作そのものを表す名詞として広く使われます。日常の場面では、学校の貸出物の受け渡しや、宅配便の荷物の受け渡し、役所での申請物の受け渡しなど、手渡しの動作を指しています。構成としては「受け取る」+「渡す」という一連の動作が核になっており、手続きを進める上で欠かせない名詞です。発音も日常語として自然で、カジュアルにもフォーマルにも使えます。
一方の"授受"は、単にものをやり取りする意味だけでなく、関係性や礼儀、儀式的な雰囲気を含むことが多い語です。授は「与える・授ける」という意味、受は「受け取る」という意味で、互いの行為が結びついて「与える人」と「受ける人」という二つの立場を同時に表す点が特徴です。学校や企業の公式文書、法令・契約書、学術的な説明文など、やや硬い場面でよく見られます。授受はしばしば「授受の関係」「授受を行う」などの語順で使われ、友人同士のカジュアルな会話にはあまり出てきません。
この違いをつかむコツは、対象が物理的な渡し/受け取りの動作かどうかを見分けること、そして場の格式を判断することです。日常的な渡し合いは"受け渡し"を使い、職場の正式なやり取りや儀式的な場面では"授受"が自然だと覚えると混乱が減ります。以下に場面別に整理します。
そもそも「受け渡し」とは何か?
まず受け渡しの基本から整理します。受け渡しは、物や書類などを実際に渡す行為そのものと、それを受け取る側の動作を一連の流れとして表す名詞です。日常生活で見かける具体例としては、図書館の本を返すときの受け渡し、学校で教材を借りるときの受け渡し、郵便局で荷物を受け取るときの手続きなどがあります。
この語を使うときは、渡す側と受け取る側、そして何を渡すかという物理的な対象がはっきりしている場面が多いのが特徴です。したがって、手順書や業務マニュアル、通知文でも受け渡しという語が頻繁に登場します。さらに、動作の完成形を強調したいときにも適しています。
例えば「本日の受け渡しは午前10時に完了しました」というように、作業の完了を報告する表現としてよく使われます。
「授受」の成り立ちと使い方の違い
次に授受の成り立ちと使い方を詳しく見ていきます。漢字の意味から考えると、授は「与える・授ける」、受は「受け取る」という動作を示します。二つの動作が同時に関係する場面で使われ、二者の立場を同時に強調したいときに適しています。公的な手続きの説明文や教育・学術の文脈では「授受の礼」「授受関係」といった表現が見られ、社会的な距離感を示すニュアンスが生まれます。実際の文を書くときは授受を使うときちんとした印象を与えやすく、逆に砕けた場面では不自然に感じやすいのが特徴です。
例として大学の研究費の授受、領収書の授受といった表現があり、相手との関係性を意識した言い換えに活用されます。
一方で授受は、物を渡す動作そのものよりも、相手との関係性や礼儀を重視する場面で使われることが多いです。授受を用いることで、ただの物品のやり取りではなく、双方の立場・役割・場の格式が文面に反映されます。日常の会話で授受を使う場面は少なく、公式文書や説明文、儀礼的な場面での採用が中心になる傾向があります。
この点を踏まえると、授受は「相手への敬意や儀礼」を表すニュアンスが強い語だと理解することができます。
実際の使い分けを場面別に考える
使い分けのコツはシーンの格式と対象の性質を見分けることです。日常生活では物を渡す場面が多く、受け渡しが自然。学校・職場の公式文書・契約や公的な場面では授受の語感が適します。以下の場面別の整理は、混乱を避けるのに役立ちます。まず日常生活の例として、友だちに本を返すときは受け渡し、先生から贈り物を受け取る場面では授受のニュアンスが感じられることがあります。次にビジネス場面では契約書のやり取りは受け渡し、取引先との関係性を示す説明文には授受が登場することがある、などです。
また公的・文化的儀式の場面では授受の語感がよりふさわしいことがあります。例えば授賞式の際の語り口や儀礼的な文脈では授受が選ばれやすい傾向が見られます。ここまでの整理を踏まえると、語の選択には相手との距離感・場の Formalさ・対象が物かどうかという三つの要素が大きく影響することが分かります。
以下の表は受け渡しと授受の特徴を簡単に比較したものです。
表を読むときのポイントは、物理的な渡しの有無と場の格式を同時に意識することです。
このように、場面の性質と相手との関係性を考えながら語を選ぶと、読み手に伝わる印象が大きく変わります。日常の場面では受け渡し、公式・儀式的な場面では授受を用いると自然な表現になります。
日常場面の例
日常でのやり取りを見てみると、友人に資料を渡すときには受け渡し、先生に贈り物を渡すときには授受のニュアンスが近いと感じることがあります。授受を使うときは相手との関係性や場の礼儀を強調したいときで、カジュアルな会話ではやや不自然になることもある点に注意が必要です。
この区別を意識するだけで、文章のトーンづくりが楽になります。例えば授業での作文では受け渡しを中心に書き、公式のメールや報告書では授受の語を適切に使うと、読み手に丁寧さが伝わりやすくなります。
ビジネス・公的文書での使い分けのコツ
ビジネスの現場では、物のやり取りを表すときには受け渡しを使い、関係性を強調する必要がある場合には授受を使うと効果的です。たとえば契約手続きの説明文では受け渡しの条項を明記し、契約の信頼関係や礼儀を示す説明には授受の表現を組み合わせると、読み手にとって理解しやすくなります。
重要なのは、対話相手が誰か、どの程度 formalな場なのかを見極めて適切な語を選ぶことです。これを実践できれば、文章の質が高まります。
授受という言葉を友達と雑談していたとき、突然の気づきがあったんだ。授受はただの渡し合いではなく、相手との関係性と場の格式を示す言葉だと。学校の事務手続きで授受の語を使うと、堅苦しさが伝わり、友人同士で軽く使うには違和感が生じる。そんな感覚を、日常のやり取りに例を当てながら話すのが楽しかった。たとえば先生にプリントを渡す場面を想像してみると、表面的な動作は同じでも、授受の語を使うと「このやり取りには相手を敬う気持ちが乗っている」という印象が生まれます。逆に何かを借りて返すような日常的な渡し合いでは受け渡しの方が自然。こうした感覚を覚えておくと、作文や報告文を書くときに適切な語を選ぶ手助けになります。
次の記事: 受渡日 約定日 違いを完全解説!初心者にも分かる株式取引の基本 »





















