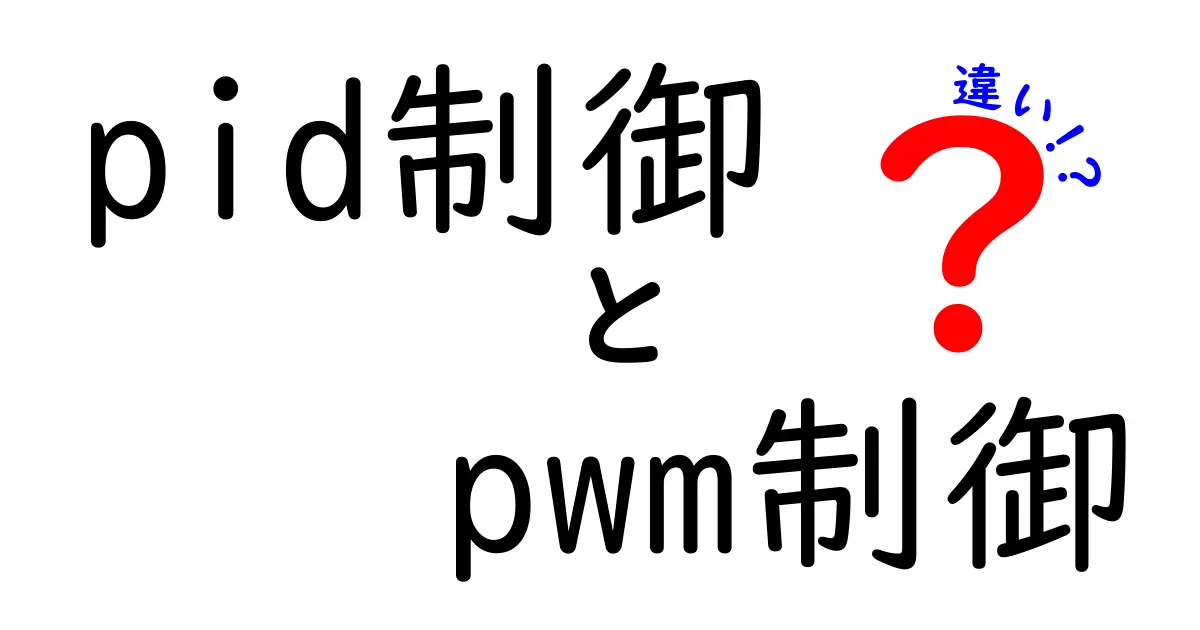

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
PID制御とPWM制御の違いを理解するための基礎知識
PID制御とは、目標値と現在値の差をもとに出力を決定するフィードバック制御の基本形です。PIDは Proportional、Integral、Derivative の頭文字を取ったもので、差を「比例」「積分」「微分」という3つの働きで補正します。
この3つの要素をどう組み合わせるかが、反応の速さ・安定性・ノイズ耐性を決めます。初心者にとっては、まず“誤差を小さくするための3つの機能がある”という点を覚えるだけでも十分です。
例えば、部活のボールの軌道を安定させるときのように、現在の位置と目標の差を素早く感じ取り、出力を滑らかに変化させるのがPIDの役割です。
また、PIDは“測定値を良くするための設計”であり、現実の世界にはノイズ・遅れ・センサの誤差などの要因がつきものです。そうした要因を踏まえ、式の各項を調整して実機の挙動を安定させるのが実務のコツです。
この考え方は、ロボットのモータ制御、エアコン(関連記事:アマゾンでエアコン(工事費込み)を買ってみたリアルな感想)の温度安定、車両の速度制御など、私たちの身の回りの多くの場面で活躍しています。重要なポイントは適切なパラメータ調整です。Pを強くすると反応は速くなりますが、過剰な振動につながることがあります。Iを増やすと長期的な誤差を減らせますが、遅れを生む原因にもなり得ます。Dを足すと急な変化に対する過剰反応を抑え、振動を和らげる働きがあります。これらをバランスさせる作業が“PID調整”です。
初学者の多くは、最初にPを控えめに設定し、IとDを少しずつ追加していく方法から始めます。データをグラフ化して、どのパラメータがどう影響しているかを目で見ながら学ぶのが効率的です。
一方、PWM制御とは、パルス幅を細かく変えることで平均的な電圧を変化させる技術です。PWMはモーターやLEDの出力をデジタル処理で滑らかに見せつつ、アナログのような制御を実現します。
PWMの基本は「一定の周波数でONとOFFを切り替え、デューティ比を変える」ことです。デューティ比が高いほど平均出力は高くなり、低いほど低くなります。モーターの回転速度を滑らかに変えたいとき、PWMは出力を細かく操作できる強力な味方です。
ただし、PWMはハードウェアの特性に左右されます。周波数が低いとモーターがギクシャク動くことがあり、逆に高すぎるとスイッチング損失や熱が増えるなど、設計上のトレードオフが生じます。現場では、PWMの周波数設定とデューティ比の範囲を、制御目的とモータドライバの仕様に合わせて決めます。
ここがポイントは「制御の目的と出力の形」「測定と更新の頻度」「現場のハードウェアとの相性」です。PIDは誤差を減らすための数学的制御で、理想は目標値へすばやく安定して近づくことですが、現実には振動や遅れがつきものです。PWMは出力をハードウェア側で作る手法で、出力の形をどう見せるかを決めます。つまり、PIDとPWMは性質が異なる別の技術であり、現場ではしばしば組み合わせて使われます。
この組み合わせによって、目標値に対して安定かつ効率的に近づくことが可能になります。
次のセクションでは、どんな場面でどちらを選ぶべきか、そしてどう組み合わせるとよいかを具体的な例とともに考えていきます。
現場での使い分けと組み合わせのコツ
現場では、まず「どの変数を制御するのか」を決め、その後「出力をどのように制御するのか」を選択します。温度のように変化が遅い場合は、I成分を活用して長期的な誤差を減らす調整が有効です。逆に風速やモーターの回転数のように急変する場面では、D成分の反応速度を活かして過剰な振動を抑えつつ、P成分で素早く反応させます。さらにPWMの周波数とデューティ比を適切に設定することで、ハードウェアのノイズや熱を管理します。
初心者はまずPを控えめに設定し、IとDを少しずつ追加していくのが無難です。データを収集し、グラフ化して挙動を観察する習慣をつけましょう。失敗したときは、1つのパラメータだけを変えて原因を突き止め、別のパラメータへ影響を広げるようにします。
現場では、PIDの3要素とPWMの出力特性を同時に最適化することで、制御系の安定性と応答の両立を図ります。要するに「何を制御したいのか」「どんな出力が現実的なのか」をまず整理し、徐々にパラメータとハードウェア設定を煮詰めていくプロセスが大切です。
中学生でも理解できるように話すと、PID制御は“心の反省ノート”みたいなもの。自分がミスしたときに「どうしたら次はうまくいくか」を3つの道具(P・I・D)で考え、すぐに直す方法を決めていく感じです。例えば、走る競技で考えると、Pは速さの出だし、Iは長い間の遅れを挽回する工夫、Dは急に止まるときの揺れを抑える抑制みたいな役割。PWMは出力をいくつもの小さなスイッチで切り替えて、アナログのように感じさせる“見せ方”の技術。だから、PIDとPWMを組み合わせると、速くて安定した動きを作れるんだよ。実験を重ねると、どのパラメータがどんな挙動に効くかが自分の感覚でも分かるようになってくる。





















