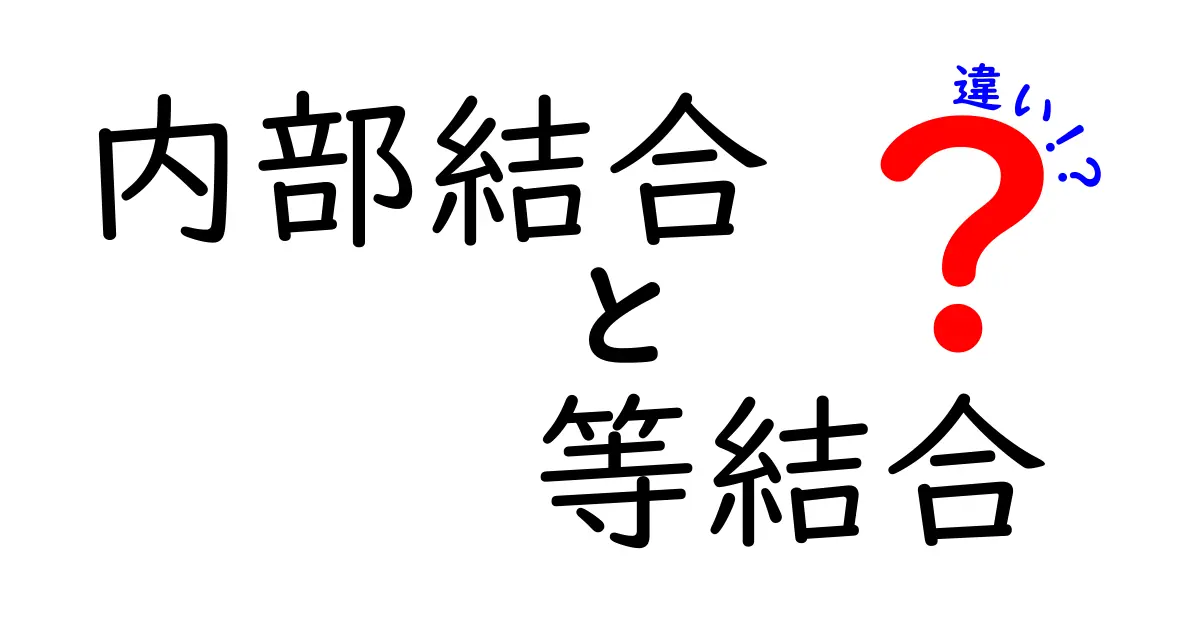

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
内部結合と等結合の違いを知ろう
内部結合とはデータベースのテーブル同士を結ぶ基本の仕組みのことです。指定した条件に合う行だけを取り出して新しい表を作る作業を指します。例えば生徒の情報が入っているテーブルと成績が入っているテーブルを結ぶとき、同じ生徒を表すidを使って結びます。内部結合は両方のテーブルに対応するデータがある場合にのみ結果を作ります。これを理解するとデータの組み合わせ方が見えやすくなります。なお等結合の話題はこの内部結合の一部として語られることが多く、厳密には等価条件を使う結合のことを指します。
この章では基本の考え方を丁寧に解説します。
最初はシンプルな例から始め、ゆっくりとポイントをつかんでいきましょう。
内部結合とは何か
内部結合は2つのテーブルの共通部分だけを取り出す操作です。共通部分という言い方は、両方に同じ情報を持つ行がある場合のみその行を結果として出すことを意味します。例えば student テーブルと score テーブルを id でつなぐとします。学生ごとに一人ずつ対応する成績がある場合にだけ、名前と成績が並んだ行が作られます。
このとき使う SQL は通常 INNER JOIN 句と ON 条件です。
ON の部分には等号を使うことが多く、これを 等結合 の核心と見る人もいます。
内部結合を使うときの基本は同じです。結合条件が成り立つ行だけを取り出すので、条件が合わない行は結果に現れません。ここが「外部結合」など他の結合と大きく異なる点です。初めてSQLを触る人でも、書式を覚えるとすぐに使いこなせるようになります。
実務では具体的な例として生徒データと成績データを結ぶ場合が多く、以下のようなパターンになります。
例: 生徒名と成績を取り出す場合、INNER JOIN を使い ON 条件として s.id = sc.student_id を指定します。これにより両方の表に存在する生徒だけが結果として並ぶのです。
重要なポイントを整理します。
ポイント:
- 内部結合は両方のテーブルに共通するデータだけを取り出す
- 等結合は結合条件が等号で表される場合の典型的な使い方である
- 非等結合は比較演算子を使うケースもあるが別カテゴリとして扱われることが多い
- 実務では INNER JOIN ON を使い等式条件を指定することが多い
等結合とは何か
等結合は結合条件が等号 = で表される結合のことを指します。等価条件 を使うため、2つのテーブルの指定した列の値がぴったり同じときだけ結びつけられます。例として先ほどと同じ2つのテーブルを考え、ON s.id = sc.student_id の形で結ぶと、id が一致する行のみが結果になります。
等結合はINNER JOIN の典型的な使い方であり、実務では最もよく使われる結合パターンです。
ただし注意点として 非等結合 という別の扱いもあり、条件に 比較演算子 を使うケースもあることを覚えておくとよいです。
等結合の良さはシンプルで読みやすい点です。値が同じであることを前提に処理を進めるので、コードの意図がすぐ伝わります。
また、複数のテーブルを結ぶ複雑なクエリでも、等結合を組み合わせることで整然とした設計に近づきます。
違いを理解するポイント
内部結合 は結合の基本の枠組みで、等結合 はその枠組みの中での代表的な条件の一つという理解がすっきりします。両者は重なる概念ですが、実務では「内部結合=テーブルを結ぶ表現」「等結合=結合条件の種類」と分けて考えると混乱を避けやすくなります。実例を見てみましょう。
以下のポイントを押さえると差が見えやすくなります。
- 内部結合は両テーブルに対応するデータがある場合のみ結果を作る
- 等結合は結合条件が等しい場合にだけ行を作る
- 非等結合は比較演算子を使うケースもある
- 実務では INNER JOIN ON を使い等式条件を指定することが多い
等結合という言葉を友達と雑談風に深掘りしてみると結合のイメージがつかみやすいです。たとえば学校の名簿と出席データを結ぶとき、同じIDを持つ人だけつなぐのが等結合の基本的な考えです。最初は「同じ値を持つ行を結ぶ」という直感から始めると、後で他の条件を追加しても混乱しません。実際には日付やコードが一致するかどうかを確認する場面が多く、等結合はその“一致条件”を明確化する道具になります。友達と話していると、データがつながる瞬間の喜びをより身近に感じられます。だからこそ等結合の感覚を養うことは、将来のデータ分析にも役立つのです。





















