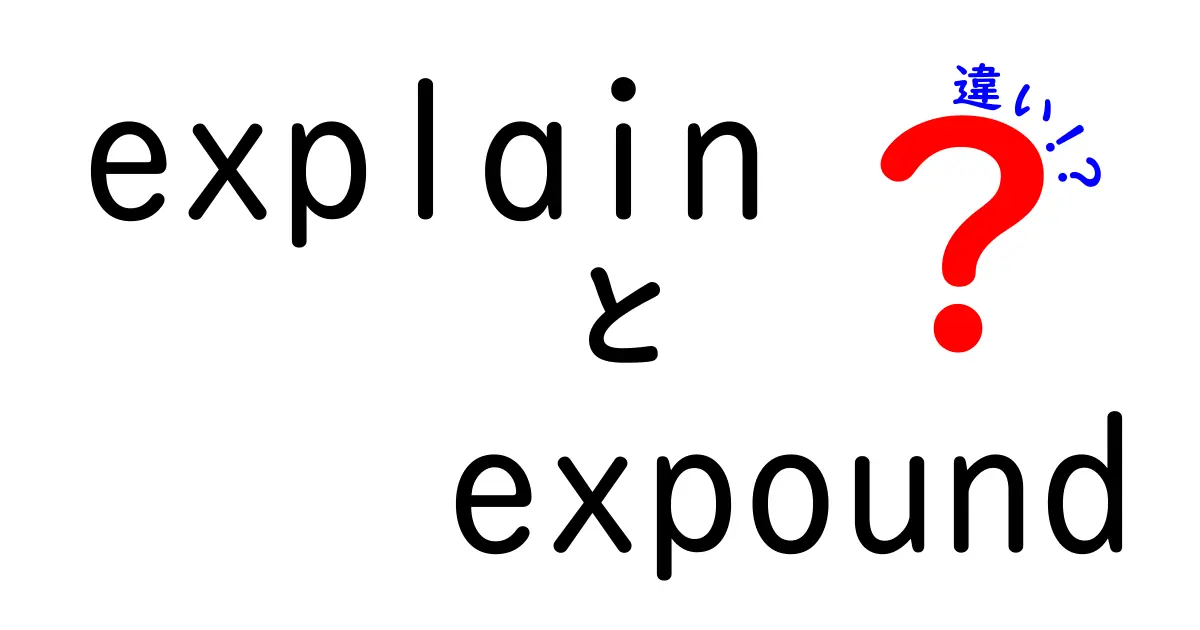

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
explainとexpoundの違いを理解する基礎知識
explainは日常の場からビジネスの場まで幅広く使われます。情報を伝えるときの基本は“何がどう起きたか、どういう理由でそうなるのか”を分かりやすく提示することです。意味を掘り下げると、explainは原因・仕組み・結論を明確に伝えることに重点が置かれます。語源はラテン語の explanare から派生し、"ex"(外へ)と "planare"(平らにする)という意味の組み合わせです。つまり、文章の奥に潜む意味を引き出し、読者の頭の中で“畳んでしまっている内容を広げて見せる”行為を指します。対してexpoundはよりフォーマルで長く、論理の筋道を順序立てて展開する意味が強くなります。教室・講演・論文・学術的な文脈でよく使われ、主張の根拠・例・反論への対処を順に並べて読者に納得してもらう目的があります。
両者の違いを一言で言えば、explainが“何がどう起きているかを説明すること”で、expoundが“その説明を詳しく、組み立てて展開すること”だと覚えると分かりやすいです。日常の会話ではexplainを使い、専門的な講義や長い解説ではexpoundを選ぶとニュアンスが伝わりやすくなります。たとえば友だちに新しいゲームのルールを説明するときはexplain、研究者が理論を詳しく説明する場面ではexpoundが自然です。すぐに使い分けを身につけたいときは、前置詞や文脈をヒントに判断する練習を重ねると良いでしょう。
意味と語源の違いを見極める
explainの語源はラテン語の explanare で、外へ広げて明確化するイメージです。expoundは古い英語の expondere から来ており、長く層を重ねて展開するという意味合いが強いです。日常ではexplainが主役で、出典・理由・使い方の基本を短く、分かりやすく伝える。専門家が理論を述べるときにはexpoundが適します。以下の例を見てください。explainは原因の説明、手順の説明、結論の要点を短くまとめるのに向いています。expoundは仮説の根拠、反例の検討、結論に至るまでの筋道を丁寧に説明する場面で活躍します。実用の場面を想像すると、explainは「なぜそうなるのか」を手早く説明する、expoundは「どうしてその結論に達するのか」を深掘りして語る、そんな使い分けが自然になります。
使い方の現場での差
日常生活の場面では、explainを使うのが最も無難で安心感があります。友人に新しいアプリの使い方を説明する、保護者に出費の理由を伝える、先生が課題の趣旨を伝えるなど、短く要点を伝える役目を果たします。反対にexpoundは、授業や講演、研究論文のような場で活躍します。ここでは「理由」「根拠」「影響」「代替案」を順序立てて並べ、読者が論理のつながりを追えるようにするのが狙いです。例えば「この仮説を支持するデータについてexpoundする」という表現は、データのどの点が重要か、どの前提が欠けているか、どういう反論が考えられるか、を順を追って説明するという意味になります。日常と学術の両方をまたぐ場面では、まずexplainで要点を伝え、その後必要に応じてexpoundで詳しく説明するのが現実的です。
具体例と注意点
実際の使い分けを見ていくと、次のようなポイントが見えてきます。
1) 短く要点を伝えるときはexplainを選ぶ。
2) 理論や方針を順序立てて展開するならexpoundを選ぶ。
3) あまりに長くなると説明の焦点がぼやけるので、必要な部分だけを詳述する工夫が要る。以下のポイントを意識すると混乱が減ります。
- 場面に応じて短く説明するか詳しく説明するかを判断する
- 語感の違いを覚え、会話や文章のトーンに合わせる
- 説明の目的を明確にして、根拠・例・結論の順序を意識する
覚え方と使い分けのコツ
覚え方のコツは、場面の緊張感と長さのバランスを想像することです。
explainは“すばやく鍵となる情報を開示する道具”と考え、expoundは“論理の筋道を順序立てて丁寧に開示する設計図”と捉えると混乱が減ります。語感の違いにも注意しましょう。explainは比較的新しめの言い回しで、実務的な場面にも自然に馴染みやすいです。expoundは古風でやや硬い印象を与えることもあるので、相手や場の雰囲気を見て使い分けると良いです。最後に、練習として自分の説明を2段階に分けてみると効果的です。最初はexplainとして短く要点を伝え、次にexpoundとして根拠と例を追加してみる。
まとめと実践のヒント
explainとexpoundの違いを理解すると、英語の表現力がぐんと広がります。要点を明確に伝える力と、論理を組み立てて詳しく説明する力の両方をバランス良く使えるようになると、文章や話の説得力が高まります。日常のコミュニケーションではexplainを主に活用しつつ、学習や研究の場面ではexpoundの要素を取り入れて読者を納得させる構成にするのがコツです。実際の教材やニュース記事、講義の資料を読むときにも、この2語の使い分けを意識すると、文章の意図を正しく読み解く力がつきます。
expound の小ネタ: 友達と雑談しているとき、expound という単語をどう使うか考える場面があります。例えば先生が講義の後で「この理論をexpoundしてくれるかな?」と聞くと、私たちは“なぜそうなるのか”という根拠や筋道を順を追って追う訓練を始めます。実際、授業で意見を述べるとき、単に結論を言うだけでなく「この結論が成り立つ理由は何か」「どんな反論があり得るか」を添えると、説明の深さが一段と増します。日常でも、少し長めの説明をする場面ではexpoundを使うと相手に“この人は考えを丁寧に組み立てているな”という印象を与えやすいです。語感はやや硬く聞こえることもあるので、場の雰囲気を見て使い分けるのがコツ。





















