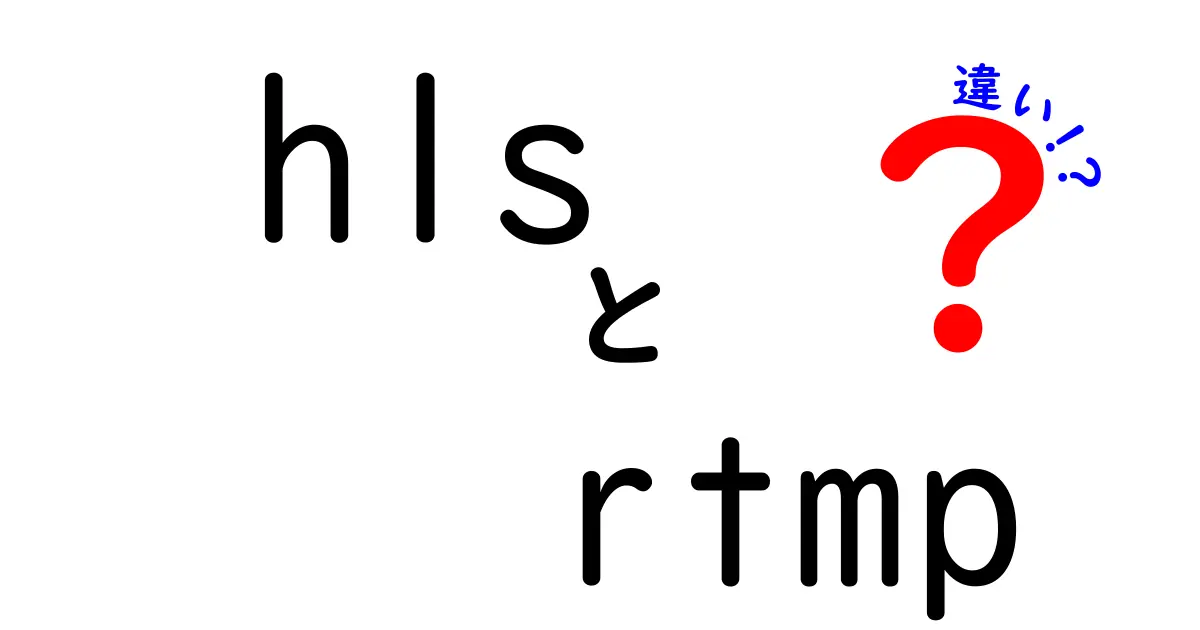

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
hlsとrtmpの違いを徹底解説|初心者にも分かる配信の選び方
HLS はHTTPベースの配信で、ウェブブラウザやスマホの視聴に強いです。
URL さえ分かればどこからでも再生でき、HTTPS の暗号化にも対応しているため安全性と拡張性が高く、CDN との組み合わせが得意です。
一方、RTMP は継続的な接続を前提とする低遅延向けのプロトコルで、エンコーダから配信サーバーへ送る用途に適しています。
この二つは役割が違うため、現場では別の段階で使い分けられます。
HLS の仕組みはセグメントとプレイリストという考え方が中心です。映像を短い区切りに分け、
.m3u8 というプレイリストで順序を管理します。クライアントはプレイリストを読み込み、セグメントを取得して再生します。
この仕組みにより、視聴者の回線状態に合わせて品質を変える ABR(適応ビットレート配信)が自然に働き、広い視聴者層へ安定した配信が可能になります。
一方、RTMP は1本の継続ストリームを保つ設計なので、低遅延は取りやすい反面、ネットワーク環境の影響を強く受けることがあります。
現場での使い分けの基本は「入口と出口を分けて考える」ことです。エンコーダからの ingest には依然として RTMP がよく使われ、配信サーバー側での処理を経て、視聴者には HLS や他の HTTP 配信へ再エンコードして届けるケースが多いです。ここに LL-HLS や低遅延技術を組み合わせると、遅延を抑えつつ広範囲へ配信できます。
ただし低遅延を追求するほど互換性の確認と環境調整が重要になる点は忘れないでください。
配信現場では、リアルタイム性と大規模配信の両立をどう実現するかが大事です。
エンコーダからRTMP で ingest し、配信サーバーで LL-HLS へ変換する流れは多くの現場で採用されています。
また、低遅延を実現する手段として LL-HLS や WebRTC などの選択肢もあり、目的や環境に合わせて組み合わせを選ぶことが重要です。
配信現場での使い分けポイント
実務の現場では 配信の目的と視聴環境を最初に決めることが大切です。
エンコーダ→RTMP で ingest し、サーバー上で HLS へ再エンコードする流れ が最も一般的です。
この仕組みなら機材やネットワークの安定性を保ちつつ、多くの視聴者に対応できます。
低遅延が命のイベント配信には LL-HLS や WebRTC などの選択肢も検討します。ただし互換性の課題があるので、事前検証と視聴環境の把握が不可欠です。
またセキュリティ対策として、RTMP の暗号化設定や token 付き配信、HTTPS 配信の導入を忘れずに行いましょう。
最後に、実装のコツをいくつか挙げます。
テスト環境を作って遅延と安定性を同時に測る、帯域シミュレーションを使って ABR の挙動を確認する、配信サーバーの負荷とスケーリングを考慮する、視聴者の端末差を想定して複数解像度を用意する。
このような準備をすると、予期せぬトラブルを避けやすくなります。
友達とライブ配信の話をしていて、hls と rtmp の違いをどう分かりやすく伝えるか悩んだことがあります。友人はとにかく低遅延を求めて rrmp が良いと言いがちですが、ここで大切なのは“どこへ届けたいのか”を考えることです。実務では ingest に RTMP を使い、視聴者へは HLS など HTTP 配信へと切り替えるのが王道です。HLS は HTTP ベースで広く再現性が高く、ABR によりネット環境が悪い人でも映像がつながりやすい。一方 RTMP は継続的な低遅延のため、局地的な配信や内部配信に適しています。こうした現実的な使い分けを覚えると、機材の購入や設定の迷いが減り、配信の現場で自信を持って判断できるようになります。





















