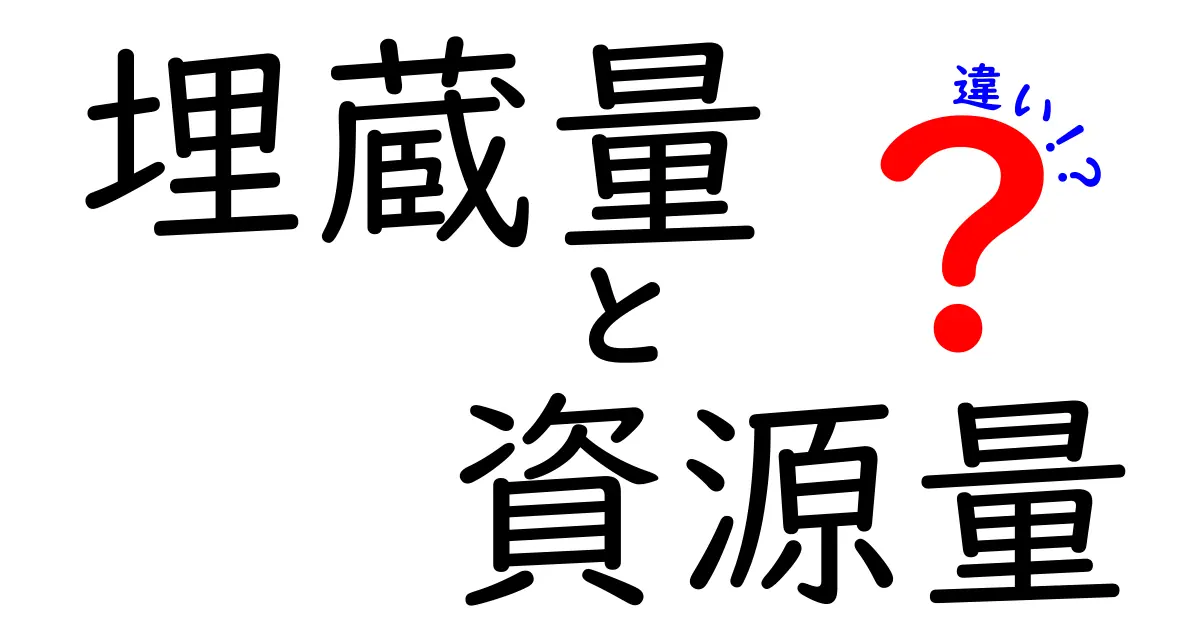

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
埋蔵量と資源量の基本を押さえよう
埋蔵量とは現在の技術と市場の条件で経済的に採掘できる資源の量のことを指します 埋蔵量 と書くことがありますが意味は決して「地面に眠っている全ての量」という意味ではありません。実は厳密には 経済的に採掘できるという条件がつきます。つまり技術が進んだり市場価格が上がったりすると、同じ鉱床でも埋蔵量は増える可能性があります。
資源量はこれに対してもう少し広い概念です。既知の資源の総量のことを指すことが多く まだ経済的に採掘できない領域や未来の可能性を含む場合が多いです。ここでの資源量には埋蔵量だけでなく未開発の鉱床や新技術で採掘が可能になると見込まれる量も含まれます。
例えば石油を例にすると現在の油田で安定的に採掘できる量が埋蔵量です。探査が進んだり新しい回収技術が開発されたりすれば、将来の埋蔵量は増えることがあります。反対に地質学的な条件が変わらない場合はそのまま減ることは少ないものの、価格の変動などで経済的な採掘が難しくなると埋蔵量の見直しが行われることがあります。
この「経済性」という言葉はとても大事です。資源が多くても採掘が難しければ実際の埋蔵量は小さく見えることがあります。結果として埋蔵量と資源量は必ずしも一致しません。この違いを理解するとニュースで出てくる資源に関する話がぐっと身近に感じられます。
ここまでのポイントをまとめると次のようになります。
・埋蔵量は 現況の経済性と技術条件で掘れる量を表す
・資源量は 知っている全ての資源の量で未来の可能性を含むことが多い
・技術や市場の変化で埋蔵量は増減することがある
埋蔵量と資源量の具体的な違いを表で見る
このセクションでは具体的な差を整理するための表を用意しました。全体の理解を深めるため、現場の人々がどう定義を使い分けているかをさくっと比較します。
最後にもう一度要点をまとめます。
埋蔵量は 現況の経済性と技術条件で掘れる量を指し、資源量は 知っている全ての資源の量と考えると理解しやすいです。
技術の進歩や市場の変動によってこの二つの数字は変わりうるため、ニュースで資源の話題を聞くときには「今の技術条件と価格での話か」を最初に確認すると良いでしょう。
ねえ埋蔵量と資源量の違いって、難しそうだけど実は身近な話なんだ。埋蔵量は今の技術と市場で採れる量、資源量は知っている資源の全体像と未来の可能性を含むもの。10年後新しい採掘技術が出れば埋蔵量は増えるかもしれない。だからニュースの数字を見るときは技術の進歩や価格の変動もセットで考えよう。
次の記事: 鉄鉱石と鉄鋼の違いを徹底解説 中学生にもわかるポイント »





















