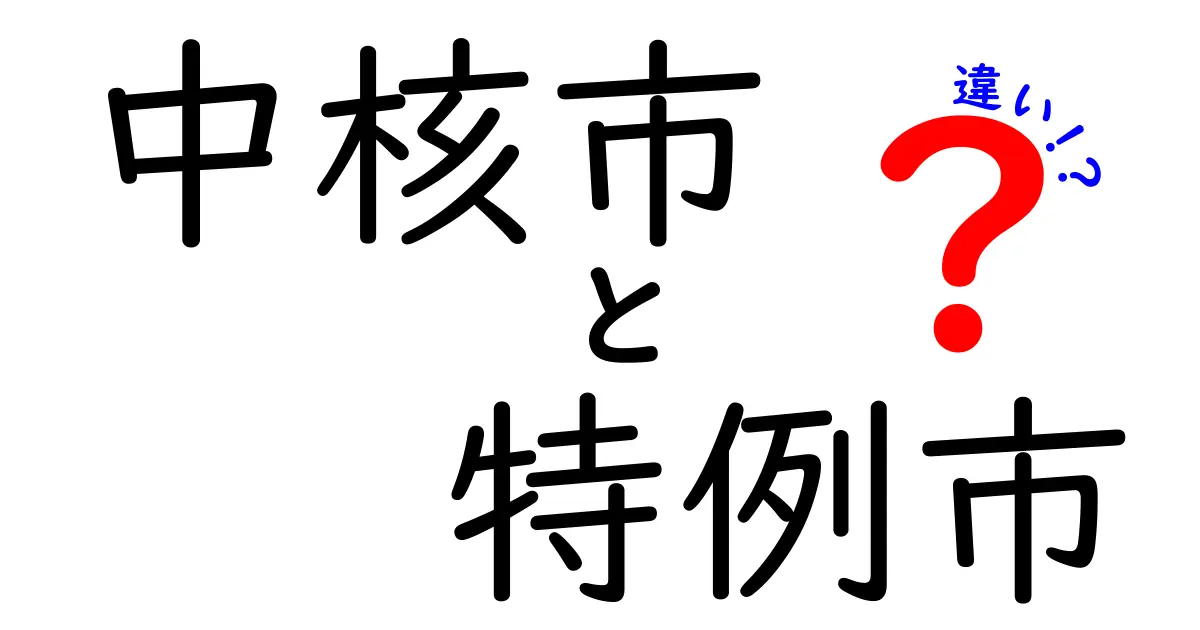

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
中核市と特例市って何?基本を押さえよう
日本の地方自治体には「中核市」と「特例市」という種類の市があります。どちらも一定の人口や条件を満たすことで、国から与えられる権限が多い市のことです。
まずは、それぞれの市がどういったものかを見ていきましょう。
「中核市」は人口がおおむね30万人以上の都市で、都道府県の一部の行政事務を自分たちで行うことができます。
「特例市」は、かつて30万人以上の人口を持つ市に与えられた制度ですが、2000年に中核市制度ができたため新設はされていません。既に指定されている市のみが特例市として残っています。
つまり、特例市は中核市が登場するまでは大きな市の特別な扱いの分類でしたが、今は中核市が新しい制度になっているわけです。
中核市と特例市の違いを詳しく比べてみよう
中核市と特例市はどちらも都道府県の一部の権限を引き継いでいますが、その範囲や条件には違いがあります。次の
表をご覧ください。
| 項目 | 中核市 | 特例市 |
|---|---|---|
| 人口条件 | おおむね30万人以上 | 人口20万人以上(2000年以前は約20万~30万人) |
| 権限の範囲 | 都道府県の事務の多くを移譲 | 都道府県から特定の事務を移譲(中核市より範囲は狭い) |
| 制度の導入時期 | 1996年開始(移行は1997年以降) | 1994年から2000年までの間に指定 |
| 現在の取り扱い | 新たな指定も可能 | 新設不可。既存の市だけが残る |
このように、中核市は特例市に比べて権限の範囲が広く、より大きな自治体として自立性が高いのが特徴です。
また、特例市は現在は新設ができないため、今後は中核市の指定が主流となっています。
「特例市」という言葉は聞きなれていないかもしれませんが、実は歴史的な背景が面白いんです。
2000年以前、日本では人口20万人以上の市が都道府県から一部の事務を任される「特例市」として扱われていました。
しかし、中核市制度が登場すると特例市は新設されなくなり、制度の枠組みが変わったというわけです。
これは「地方自治の進化」を象徴しており、市の自主性を強化する流れの一つなのです。
知っておくと、市の名前の後ろに「特例市」とつく市が古い制度の名残りであることがわかり、面白いですよね。





















