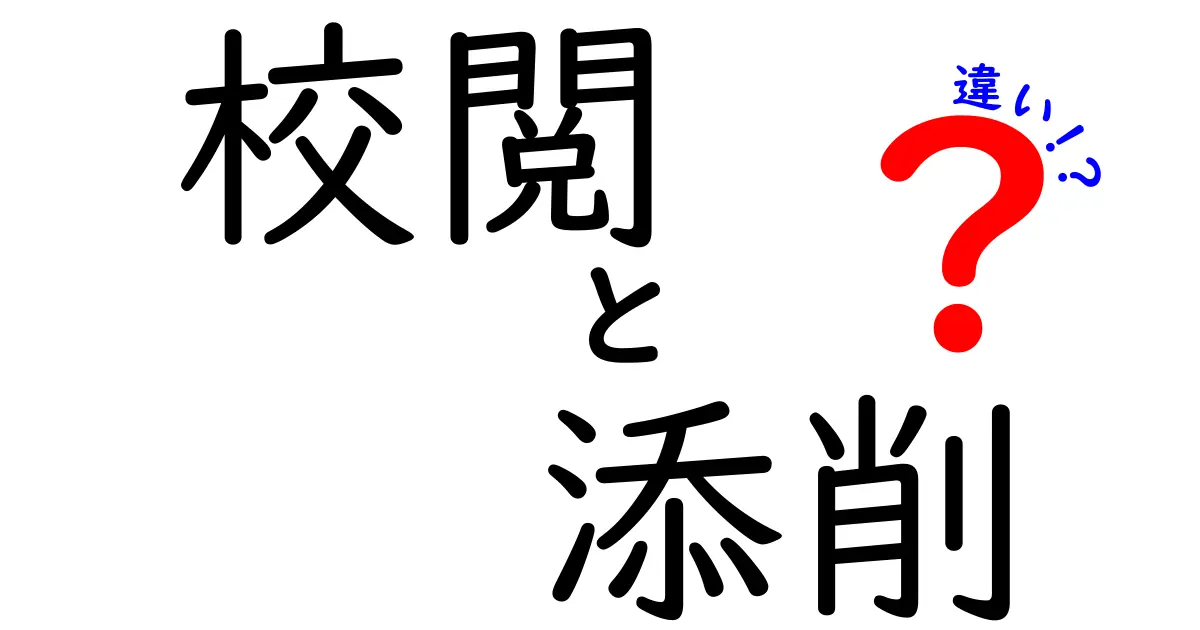

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
校閲と添削の違いを徹底解説:中学生にも分かる実務のポイント
校閲と添削は、どちらも文章をより良くするための作業ですが、目的や見るポイントが異なります。校閲は正確さと信頼性を高める作業であり、事実関係の確認、用語の統一、数字の表記、引用の出典表記、表現の適切さなど、文章全体の信頼性を確保することを第一に考えます。誤記や事実の誤り、統一性の崩れがあると読者は混乱し、発信元の信用も落ちてしまいます。だからこそ、校閲者は原稿を大きく変えずに、誤りを指摘し修正案を提示することが多いのです。阅读者が正確な情報を受け取りやすいよう、出典の確認や文体の統一なども一貫して見直します。
一方、添削は伝わり方を改善する作業で、語彙の選択や語感の調整、文のリズム、段落の構成、論理のつながり、要点の強調など、読み手に伝える力を高めることを重視します。添削は著者の意図を壊さずに、読み手が理解しやすく、興味を持ち続けられるように文章の表現を整えます。実務では、まず校閲で正確さを確認し、その後添削で読みやすさと表現の魅力を高める順番で進むことが多いのです。ここが二つの大きな違いであり、両方を上手に組み合わせると文章の品質が大きく向上します。
具体的な場面とねらい
実務の現場では、校閲と添削をどう使い分けるかが重要です。校閲を必要とする場面としては、ニュース記事、学術論文、政府広報、企業の公式資料、学習教材など、事実関係が問われる場面が挙げられます。これらは誤情報による混乱を避け、信頼性を守ることが最優先です。
一方、添削を必要とする場面は、作文指導、ブログ記事、プレゼン資料、広告コピーなど、伝えたい内容が読者に正しく伝わることが重要なケースです。読みやすさや伝え方の工夫によって、伝えたい要点がより強く伝わります。
つまり、校閲は"正確さの担保"であり、添削は"伝わり方の改善"だと覚えておくと混乱しにくいでしょう。
結局、校閲と添削は目的が異なる専門的な作業ですが、実務では互いに補完し合う関係です。正確さを崩さず、伝えたい情報を読者に正しく、分かりやすく伝えるためには、両方の視点を持つことが大切です。文章の種類や読者層に応じて、どの順番でどの程度の修正を行うべきかを判断できる力が、良い文章を生み出す鍵となります。
放課後、友だちと作文の話をしていて、校閲と添削の違いについて雑談が始まりました。彼は「校閲は事実の正確さを守る作業だよ」と言い、私は「添削はどう伝えるかの工夫をする作業だね」と返しました。私たちは、学校の宿題や部活動の報告書で、まず事実を確認して誤りを直す校閲を丁寧に行い、次に読み手が読みやすいように文章の流れや語彙を整える添削を行うべきだという結論に至りました。結局、正確さと伝え方の両方を大切にすることが、良い文章を作るコツだと気づいたのです。
次の記事: 発行者と編集者の違いを徹底解説|誰が何を決めるの? »





















