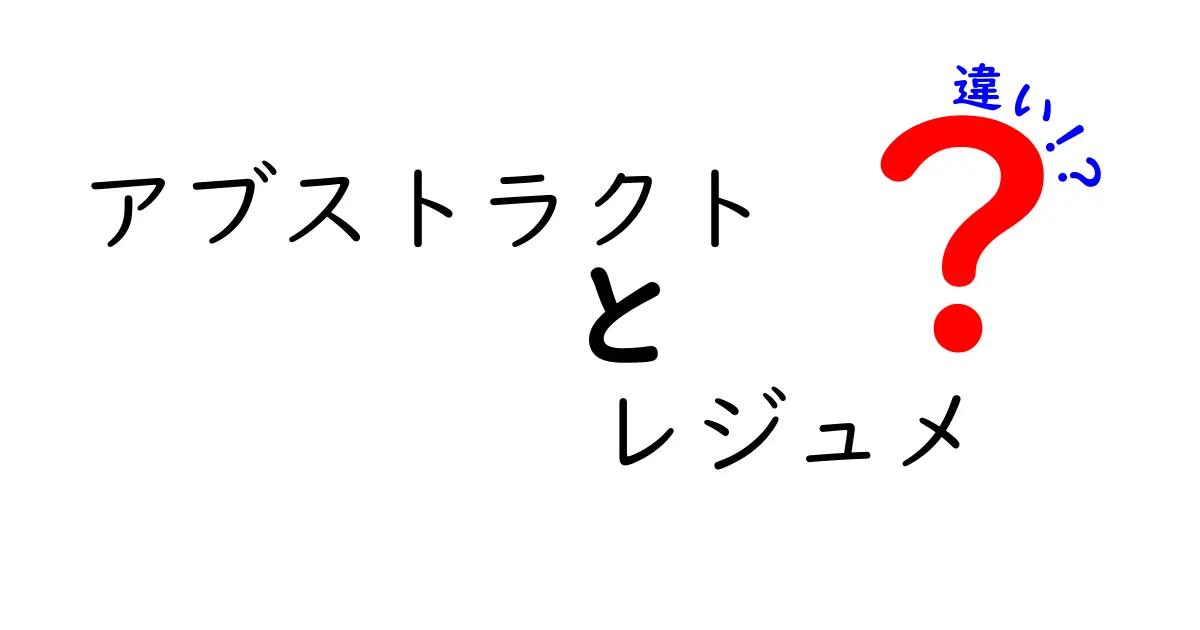

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
アブストラクトとレジュメの基本的な違い
この話を始める前に、まず大事な前提を揃えましょう。アブストラクトとレジュメは、どちらも「内容を短くまとめた文章」ですが、目的が全く異なります。アブストラクトは論文や研究の要点を読者に伝えるためのもので、研究の目的・方法・結果・結論を要約します。対してレジュメは就職活動のための自分自身の経歴の要約で、学歴・職歴・スキル・資格などを端的に示します。用途・読者・求められる情報の種類が違うため、書き方や構成も大きく変わります。この記事では、両者の違いを中学生にも分かるように、具体的な特徴と使い分けのコツを丁寧に説明します。
まずは、結論だけ知りたい人のために要点を整理します。アブストラクトは学術的な資料の先頭に置かれ、本文の全体像を短く伝える文章、レジュメは就職活動のための個人情報の要約として機能する文章です。この二つを混同すると、読者が混乱してしまうことがあります。
アブストラクトの特徴
役割は論文・研究の先頭で読者に内容を伝えることです。読者はアブストラクトだけを読んで“本文を読むべきか”を判断します。
長さは学術誌や会議の規定により異なりますが、一般的には短くても数百語程度、長すぎず読み手の集中力を保てる範囲にします。
構成は「背景・目的・方法・結果・結論」の順に整理するのが基本です。引用や長い考察は通常入りません。
文体は客観的・中立的で、著者の個人的な感想は最小限にします。読み手が本文を読みたくなるよう、情報が論理的に繋がるように書くことが大切です。
注意点は、本文の詳しいデータやグラフの説明は入れず、結論の要点だけを伝えることです。
語彙の選び方にも配慮し、専門用語は最小限に抑え、必要なら簡単な定義を添えます。
例としては、研究テーマを一目で伝え、結果がどのようにそのテーマに寄与するかを短くまとめる形が一般的です。
レジュメの特徴
役割は就職・転職活動で自分を売り込むことです。採用担当者が一目で自分の経歴・能力・価値を理解できるようにします。
長さは状況によりますが、一般的には1ページ前後、場合によっては2ページ程度までが許容されることが多いです。読み手の負担を考え、要点を絞りつつも必要な情報は漏らさないバランスを目指します。
構成は「連絡先・プロフィール(任意)・学歴・職歴・スキル・資格・活動・志望動機・自己PR」など、読みやすい順序で並べます。
文体は主体性を示す表現が多く、実績を数字や具体例で示すことが評価につながります。
注意点は、個人情報の取り扱いです。個人を特定しやすい情報や、写真・生年月日・家族構成などの記載を控えるのが一般的です。
例としては、職歴を箇条書きで示し、各経験でどんな成果を出したかを短く具体的な成果指標とともに述べる形が多いです。
実務での使い分けのコツ
就職活動と学術活動では、読者が異なります。読者が誰かを意識して書くことが大切です。
1 アブストラクトは読者を本文へ誘導するための入口です。専門用語は最小限に抑えつつ、研究の意義を短く強調します。
2 レジュメはあなた自身の価値を伝える広告です。数字・具体例・成果を前面に出して、読み手に「この人なら役に立つ」と思わせる工夫をします。
3 表現のトーンを読者に合わせること。学術誌向けには客観性を重視、企業向けには積極性・実績を前面に出します。
4 レビューの機会がある場合は、先にアブストラクトを用意し、後でレジュメの要点を抽出して使い回すと効率的です。
以下は、両者の違いを短く比較したポイントです。
- 目的:アブストラクトは研究の全体像を伝える、レジュメは自分の経歴をアピールする。
- 長さ:アブストラクトは短く、レジュメは適切な長さに調整する。
- 構成:アブストラクトは背景・目的・方法・結果・結論、レジュメは学歴・職歴・スキル・実績などを順序立てて並べる。
- 文体:アブストラクトは客観的、レジュメは自分の実績を積極的に示す。
実務での使い分けを実感するには、実際の募集要項を読み、求められている情報と語調を確認するのが一番です。就職活動用の履歴書を作成するときは、応募先の業界用語やキーワードを取り入れると効果が高まります。論文を提出する場合は、研究分野の専門用語や定義を正確に使い、読み手が研究の新しさや意義を理解できるよう配慮します。読者の立場に立って、必要な情報がすべて抜けなく、なおかつ読みやすい形で並べられているかを何度も見直しましょう。
要点の確認表として、次のようなポイントを頭に置くと整理がしやすくなります。アブストラクトは「誰が・何を・どうしたのか・結論は何か」、レジュメは「誰に・何を・いつ・どのように役立つのか」を中心にチェックします。これらを意識するだけで、同じ文章でも読者に伝わり方が大きく変わります。
まとめとよくある誤解
ここまでで、アブストラクトとレジュメの違いと使い分けのコツを整理してきました。重要なのは、用途と読者を意識して書くことです。アブストラクトを読む人は学問の入り口に立つ人であり、レジュメを読む人は雇用の判断材料としてあなたの価値を見ようとしています。
よくある誤解としては、「短ければ良い」「長ければ良い」という思い込みです。実は長さよりも「要点が的確に伝わるか」が最も重要です。もうひとつの誤解は、内容をそのままコピーして別の場面で使い回すことです。アブストラクトとレジュメは目的が違うため、改編せずそのまま流用すると失点につながります。
このガイドを参考に、まず自分の目的をはっきりさせ、次に読者を想定して、適切な要約を作ってください。最後に、実際に投稿・応募する前に友人や先生・先輩に読んでもらうと、分かりにくい表現や不適切な情報を見つけやすくなります。
友達との雑談形式で話すとき、アブストラクトは“研究の入り口の案内板”のようだね。論文を読もうとしている人に、ここから先がどう展開するのかを短く教える役割。だから難しい語彙をあまり使わず、結論までの筋道をはっきり示すのがポイントだよ。逆にレジュメは“あなた自身の自己紹介ボード”。これまでの経験や実績を、雇ってくれそうな人に伝えるための道具さ。だから数字や成果を具体的に並べ、読み手がすぐに「この人は使えそうだ」と思えるように工夫するんだ。もし友達が『どちらを作るべきか分からない』と迷ったら、まず目的を確認してから書き始めるのが一番だよ。





















