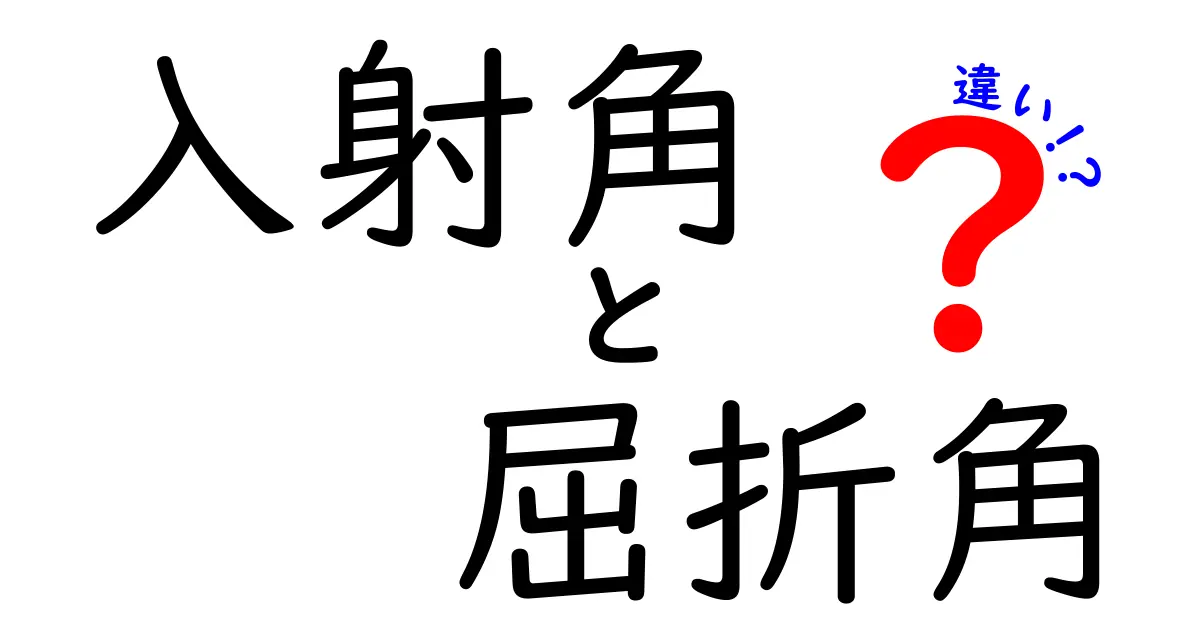

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:入射角と屈折角の基本を押さえよう
入射角とは、光が境界面に入るとき境界に対して測る角度のことです。境界の法線、すなわち境界面に垂直な直線を基準にして測定します。屈折角は、光が新しい媒質へ進む際にその境界面と法線との間にできる角度のことで、これも基準は同じ法線です。これら2つの角度は混同されがちですが、媒質が変わると進む方向が変わるという「向きの変化」を表す異なる量です。実生活でいうと、ガラスのコップに水を入れて水面を見たとき、棒が水中で少し曲がって見える現象の原因にもつながります。
この2つの角度はどのように関係しているのか、見方を整理することが重要です。
本記事では、入射角と屈折角の違いを中学生にも分かりやすく、具体的な例と図の代わりになる説明で解説します。
違いを理解するためのポイント: Snellの法則と基礎の整理
光が境界面を越えるときの道筋は、Snellの法則と呼ばれる関係式で決まります。
Snellの法則は「n1 sin 入射角 = n2 sin 屈折角」です。ここで n1 は光が出る媒質の屈折率、n2 は入る媒質の屈折率です。入射角が大きくなると、屈折角も大きくなるとは限らず、媒体の性質によって変わります。
例えば空気の屈折率は約1.00、ガラスは約1.50、水は約1.33です。空気から水へ入る場合は、同じ入射角でも水中での進む角度(屈折角)は小さくなる傾向があります。これを理解することで、なぜ鏡のように光が反射する方向や、コップの水が屈折して見える現象が起こるのかが分かります。
日常の例で理解を深める:入射角と屈折角の現れ方
日常の身近な場面で入射角と屈折角を感じられる例を挙げてみましょう。例えば、強い日光が窓ガラスに斜めから当たると、窓ガラスを通して中の景色が水彩画のようにずれて見えることがあります。これは光の進む方向が媒質の違い(空気からガラス)によって屈折角が変化するためです。
もう一つの例として、海辺で波打ち際を見た時、波の先端に向かって進む光が水面の境界で屈折することで水中の魚が別の場所に見える現象があります。これも入射角と屈折角の変化が生む見え方の違いです。
このような現象を理解するには、まず自分がどの角度で光を見ているのか、そして媒質がどのように変わっているのかを意識することが大切です。
下の表は、空気から水へ光が進むときの典型的な関係を示したものです。
この表を見て分かるように、入射角が同じでも媒質の違いによって屈折角は変わります。Snellの法則が成立しているからです。さらに、全 internally 反射が起きる境界も存在します。水から空気へ光が入るとき、ある入射角以上では屈折角がなくなり、光は境界で完全に反射してしまいます。こうした現象は船の窓や水中の生き物を観察する際にも現れて、私たちの視覚体験に大きな影響を与えます。
具体的な理解を深める:実験と観察のコツ
実験的に理解を深めるには、身近な道具を使って境界を作り、光を同じ媒質の境界に対して斜めに当ててみると良いです。懐中電灯を用意して、紙を境界として置き、鉛筆やストローで法線を描くと、入射角と屈折角を視覚的に比較できます。入射角と屈折角を紙の上で測ると、数値の関係が Snellの法則と一致することが分かります。鑑賞しながら、媒質の違いを変えることでどう曲がり方が変化するかもチェックすると、理解がさらに深まります。
まとめ:重要ポイントのおさらい
・入射角は境界面に対して入ってくる光の角度を、法線を基準に測る。
・屈折角は新しい媒質の中での進む方向の角度を、法線を基準に測る。
・Snellの法則 n1 sin theta1 = n2 sin theta2 に従い、媒質の屈折率の違いが屈折角を決める。
・媒質が変わると入射角と屈折角の関係は変わり、時には全反射が起こることもある。
・日常の観察から数式まで、角度と屈折の関係を結びつけると理解が深まる。
屈折角は光が新しい媒質へ進むときの進行方向を示す角度であり、入射角と同じ法線を基準に測る。媒質の屈折率が変わると屈折角も必ず変わるため、同じ入射角でも見え方は媒質ごとに異なる。 Snellの法則を使えば、なぜ光が水中で鉛筆のように見えるか、なぜ全反射が起こるのかを説明できる。日常の観察と実験を通して、入射角と屈折角の違いを体感することが大切だ。
次の記事: 正反射と鏡面反射の違いを徹底解説|中学生にもわかる実例付き »





















