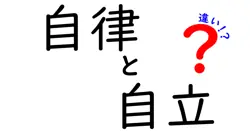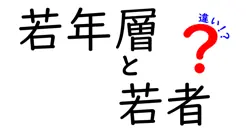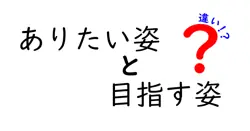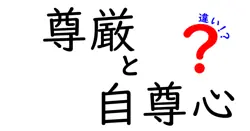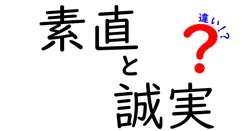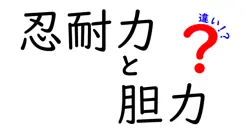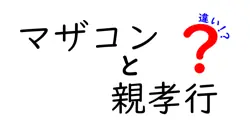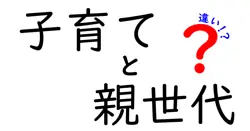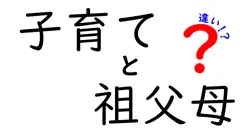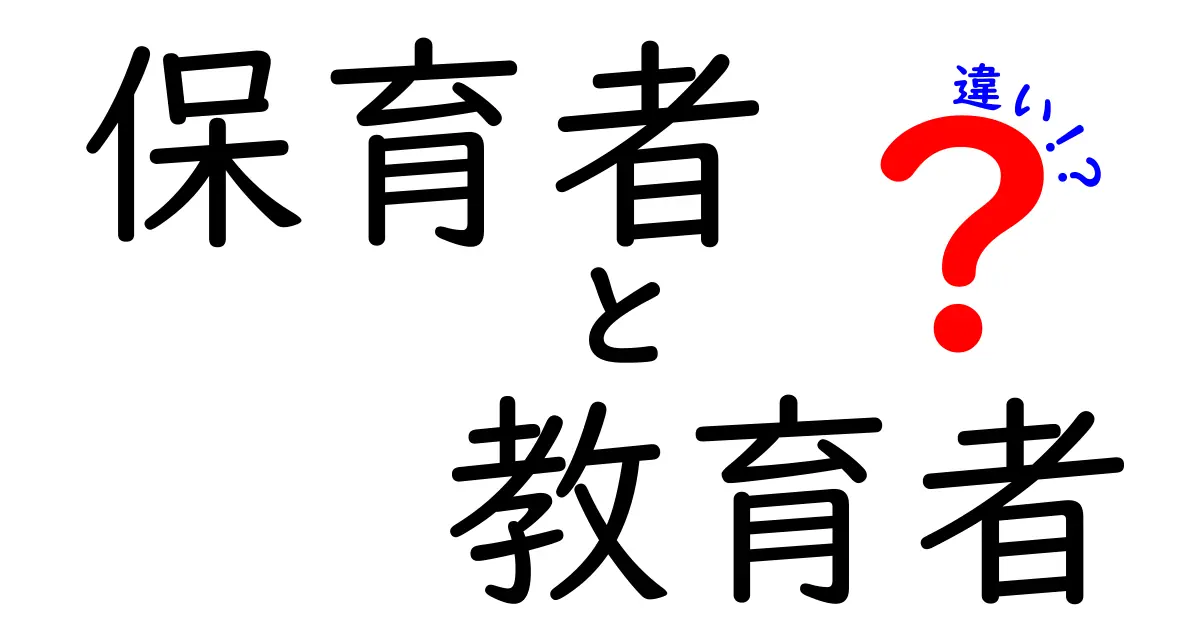

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
保育者と教育者の違いを正しく理解するための基本ガイド
このガイドでは保育者と教育者の役割の違いを、子どもの成長にどんな風に影響するかという視点で解説します。保育者と教育者は似ているようで仕事の目的やアプローチが異なり、現場での実践にも大きな差が出ます。たとえば朝の登園時、子どもが緊張しているときにかける言葉や、トイレの順番を教えるときの説明の仕方、遊びの中でルールをどう伝えるかなど、細かい場面での違いが積み重なると子どもの安心感や学習意欲にも影響します。
日常の言葉遣い、接し方、課題設定の仕方、評価の視点など、各要素を分解して考えることが大切です。
まず大切なのは「子どもの安全と安心の確保」です。食物のアレルギーに配慮する、怪我を未然に防ぐ、泣いている子を落ち着かせるなど、生活の土台を整える作業は保育の基本であり、教育の現場にも不可欠です。
安全を第一に考える姿勢は保育の基本であり、教育の現場でもそこから発展して学習過程の設計を意識します。大切なのは「生活のリズムと学習のリズムをどうつなぐか」を理解することです。
本ガイドでは具体的な場面を例に取り、どのように言葉掛けを変えるべきか、どのような場面で介入が必要かを見ていきます。現場の声を拾って分析することで、保育者と教育者の役割がどう補完し合うかが見えてきます。
保育者と教育者の主な違い
「保育者」は主に乳幼児期の生活支援と情緒の安定を担い、遊びの介入を通じて基本的な生活習慣を作る役割を持ちます。
一方「教育者」は学習課程の設計と知識の獲得を重視し、学校の場や教育プログラムの中で知識の構築を促します。
この違いを理解するには、保育の現場での関わりと教育の現場での関わりを区別する枠組みを使うとわかりやすいです。
両者は協力して子どもの成長をサポートしますが、主に関わる年齢層と目的が異なるのです。現場の実例として、朝の受け入れ時の声掛け、遊びを通じた学びの設計、生活習慣の形成の順序などを挙げて、各場面での役割の差を具体的に説明します。さらに、保護者との連携の仕方や、評価の観点の違いについても触れ、混同されやすい表現を整理します。
現場での具体的な違いとキャリア像
現場の一日を想像してみましょう。保育園では朝の受け入れから始まり、子どもの機嫌に合わせて遊びの時間を組み立て、怪我やトラブルが起きた場合には迅速に対応します。
教育者の場では授業の時間割に沿って授業を実施し、観察記録をつけながら児童の理解度を測り、宿題の出し方や補習の計画を立てます。
どちらの職種も「子どもの可能性を引き出す」という共通の目的を持つ一方で、進む道は異なります。
キャリアの選択は年齢層・場の種類・組織の方針によって変わります。
友達とカフェで雑談する形で深掘りします。Aさん: 教育者って結局何をする人なの?Bさん: 学習設計だけでなく子どもの発達を見守る長期視点が大事だよ。Aさん: なるほど、授業づくりの前に観察があるんだね。Bさん: そう、興味を引くきっかけ作り、失敗をどう学びに変えるか、保護者との連携も含めて全体設計をするのが教育者の役割だよ。
前の記事: « 2Dと3Dの違いを完全解説!中学生にもわかるやさしい比較ガイド