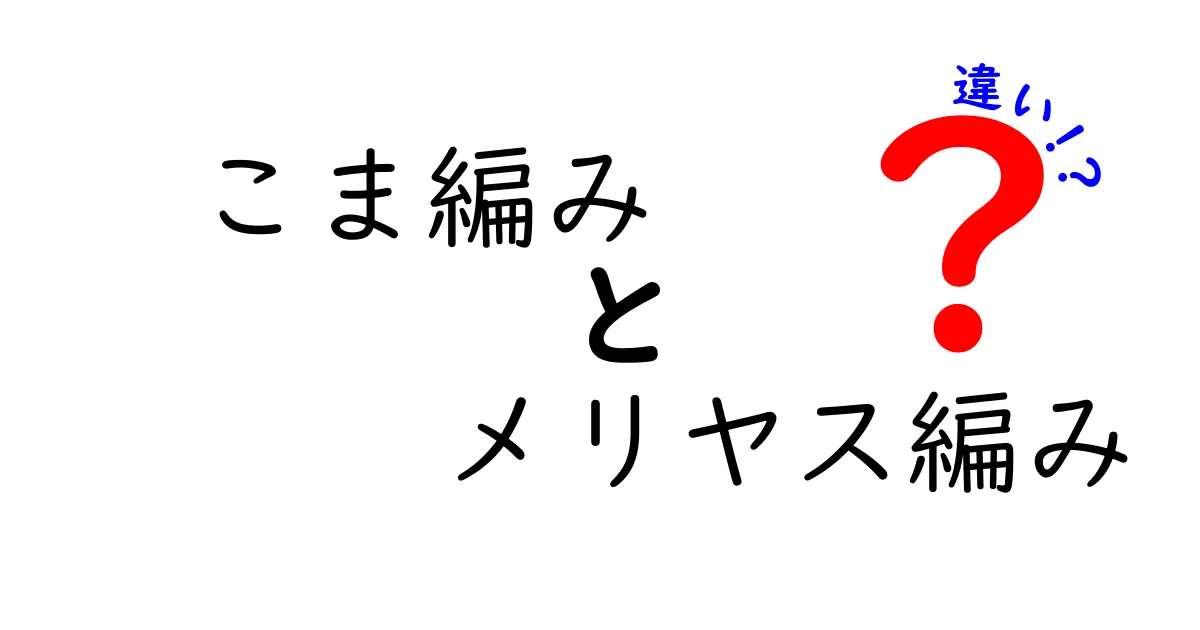

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
こま編みとメリヤス編みの違いを徹底解説!初心者が最初に知るべき編み方のポイント
こま編みとメリヤス編みは、編み物を始めたときに最初に出会う基本の技法です。どちらも糸を編んで布を作る点は同じですが、編み目の形や仕上がり、使われる場面が大きく異なります。この記事では、こま編みとメリヤス編みの違いを、「作り方の基本」「仕上がりの印象」「用途と適した作品」「練習のコツ」「よくある質問」の順で詳しく解説します。こま編みとメリヤス編みを正しく理解することで、編み物の練習がぐっと楽になり、作品の完成度も上がります。では、まずそれぞれの編み方の基本から見ていきましょう。
なお、初めての人は動画や絵を見ながら練習すると理解しやすいです。指の動きや糸のテンションをゆっくり確認し、体に合った道具を選ぶことも大切です。
こま編みとは何か
こま編みは、1目1目が立体的でつぶれにくく、布の表情が硬めに見える編み方です。棒針やかぎ針での作業でも現れますが、ここでは基本的に“鎖編みの次に出る基本の編み方”として理解します。具体的には、鎖編みの後に編み目を拾って編む形が一般的です。こま編みの特徴としては、編み目がきちんと矩形状に揃いやすく、編み地に独特の“しっかり感”が出やすい点があります。初心者にとっては、指の動きが比較的簡単で、糸のテンションを一定に保つ練習に最適です。
道具の選択としては、細すぎる糸や太すぎる糸を避け、手触りが柔らかく扱いやすい糸を選ぶと良いでしょう。作品例としては、ブランケットの表面、クッションのカバー、セーターのリブ部分など、厚みのある編み地を作りたいときに適しています。強く編みすぎると布地が硬くなりやすいので、糸の張りと編み目の大きさを意識して練習します。
メリヤス編みとは何か
メリヤス編みは、編み物の代表的な基本技法のひとつで、表編みと裏編みを交互に繰り返すことで平らで滑らかな布地を作ります。棒針編みのときは前段の頭をくるりと返して、次の段を編む動作を繰り返すのが基本です。表編みは糸が表に出ている編み地、裏編みは糸が裏に出ている編み地で、これを交互に繰り返すと布はなめらかで均一な表情になります。メリヤス編みの最大の特徴は、裏目がそのまま布の裏面になること、つまり編み地の正・反転が目立っていますが、縦方向に模様を作りやすく、身につける衣類や小物に広く使われます。初級者には、手元の糸の動きを一定に保つ練習と、段ごとの「表・裏」を間違えないようにするテクニックが重要です。
また、メリヤス編みは縮みが少なく、布地が柔らかく、肌触りが良い布地が特徴です。厚みを調整したり模様を作る場合は、減目・拾い目・増し目などの基礎技法を同時に学ぶと良いでしょう。例えば、ニット帽や手袋、セーターの本体部分、薄手のスカーフなど、日常使いのアイテムに多く用いられます。
違いを理解するポイント
こま編みとメリヤス編みの違いを理解するには、まず「編み目の形」「布地の仕上がり」「糸の扱い」「用途と適した作品」を比較するのが効果的です。
<編み目の形>こま編みは一目一目が角ばった形を作りやすく、表面が凹凸を感じられます。メリヤス編みは滑らかで平らな表面になり、表と裏で模様が連続します。<布地の仕上がり>こま編みは厚みがあり、布のハリとコシを感じる仕上がりになります。メリヤス編みは柔らかく、肌触りが良い布地が特徴です。<糸の扱い>こま編みは練習初期でも安定感があり、糸輪の動きが乱れにくいです。メリヤス編みは段数を重ねると布地の張りが出やすく、テンションのコントロールが求められます。<用途と適した作品>こま編みは厚みのあるマフラー、クッションカバー、ブランケットなど、保温性を重視する作品に向いています。メリヤス編みは衣類や薄手の布小物、滑らかな表面を活かす作品に適しています。ここで大切なのは、目的に合わせて技法を使い分けることです。
初級者が混同しやすい点として、「同じ糸でも編み方を変えると印象が大きく変わる」ことがあります。例えば、厚手の毛糸でこま編みを施すと堅めの布地になりますが、同じ糸でメリヤス編みをすると柔らかい肌触りの布になります。こうした違いを体感するには、短いサンプルを作って比較するのが一番早い方法です。
また、編み方ごとに練習の順序を変えるのもポイントです。最初はこま編みで「糸のテンションを一定に保つ練習」、次にメリヤス編みで「段の数え方と表・裏の交互」を身につけると、両技法の切り替えがスムーズになります。
編み方のコツと練習法
コツはとにかく「糸のテンションを一定に保つ」ことと「手首・指の動きをリラックスさせること」です。まずは道具選びから始めましょう。細すぎる針や硬い糸は、指先が疲れやすく、編み目が乱れやすくなります。自分の手の大きさや力の入れ方に合わせた針のサイズを選ぶことが長続きの秘訣です。練習法としては、以下の順に進めると効果的です。
1) 糸の持ち方と糸のテンションを体に染み込ませる練習
2) こま編みの基本の1段を繰り返して均一な目を作る練習
3) 表編み・裏編みの交互練習でメリヤス編みのリズムを身につける
4) 簡単な小物を作って完成度と達成感を得る
また、ミスをしても焦らず解き直すことが大切です。編み物は「けがき」や「ほどく作業」を通じて、正しい編み方を覚える学習の場です。経験を重ねるたびに、指先の感覚が鋭くなり、キレイな編み目を自分の手で作れるようになります。
いわゆる“こま編み”の話をすると、友だちのAさんはこう言いました。「こま編みって、編み地が硬めでしっかりしてるから座布団カバーとか厚地のものに向いてるよね?」と。私はそれに対して、「確かにそうだけど、同じ糸でも編み方を変えると手触りがずいぶん変わるんだ。こま編みは形がしっかりしている分、独特の張り感が出る。一方でメリヤス編みは滑らかで柔らかさが出やすい。だから、同じ糸でセーターを作るなら、こま編みを使うと型崩れを防ぎやすい一方、メリヤス編みは着心地を良くするのに向いている。こうした“選択の幅”が編み物の楽しいところだよね。その日の気分や用途に合わせて、どちらを使うかを決めるのが、編み物部の楽しみの一つだと思います。
\n




















