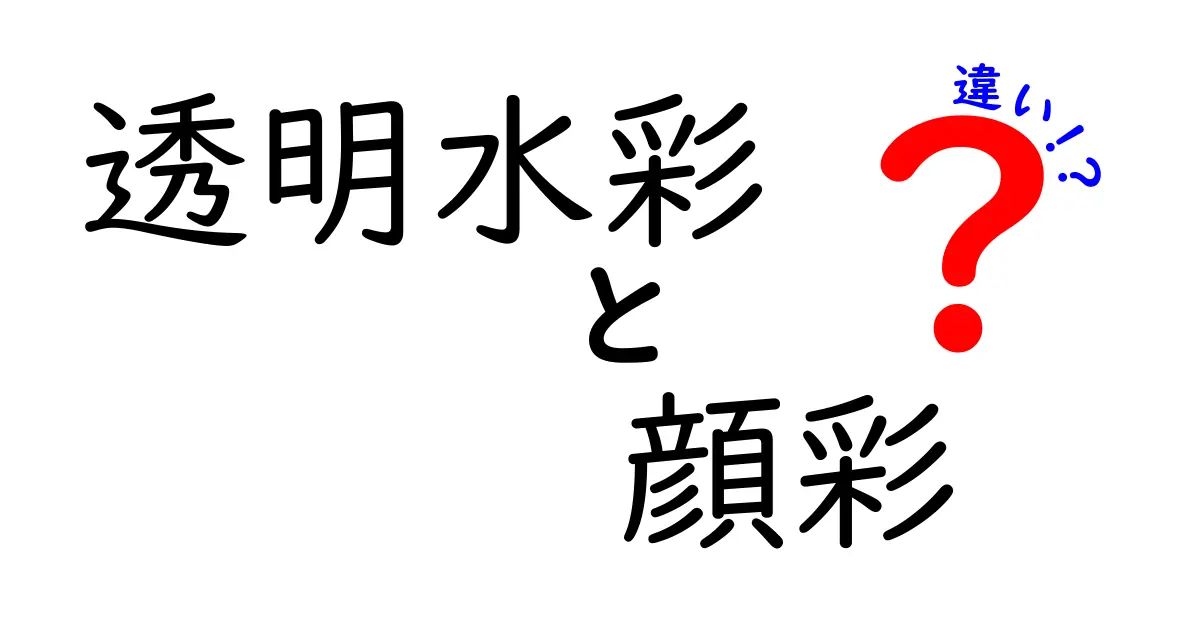

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
透明水彩と顔彩の違いを理解する
透明水彩は、水と色材を混ぜて使う絵の具で、紙の白さと下地の色を活かせるのが最大の特徴です。水の量を調整すれば、薄く淡い色から濃い色まで表現できます。特徴のひとつとして、塗れば塗るほど色が透明に重なるレイヤリング効果が出やすく、透明度を活かしたグラデーションや光の再現が得意です。
一方、顔彩は日本の伝統的な化粧用の色材として発展してきたもので、現代の画材としては水彩系の顔彩(がんさい、Gansai)も一般的です。顔彩は粉末を水で溶かして使い、塗膜が比較的不透明寄りに仕上がることが多いため、くっきりとした発色や陰影を作りやすいのが特徴です。
この二つの大きな違いは、用途と見え方、そして扱い方です。絵を描く目的なら透明水彩を選ぶ場面が多く、背景の風景や水の表現に適しています。対して、人物描写や強い色味を出したい場面では顔彩の方が適していることが多いです。
次の表は、それぞれの特徴をざっくり比較したものです。
どちらを選ぶか迷ったときの目安を知っておくと、作品の雰囲気づくりが楽になります。
この表を見れば、どんな場面でどちらを使うべきかが見えやすくなります。
さらに実践では、まず透明水彩で背景を作り、次に顔彩で人物の肌色や影の部分を丁寧に塗ると、作品全体のコントラストが明確になります。
ここからは、実際の使い分けのコツや練習法を具体的に紹介します。
使い分けのコツと練習プラン
まずは透明水彩だけで、風景や空、水の表現を練習します。薄い色を多く重ねると、光や風の動きを自然に表現できます。次に顔彩で、人物の肌色を塗る際には、下地として薄い色を何度も重ねることで、自然な陰影を作れることを覚えましょう。顔彩は乾くと厚みが出やすいので、指で薄くぼかす練習も効果的です。
また、両方を組み合わせるときは、透明水彩で下地を作ってから、顔彩ではっきりした部分を仕上げると、見た目のバランスが取りやすくなります。作品の雰囲気を決めるのは、結局のところ「どう塗るか、何を優先するか」という使い方の工夫と、練習量です。初めのうちは混同せず、道具ごとに得意な表現を覚えることが大切です。
なお、道具の手入れや保管方法も、長く良い状態を保つ秘訣です。絵具は湿度が高い場所を避け、筆は洗浄後に適切に乾燥させると、筆付きの塗り心地が長く続きます。
このように、透明水彩と顔彩は似ている部分もありますが、使い方次第で大きく雰囲気が変わります。自分の描きたい世界観を先に決め、それに合う道具を選ぶと良いでしょう。
透明水彩の世界は、色を薄く何度も重ねていく作業がとても楽しいですよね。僕も最初は一色をしっかり塗るだけで満足していましたが、透明水彩の良さは“紙の白さを生かす”ところにあります。薄い色を何回も重ねると、時間をかけて光が紙の上で折りたたまれていくような、静かな美しさが生まれます。顔彩の強い色と組み合わせると、人物の顔に立体感や陰影を出すのが難しくもあり、同時にとても楽しいチャレンジになります。練習のコツは、まず透明水彩で背景を作り、次に顔彩で主役を塗る順番を守ること。使い分けができると、作品全体の表現幅がぐんと広がります。





















