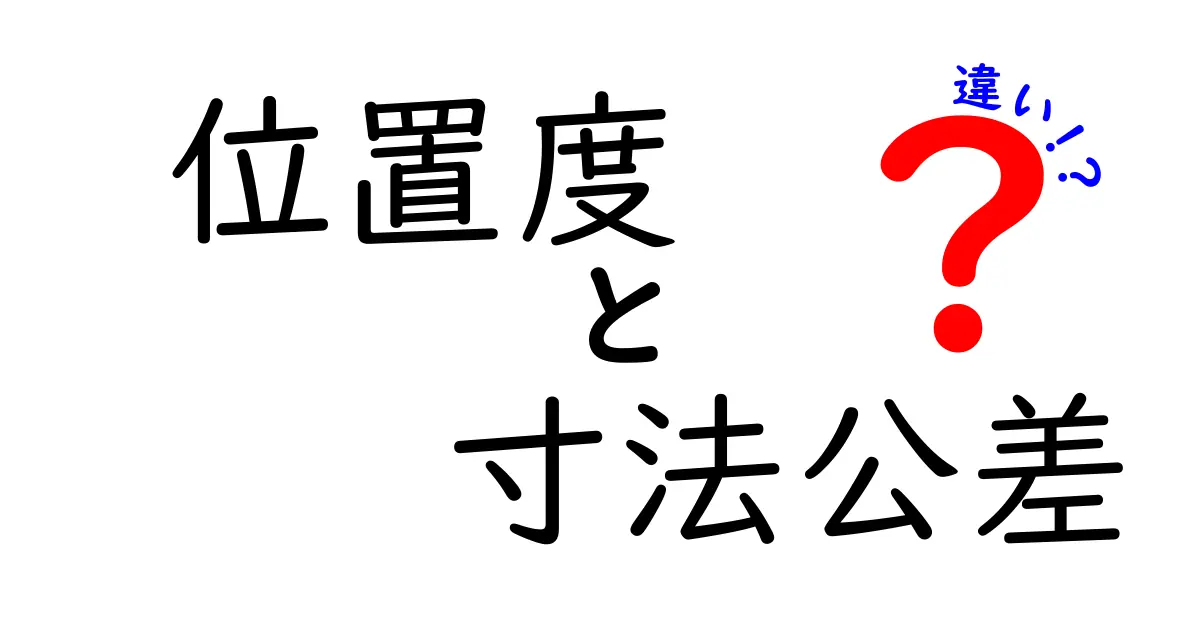

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:位置度と寸法公差の基本
機械や部品がきちんと組み立てられるには、形や位置が正確であることが必要です。そこで現れてくるのが「位置度」と「寸法公差」です。位置度は部品の穴の中心がどこにあるか、ネジ穴の中心が基準線からどれくらいずれていてよいかを決める規定です。一方、寸法公差は部品の長さや幅、厚さなどの大きさがどれくらいの幅で作られてよいかを決める規定です。違いをきちんと理解することで、図面を読んだときに「この部品はどう作るべきか」「どう組み合わせるとちゃんと動くか」が分かります。ここでは、まず頻繁に出てくる用語の意味をやさしく整理します。日常の例えを使いながら、具体的な数字の例も交えて説明します。これから出てくる用語は、現場だけでなくモノづくりの考え方全般にも関わる基本的なものです。
位置度(位置公差)とは何か
位置度とは、部品の特徴が配置されるべき位置の誤差範囲を指します。例えば穴の中心が基準となる点からどれだけずれていてよいか、またはネジ穴の中心が取り付ける相手の穴の中心と一致するかを数値で表します。図面では「位置度3次元に対して公差円・公差長方形・公差円筒」などの形で示され、データは公差帯として表現されます。ここで重要なのは、位置度を決める際には必ず基準となる参照点、いわゆる「データム」が設定されることです。データムは部品のどの面を基準にして測るのか、どの面同士を同じ座標系として扱うのかを決める要素です。これがなければ、測定結果が定義されず、製品の組み付けがうまくいかない可能性が高まります。さらに、測定は実際には公差の範囲内かを判断する作業であり、測定機器の精度、温度、作業者の手の揺れといった外的要因も影響します。したがって、実務ではデータムの選択と測定手順の統一がとても大事です。
寸法公差とは何か
寸法公差は、部品の長さ・幅・高さなど「大きさ」に関する許容範囲を表します。例えば長さ100.0mmの部品には公差±0.05mmと決められることがあります。つまり完成品は99.95mmから100.05mmの間で作られてよいのです。寸法公差は通常、ISOやJISなどの規格で定義され、寸法と公差がセットで示されます。公差の表現には等級(例えばH7やm6など)や、最小・最大の形での表現、あるいは穴と軸の関係での許容差(穴の公差と軸の公差の組み合わせ)などがあり、これを「公差帯」として図面に描きます。公差を適切に設定する理由は、部品同士を組み合わせたときに機械的な干渉が起きないようにするためです。公差が厳しすぎると製造コストが上がり、甘すぎると動作不良の原因になります。実務では部品の機能と製造能力のバランスを取りながら、公差の割り当てを行います。
位置度と寸法公差の違いを整理する
大きな違いは「何を許容するか」という点です。位置度は部品の穴・ビス穴などの“位置”を正しく揃えるための許容であり、部品が正しい場所に配置されて機械が正しく動くことを保証します。
一方、寸法公差は部品の大きさそのものの“寸法”を許容する範囲で、部品が過度に大きくなったり小さくなったりして組み付け不良や機能不全を引き起こさないようにします。
また、データムの取り方や測定方法の違いも、両者の理解を難しくする要因です。位置度は基準点のずれを測る一方で、寸法公差は長さの誤差を測るため、測定の対象と基準が異なります。現場での実務を想定すると、図面の読み方・測定の手順・公差帯の読み方・データムの設定など、複数の要素が組み合わさって全体としての品質を決めることがわかります。以下の表でも、違いを視覚的に整理しておくと理解が進みます。
日常の例と実務での使い方
身近な例で考えてみましょう。例えば自作の家具を組み立てるとき、ネジ穴の位置がずれていると扉が閉まらなくなります。これは位置度の影響です。別の例では、木材の長さが厳密に100cmでなくても、棚を綺麗に並べるために誤差を受け入れる公差の考え方が必要です。製造現場では、図面に示された公差帯を守るために、検査工程でサンプリングを取り、機械の設定値を調整します。公差を正しく設定することで、部品同士の干渉を防ぎ、動作の安定性を確保できます。
また、データムの選択は作業の効率にも直結します。どの面を基準にするか、どの穴を基準として測るか、これを統一しておくと測定の再現性が高まり、誰が測っても同じ結果が出やすくなります。最後に、設計と製造の両方の視点を持つことが大切です。設計では機能を最優先して厳しい公差を設定する場面もありますが、製造側はコストと生産性を考慮して現実的な公差を選ぶ必要があります。
表で比較する要点の追加
以下の表は、日常の判断材料として参照しやすい要点をまとめたものです。
強調点は要点の要約として覚えておくと、図面を読んだときの理解が速くなります。
| 観点 | 位置度 | 寸法公差 |
|---|---|---|
| 対象 | 配置・位置 | 寸法そのもの |
| 評価の軸 | 中心の一致・ずれ | 最小・最大の範囲 |
| 意味する成果 | 正しい組み付け・動作 | 部品の機能とコストのバランス |
位置度の話を、友だちと雑談風に深掘りしてみます。机の上の模型を作っていると、穴の位置がズレると部品がうまく嵌らず、どうしてズレるのかという疑問が浮かびます。実はデータムの選び方と測定条件が鍵です。データムが違えば同じ公差でも結果が変わってしまうことがあるのです。だから設計者と製造者が事前に打ち合わせをして、どの面を基準に測るか、どの穴を基準とするかを決めておくことが大切。そうすれば誰が測っても同じ結果に近づき、製品の品質が安定します。最後に、実際の現場では“正確さ”と“現実的なコスト”の両方を見ないといけないという話で締めくくります。
前の記事: « ctorとctrの違いを徹底解説:よく混乱する用語の正体を紐解く





















