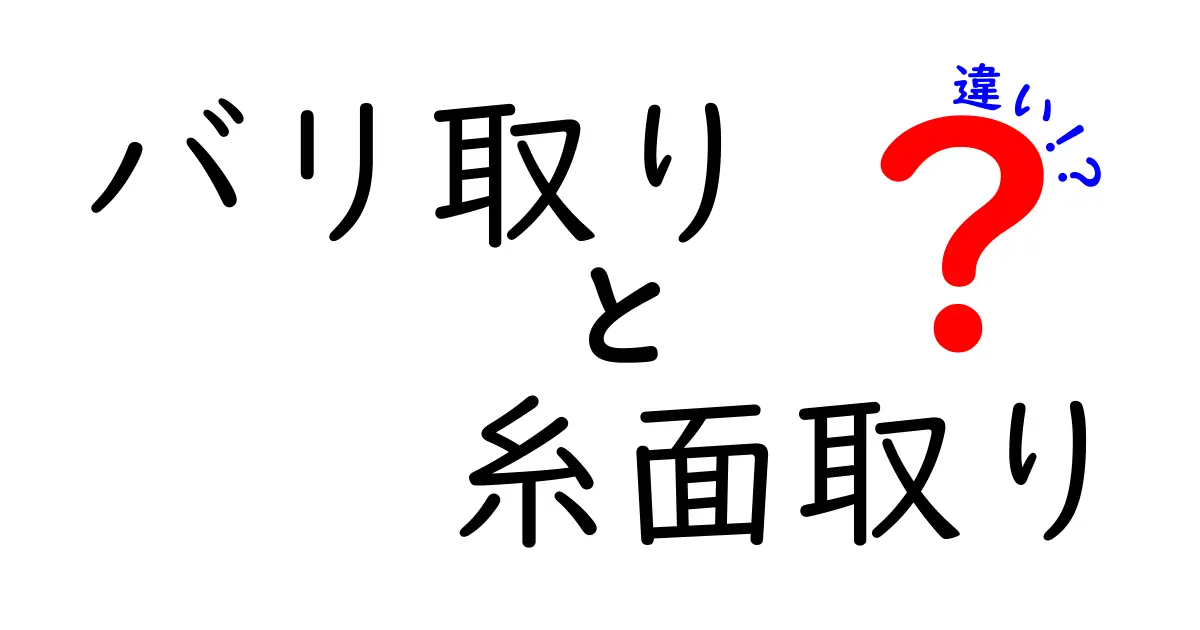

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
バリ取りと糸面取りの基本的な違い
バリ取りとは、板金や樹脂、金属の切削加工後に現れる鋭い縁や突起(バリ)を削ったり丸めたりして、安全性と機能性を高める作業のことです。バリは薄くて尖っていることが多く、触れると怪我をする恐れがあるだけでなく、組み立て時の引っ掛かりやねじの締結時の抵抗にもつながることがあります。角の鋭さを落とすだけではなく、塗装やコーティングの前処理としても重要です。
この作業は手作業と機械作業の両方で行われ、表面の均質感や美観にも影響します。
一方、糸面取りはねじ山の始点を整える加工で、ねじを相手にねじ込むときの「引っかかり」を減らすための作業です。ねじは複数の山と谷から成り、山の先端が角ばっていると挿入時に抵抗が生じ、ねじ山の食いつきが悪くなることがあります。
糸面取りはねじの機能を円滑にするための専用の面取りであり、バリ取りとは目的が異なります。
加工現場では、部品の形状と必要な仕上がりを見極めて使い分けることが求められます。
バリ取りと糸面取りの違いを理解するには、どんな部品に適用されるか、どんな道具が使われるかを知るのが近道です。例えば、穴の周囲の縁に現れるバリはドリル加工後に出やすく、外周の縁を丁寧に整えます。対して、ねじ山の先端を整えるには糸面取りを行い、ねじの挿入性と組み付け時の安定性を高めます。以下の表も具体的な違いを分かりやすく示しています。
作業の基本として、適切な力加減と視覚的なチェック、そして安全な作業環境が大切です。
どちらの作業も、仕上げ品質に直結します。適切な工具を選び、適切な力加減で作業することが重要です。初心者は最初は難しく感じるかもしれませんが、練習と安全への配慮を重ねることで、部品の適合性と耐久性が大きく向上します。
また、実務では作業手順の標準化が進んでおり、品質管理の観点からも記録と点検が推奨されます。
バリ取りの作業の基本と使う道具
バリ取りは、加工作業の最後の仕上げとして不可欠です。まず、作業前に部品を固定して振動を抑え、誤って削りすぎないようにします。主な道具としては、ファイル系の道具(丸やすり、Flatファイル)、デバリングナイフ、小型の電動バリ取り機、そして仕上げ用の研磨用ペーパーや布が挙げられます。加工の流れは、(1)バリの存在を確認、(2)角度を保って徐々に削る、(3)表面を均す、(4)指でなめらかさを確認、(5)最終チェック、という順序です。練習を重ねると、力加減を感覚で掴めるようになり、仕上がりの均一性が向上します。特に薄板や薄肉部品では、過度な力が歪みの原因になるため、慎重な作業を心がけましょう。
- 固定して振動を抑える
- 適切な工具を選ぶ
- 徐々に削って角を丸くする
バリ取りのコツは、削りすぎないことと、仕上げの表面感を均一に保つことです。経験を積むほど作業スピードと品質の両方が安定します。
糸面取りの作業の基本と使う道具
糸面取りは、ねじ山の先端部を滑らかに整える専門的な作業です。ねじを正しく挿入するためには、先端の角を少しだけ丸くしておくと入りが良くなります。使う道具は、糸面取り用の刃や、ねじ穴の入口を優しく整える丸ヤスリ、細かな仕上げには専用の面取り工具や微細な砥石が適しています。作業の流れは、(1)ねじ山の状態を点検、(2)挿入方向をそらさずに角を落とす、(3)表面を清掃して清浄な状態にする、(4)実際にねじを通して動作を確認、という順序です。糸面取りは、ねじ・ねじ穴の長寿命化と組み付けの信頼性を大きく左右します。慣れていないとねじ山を傷つけることがあるので、ゆっくり丁寧に進めることが重要です。
- ねじ山の状態を事前に点検する
- 角を落とす程度の弱めの力で作業する
- 仕上げ後は清掃して粉塵を取り除く
糸面取りは、ねじの挿入性と組み付け時の安定性を高める重要な工程です。適切な道具と正確な手順を守れば、長寿命のねじ接合を実現できます。
糸面取りは、ねじの入口の角をほんの少しだけ丸める作業です。最初は難しく感じるかもしれませんが、道具の使い方を覚えるとねじがすっと入る感触が嬉しくなります。私は高校の工作部で初めて糸面取りを学んだとき、角を落とすだけでねじがスムーズにかみ合う体感を覚えました。力を入れすぎると山を傷つけるので、優しく丁寧に進めるのがコツです。経験を積むと、部品の組み付けがぐんと楽になります。





















