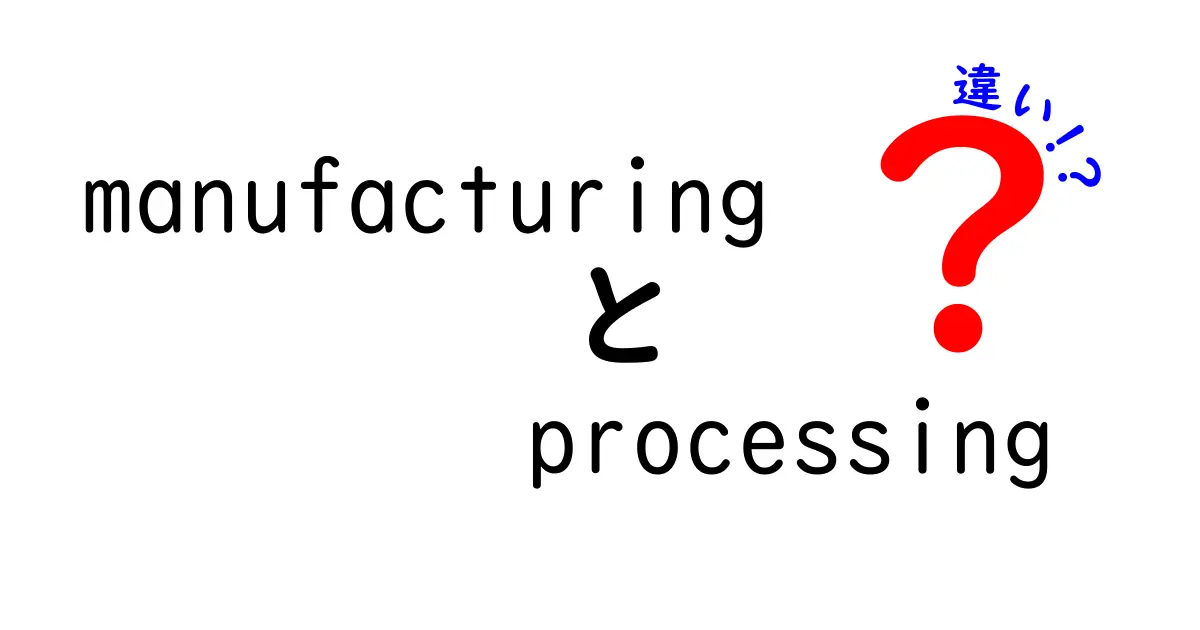

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
manufacturingとprocessingの違いを徹底解説:中学生にもわかる製品づくりの基礎
製造業という言葉を耳にすると、私たちは「何かを作ること」と思い浮かべます。では manufacturing と processing は同じ意味なのでしょうか。実は英語の使い方が少し違い、現場での意味も異なります。本記事では、学校の授業だけでなく実際の工場の動きにも触れながら、両者の違いを丁寧に説明します。まずは結論から言うと、manufacturing は「完成品を作るための全体的な工程」を指し、processing は「材料を加工して形を作る、あるいは部品を作るための前段階の作業」を指すことが多いです。ここには素材の性質を変えたり、サイズを整えたりといった具体的な操作が含まれます。
この違いは、私たちが日常で使う場面にも現れます。例えば食品業界では「製造」が品質管理と全体の生産計画を意味し、「加工」は原材料を細かく砕く、刻む、混ぜるといった前処理を指すことが多いです。金属や樹脂の工場では、加工は部品を作る前の形状変更の作業を指すことが多く、製造はその加工された部品を組み合わせて機械や車を作る大きな工程を表します。
このような区分は、どの企業や教材にも少しずつ違いがありますが、共通して言えるのは「加工」が材料の形や性質を変える具体作業であり、「製造」が完成品へと組み上げる大きな流れだ、という点です。
本記事のねらいは、学校で英語の授業だけでなく、現場の現実と結びつけて理解を深めることです。読み進めるうちに、業界用語の使い分けが理解でき、将来、工場見学やインターンシップに参加するときにも役立つ考え方が身につくでしょう。さあ、具体的な違いを見ていきましょう。
製造と加工の両方を一つのチームとして捉え、どんな作業がどの段階で行われるのかをイメージしてみてください。
そもそも「manufacturing」と「processing」はどう意味?
英語の語源と実務の違いを分けて考えると理解が深まります。manufacturing は工場全体の活動を含み、設計、資材の調達、ラインの組み立て、品質管理、出荷までを統括する大きな流れを指します。対して processing は原材料を加工する具体的な操作のことを指します。例えば金属の切断、樹脂の成形、木材の切削など、素材そのものを変化させる作業です。現場では加工が完了する段階で「部品」が出来上がり、これを「組み立てる」または「仕上げる」ことで製品となります。つまり加工は製造の一部であり、製造は加工を含むもっと広い工程です。さらに、用語の使われ方には業界ごとの差もあり、電子部品のように加工の結果を検査で保証する分野では「加工」という表現が多く使われ、完成品の品質保証を強調する文脈では「製造」という言葉が中心になることがあります。
日常の教育現場でも、この区別を説明するときは「加工は形を整える、寸法を合わせる、材料の性質を変える、加工機を使う作業」というイメージを使います。製造はそれらの加工を組み合わせて、最終的な商品の機能・デザイン・価格を決める大きな枠組みと考えると分かりやすいです。実際の工場を想像すると、原材料を受け取り、加工機で成形し、部品を組み立て、検査を経て、最終的な製品として出荷するという一連の流れが見えてきます。その中で加工と組み立て、検査がそれぞれの役割を果たします。
本記事のねらいは、学校で英語の授業だけでなく、現場の現実と結びつけて理解を深めることです。読み進めるうちに、業界用語の使い分けが理解でき、将来、工場見学やインターンシップに参加するときにも役立つ考え方が身につくでしょう。さあ、具体的な違いを見ていきましょう。
製造と加工の両方を一つのチームとして捉え、どんな作業がどの段階で行われるのかをイメージしてみてください。
実務の現場での使い分けと具体例
ここでは具体例を見ながら違いを確かめます。たとえば自動車の部品を作る場合、アルミの板を切って穴をあける作業は加工の代表です。さらにこの加工された部品をボディに取り付け、電装部品を組み合わせ、塗装や検査を経て車が完成します。食品業界でも同様の考え方があり、野菜を洗浄・カットして適切な大きさや形にするのが加工、できあがった素材をパッケージに詰めて出荷するのが製造です。ここで大切なのは「どの段階で何をしているか」を整理することです。加工は材料を“形に変える作業”、製造はその形にした部品を組み立て、仕上げ、検査して完成品へと導く工程です。
さらに表現の観点から整理します。加工 には「変形・切削・成形・混合」などの技術が含まれ、製造 には「設計・流通・品質保証・組立・出荷」など、トータルの視点が含まれます。実務では、工程間の連携がほんとうに大切で、加工の品質がその後の製造の品質を決めることが多いです。ここで大切な考え方は、加工と製造を別々の作業として捉えず、全体を連携する一連の流れとして理解することです。そうすれば、現場の問題点や改善点を見つけやすくなります。
友達とカフェで話していたとき、加工と製造の話題になって、友だちが“加工は形を整える、寸法を合わせる、材料の性質を変える作業だよね?”と言い、それに僕は“製造は加工を含むが、それに部品の組み立てや品質管理、出荷まで含む大きな流れを指すんだ”と答えました。実際の工場を想像すると、加工は切る・削る・混ぜるといった具体的操作、製造はその加工済みの部品を組み立てて車や家電を作る全体の旅路です。こうした用語の違いを知ると、技術の話がぐっと身近に感じられ、授業の理解も深まります。
次の記事: kshとshの違いを徹底解説:どちらを使うべき? »





















