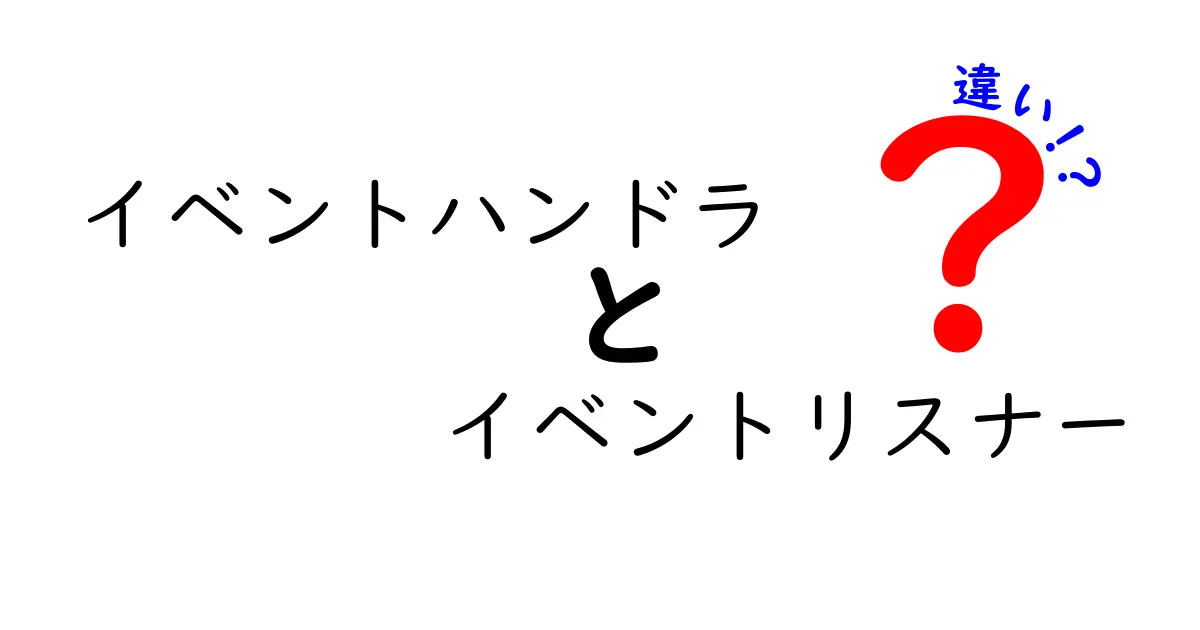

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
イベントハンドラとイベントリスナーの違いを徹底解説!中学生にも分かる実践ポイント
このコラムでは、ウェブ開発やプログラミングでよく耳にする「イベントハンドラ」と「イベントリスナー」の違いを、難しく感じずにわかりやすく解説します。まず前提として、イベントというのは何かが起きた合図のことです。私たちは、ボタンをクリックしたり、ページをスクロールしたり、文字を入力したときに起こる様々な出来事を"受け取って対応"します。その時に使われるのが「イベントハンドラ」と「イベントリスナー」です。
ここで大切なポイントは、どちらも“イベントが起きたときに実行される処理”を用意する道具だということ。しかし呼び方や使い方に差があり、使い分けることでコードの読みやすさや保守性が変わってきます。
この文章を読んでいるあなたが、きっとすぐにでも自分の作るサイトやアプリの挙動を思い通りに動かせるようになるよう、具体的な場面での使い分け方や実務でのコツを丁寧に紹介します。
なお、実務ではHTMLとJavaScriptの文脈で話を進めますが、他の言語でも似た概念が多くあるため、全般的な考え方として覚えておくと役立ちます。
まずは結論から言うと、「イベントハンドラ」はイベント発生時に実行される関数そのものを指すことが多いのに対し、「イベントリスナー」はその関数をイベントシステムに登録する仕組みのことを指すことが多い」という点が基本的な違いです。
以下では、それぞれの意味と使い方、そして実務での使い分けのコツを順に見ていきます。さらに最後には、要点をすぐに確認できる比較表と、典型的な誤解を避けるためのポイントを追加します。
この知識を身につければ、ボタンを押したときに何がどう呼ばれるのか、
どの順番で呼び出されるのか、そして不要になったときにどう消せばいいのか、をきちんと把握できます。
それでは、具体的な差分を見ていきましょう。
イベントハンドラとは
イベントハンドラとは、イベントが発生したときに実行される「関数そのもの」や「関数の呼び出し元となる処理のことを指します。ウェブ開発の文脈では、例えばボタンのクリックに対して何らかの処理を行いたいとき、onclickというイベントプロパティに対して関数を割り当てる形のことが多いです。具体的には、
button elementの onclickに対して handler として定義した関数を割り当てると、ボタンをクリックした瞬間にその関数が実行されます。
この場合「イベントハンドラ」はその関数そのものを指すことが多く、
「この関数がイベントを受け取って何をするか」が中心になります。
例を言葉で説明すると、
「クリックされたらメッセージを出す」という処理を、イベントハンドラとして作成します。
そしてそのハンドラを、ボタンの onclick 属性に割り当てることで、実際のクリックイベントが起きたときに呼び出される仕組みです。
このやり方の利点はシンプルで分かりやすい点ですが、同じ要素に別のイベントを同時に扱いたい場合には工夫が必要です。
また、ひとつのプロパティに複数の関数を割り当てることは難しく、後から差し替えると今までの動作を維持できなくなることがあります。
この章の要点は以下のとおりです。
・イベントハンドラはイベントが起きたときに実行される関数のこと
・onclickのようなイベントプロパティに割り当てる形が代表的な使い方・単一の処理として分かりやすいが、拡張性には限界があることもある・削除や差し替えの際にはプロパティを直接書き換えることが多い
この理解を土台に、次のイベントリスナーの章へ進みましょう。
イベントリスナーとは
イベントリスナーとは、イベントが発生したときに呼び出される関数を、「イベントシステムに登録する仕組み」そのものを指します。ウェブ開発では addEventListener を使って、同じ要素に複数のリスナーを登録できる点が大きな特徴です。複数のリスナーを登録しておけば、同じイベントに対して複数の処理を順番に実行できます。
この仕組みの利点は「複数の処理を連携させられる」「後から追加・削除がしやすい」「イベントの伝搬(捕捉・バブリング)を細かく制御できる」点です。捕捉フェーズとバブリングフェーズの選択、あるいはキャンセルの扱いなど、思いのほか細かい挙動まで制御可能です。
具体例として、ボタンに対して複数のリスナーを登録するケースを考えます。1つのクリックで、メッセージを表示し、同時にサーバへ通知し、さらに別のUIを更新するといった複合的な処理を、個別のリスナーに分割して実装できます。秋葉原の雑踏を思い浮かべるように、複数の人が順番に反応するイメージです。
この章の要点は以下のとおりです。
・イベントリスナーは addEventListener によって登録する仕組み
・同じイベントに対して複数のリスナーを追加できる・リスナーは捕捉・バブリングの伝搬モードを選べる(キャプチャ・デフォルトはバブリング)・削除には removeEventListener を使う
・複雑な挙動や拡張性が求められる場面で有用
次のセクションでは、ハンドラとリスナーの実務的な使い分けをまとめます。
違いの要点を実務でどう使い分けるか
実務での使い分けのコツを、実際の場面を想定して整理します。 この table には、実務でよくあるケースを3つ挙げました。結局のところ、 シンプルな挙動にはハンドラ、複雑で拡張性のある挙動にはリスナーを使い分けるのが現実的です。 ここまでの話を、簡単な実用例で腹落ちさせましょう。 以下の表は、イベントハンドラとイベントリスナーの違いをもう一度整理したものです。表を読み返すだけでも理解が深まるはずです。 友達とおしゃべりしているときの雑談風にいうと、イベントハンドラは「この動きをする関数そのもの」、イベントリスナーは「その動きを起こすための“登録ボタン”みたいな仕組み」と考えると分かりやすいよ。例えば、友達がスマホで写真を撮るとき、シャッターを押すのがイベントハンドラ、同じ状況で“撮る・保存する・共有する”を順番に行う3つの作業を登録しておくのがイベントリスナー、みたいなイメージ。そうすると、あとから新しい処理を追加したいときに、ハンドラの関数をいじるよりリスナーの登録を増やすだけで対応できる場面が増えるんだ。 前の記事:
« クリック必至!indexとindirectの違いを徹底解説
1つの要素に対して、単純な反応だけを求める場合は「イベントハンドラ」を直接割り当てるのが手早くて分かりやすいです。
一方、同じイベントで複数の処理を順番に走らせたい、あるいは動作を後から追加・削除したい場合は「イベントリスナー」を使うのが賢い選択です。
2つの方法を併用することもできますが、混在させるとコードが複雑になりやすいので、構造をしっかり分けて管理するのがポイントです。
以下の比較表を見てもらうと、どの場面でどちらを使えばよいかが見えやすくなります。 項目 イベントハンドラ イベントリスナー 割り当て方 単一の関数をイベントプロパティに割り当てる addEventListenerで複数の関数を登録可能 削除方法 プロパティを null などに設定して削除 removeEventListenerで個別に削除可能 複数処理 基本的に1つの処理に向く 複数の処理を組み合わせられる ble>伝搬の制御 伝搬の制御は難しいケースが多い 捕捉/バブリングのモードを選べる
ただし、プロジェクトの方針や既存コードのスタイルに合わせることも大切です。新しいコードを書くときは、将来の保守性を考えてリスナーを採用するのが多くの場合おすすめです。
最後に、すぐに使える実践のコツを2つ紹介します。
・イベントを登録する際は、どのイベントを拾うのか、どのタイミングで実行したいのかを事前に整理すること。
・不要になったらすぐ removeEventListener を使って解放する癖をつけること。これにより、メモリ leaks を防ぎ、アプリのパフォーマンスを安定させられます。以上が、違いを実務で活かすための基本的な考え方です。
なお、実務ではイベントの性質(クリック・入力・スクロールなど)や、ブラウザの挙動(キャプチャ/バブリング)を踏まえた上で、最適な方法を選ぶと良いでしょう。実用例とヒント
例1: 単純なボタン1つに対して1つの動作だけをさせたい場合、イベントハンドラを用いると分かりやすくコードがすっきりします。
例2: 同じボタンに対して、クリック時にUI更新とデータ送信という2つの処理を同時に行いたい場合、イベントリスナーを使って2つの関数を順番に実行させます。
例3: 複数の要素で同じイベントを扱う場合は、イベントリスナーを使って共通の関数を複数の要素に登録することで、コードの再利用性が高まります。
このように使い分けると、後からコードを見直すときにも理解しやすく、修正もしやすくなります。
最後に、重要なポイントをもう一度まとめておきます。
・イベントハンドラは関数そのもの、・イベントリスナーは登録する仕組み、・複数の処理が必要なときはリスナーを活用、・削除は removeEventListener が基本。
この3点を押さえるだけで、イベント周りのコードはぐんと扱いやすくなります。
以上が、イベントハンドラとイベントリスナーの違いを、中学生にも分かるように整理した解説です。この記事の補足情報
表は要点を短く切り出していますが、実務ではこの差を意識してコード設計を行うと、後での修正が楽になります。
もしこの話題をさらに掘り下げたい場合は、次のトピックもおすすめです。
・イベント伝搬(捕捉とバブリング)の挙動の詳解
・removeEventListener の使い方と注意点
・ハンドラとリスナーの組み合わせパターン
この話題は、コードの見通しを良くするための“整理整頓のコツ”でもあるから、まずは1つの要素に1つの処理を割り当てる癖をつけつつ、徐々に複数処理の組み合わせへと拡張していくといいよ。
ITの人気記事
新着記事
ITの関連記事





















