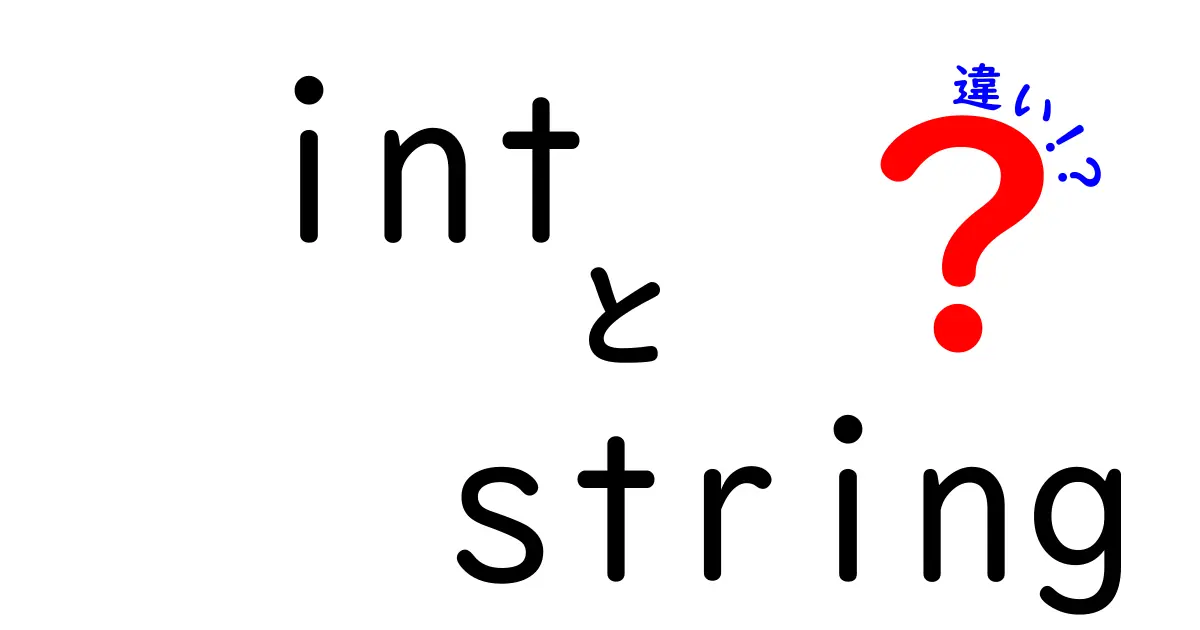

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
intとstringの違いを徹底解説:基礎から実践まで詳しく学ぶ
整数を表すデータ型である「int」と、文字列を表すデータ型である「string」。どちらもプログラミングを始めると必ず出てくる用語です。
ここでは「意味」「使いどころ」「取り扱いのコツ」を中学生にもわかりやすい言葉で丁寧に説明します。
まず大切なのは、「intは数値そのものを扱い、stringは文字の列を表す箱」という点です。例えば、5 という数字はintとして扱われ、文字列として扱われるのは 5 ではなく「5」という文字の列です。これだけで、両者の根本的な違いが見えてきます。
この違いを理解することは、後でプログラムを組むときのミスを減らす第一歩です。
次のポイントとして、型の変換があります。数値を文字列へ変換するには toString(または文字列連結)を使い、逆に文字列を数値に変換するには parseInt や int() などの関数を使います。
この変換を間違えると、思わぬ結果になることがあります。例えば端末入力で空文字列が来た場合の処理などです。こうしたケースをあらかじめ想定しておくと、後でデバッグが楽になります。
例として、int a = 5; string s = こんにちは などの表記は言語により形が変わりますが、意味は同じです。
計算にはintを用い、文字情報にはstringを用いるのが基本です。
例えば、アイテムの個数を数えるときはint、アイテムの名前を表示するときはstringです。
- 手元のデータが数値ならintを使う
- データに文字が混ざるならstringを使う
- 計算と表示の場面で変換を挟む場面が多い
ここまでを押さえると、プログラムを読むときの判断が早くなり、後のトラブルを減らせます。
また、コードの読みやすさ、保守性、バグの減少にもつながるのがこの違いの学習の利点です。
難しく感じるかもしれませんが、最初は5 という数字と 5 という文字列の区別を理解するところから始めましょう。
この段階を越えると、変換の仕組みや、文字列を数値に直すタイミングが自然と分かるようになります。
使い分けのポイントと実例
実際のプログラムで int と string を使い分けるときは、データの性質をまず確かめることが大切です。
このとき、外部から来るデータは多くの場合文字列として受け取られます。入力された年齢や数値のカウントなど、演算に使う場合は文字列から数値へ変換する処理が必要です。変換を適切に行わないと、計算結果が正しく出なかったり、エラーが発生したりします。
具体的には、数値として扱いたいデータは int に格納し、テキストとして表示したいデータは string に格納します。変換の際には言語特有の関数を使いますが、変換が失敗するケースにも備えるべきです。例えば端末入力で空文字列が来た場合の処理などです。こうしたケースをあらかじめ想定しておくと、後でデバッグが楽になります。
さらに、文字列は長さや内容によって扱い方が変わります。長い文字列を操作する場合はメモリの使い方に気をつけ、頻繁に結合する処理は新しい文字列を都度生成してしまう非効率を避けるべきです。実装言語ごとに最適化のコツは異なりますが、共通して言えるのは「不要な変換を増やさず、必要なときだけ変換する」ことです。
この考え方を持つと、コードの可読性と信頼性が高まり、バグの発生を未然に減らせます。
最後に、デバッグの現場で役立つ具体的なヒントをいくつか挙げます。データを受け取った瞬間に型をログへ残す癖をつける、数値と文字列が混ざる計算式には必ずキャストを入れる、テストケースには大小さまざまな入力を用意する、などです。こうした手法を習慣化すると、問題が起きても原因を素早く特定できるようになります。
放課後の部活動の合宿準備で、友達のミキと話していたときのこと。ミキは『intって本当に数字だけ?文字列とはどう違うの?』と尋ねた。僕は『うん、見た目はどちらもコードの中の値だけど、中身が違うんだ。数値として使うときはintを選ぶ。文字列として使うときはstringを選ぶ』と説明した。さらに、実際のコード例を見せ、数字をそのまま文字にするべき時と、文字列から数値へ変換するべき時の判断基準を一緒に考えた。こうした日常の会話が、プログラミングの学びを深めるきっかけになる。
次の記事: jpaとjpbの違いを徹底解説!初心者にも分かる比較ガイド »





















