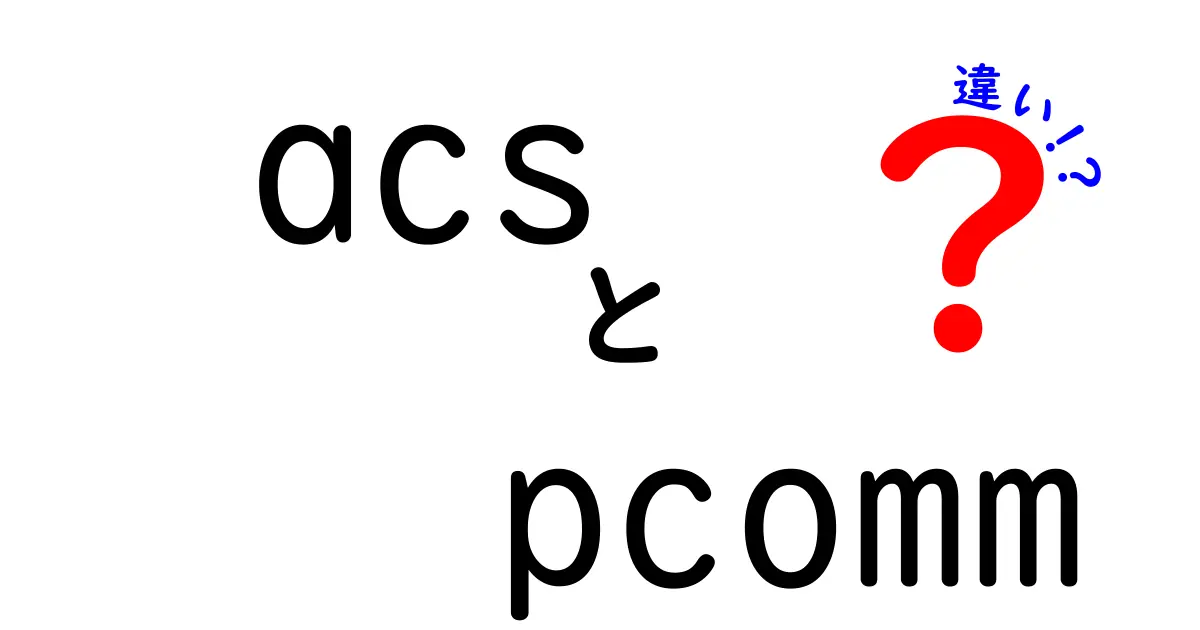

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
acsとpcommの違いを知ろう: 実は何が違うのかをやさしく解説
このキーワードを検索する人には、研究者だけでなく高校生や科学好きな中学生も多いです。ACSとPCommは化学の世界でよく目にする略称ですが、指す意味は全く違います。まずACSはAmerican Chemical Societyの略で、組織そのものと出版活動の両方を含む大きな存在です。学会が提供する会員サービスや学術イベント、雑誌の編集・発行など、さまざまな活動を指すことが一般的です。これに対してPCommはPhysical Chemistry Chemical Communicationsなどの特定の学術誌の略称として使われることが多く、物理化学の分野で短報を中心に発表される場として読まれることが多いです。つまりACSは全体の組織・枠組み、PCommは特定の雑誌名である、という違いを押さえると混乱が少なくなります。
この理解を具体的な利用場面で見ると、出典の表記がどう変わるかが分かりやすくなります。例えばACS Publicationsが刊行するジャーナル名が続くこともあり、出典の記述として的確に伝わる場面が多いです。たとえばACS Publicationsが刊行するジャーナルの中の一つを指すことや、単に「ACSが提供する研究成果」といった意味として扱われることもあります。一方でPCommとだけ書かれている場合は、特定の雑誌名を指しているケースがほとんどであり、論文の本文や出典欄にはその雑誌名がはっきりと示されます。
この違いを覚えておくと、論文の出典や情報源を誤解するリスクを減らせます。日常の勉強の中で、略称だけを見て判断せず、正式名称や発行元を合わせて確認する癖をつけると良いでしょう。
ACSとPCommの使い分けのコツと具体的な場面の解説
実務や学習の場面では、次のポイントを意識すると混乱を避けられます。論文の引用欄でACSと書かれていても、出典は一つのジャーナル群を指す場合があり、具体的にはACS Publicationsが刊行するジャーナル名が続くことがあります。対してPCommが使われている場合は、通常は物理化学分野の短報誌として名指しされ、読者層は研究の初期段階や速報的な結果を追う人々です。次に、アクセスの仕組みも違います。ACSのジャーナルは多くが購読制で、大学や研究機関の契約により閲覧できることが多いですが、最近はオープンアクセスの選択肢も増えています。一方でPCommのような特定誌は、出版社の方針次第でオープンアクセスの機会がある場合とない場合があります。研究を進めるうえで、こうした実務的な情報を前もって知っておくと、論文検索の速度が上がります。さらに、研究者同士の会話での理解を深めるには、略称の背景だけでなく、分野ごとの専門用語や研究の目的、短報の特徴(新規性が重視されること、実験の再現性の簡略化が求められる点など)を押さえると良いでしょう。最後に、ACSとPCommの違いを日常の会話で使い分ける練習として、身近な教材やニュース記事の出典を読み比べてみるのがおすすめです。
ある日の図書館で、友人と本棚の前でACSとPCommの違いについて話した。友人はACSを組織そのものだと思っていたけれど、私がACSはAmerican Chemical Societyの略で、学会活動や出版を含む大きな枠組みだと説明すると驚いていました。一方、PCommは特定の雑誌名で物理化学の短報を扱う雑誌だという点を伝えると、すっと理解してくれました。話の途中で、情報源を確認する大切さも実感。略称だけで判断せず正式名称と発行元をセットで見る癖が身につき、授業の課題や論文検索がぐっと楽になったのを覚えています。





















