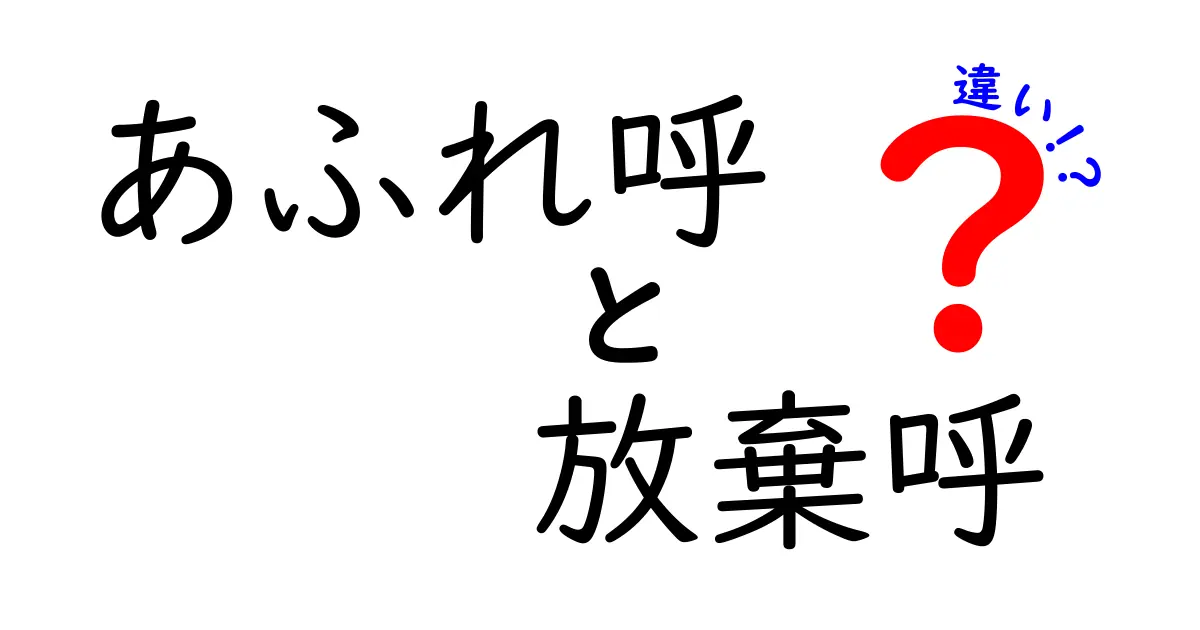

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
あふれ呼と放棄呼の基本を知ろう
あふれ呼は、インバウンドの待ち行列が長くなると起きやすい現象です。オペレーターの数が不足している、システムの優先度設定が適切でない、または時間帯で負荷が急増するなどの理由で、電話が行列の外へあふれ、別の回線や別のコールセンターへ転送されることを指します。これに対して放棄呼は、呼び出し側が長時間待つことに耐えきれず自分で電話を切ってしまう現象です。放棄呼が発生すると、企業側は実際の待機人数や通話時間、応答率が悪化して見え、顧客体験が低下します。それぞれの現象は似ているようで、原因・影響・対策が異なります。あふれ呼は「受け手のキャパシティ不足を補うための設計」の一部として扱われ、組織間の連携やルーティングの設計、外部委託先の設定次第で改善が進みます。一方、放棄呼は「待ち時間の長さ」が主因になることが多く、顧客が意思決定を早めるかどうか、音声案内の分かりやすさ、待ち時間の短縮などの改善が求められます。現場では、サービスレベル、アボーンレート、平均待機時間といった指標を使って監視します。これらの指標は、顧客満足度と直結しています。さらに、技術的には「キューの設計」「ルーティングルールの最適化」「リソースの再配置」などの具体的な施策があり、
業務の繁忙期には一時的なオーバーキャパシティの確保や外部委託の活用などの対応が効果を発揮します。長く待たせることを避けるためには、まず現状の数値を正しく把握することが大事です。
現場での違いをとらえるコツと実務のポイント
この見出しの下にも詳しい説明を続けます。あふれ呼と放棄呼は「どういう仕組みで発生するのか」を知るほど、対策が立てやすくなります。
まずは現場のルーティング設計を見直して、キューの長さと待ち時間の許容範囲を現状のデータと比較します。次に、対応リソースを適切に配置するためのデータを集め、
ピーク時には一時的に人員を増やす、もしくは外部委託で補完することを検討します。以下の表と箇条書きが、実務のイメージを作るのに役立ちます。
なお、数字は現場の実測データをもとに設定しますので、最初から完璧を求めず、改善のサイクルを回すことが大切です。
- ポイント1: ルーティングの最適化と待機時間の短縮を同時に追求する
- ポイント2: 繁忙期には一時的な人員増員や外部委託を活用する
- ポイント3: 指標を定期的に確認し、原因仮説→検証のサイクルを回す
- ポイント4: 顧客視点の案内を改善して待ち時間のストレスを減らす
このように、表と文章を組み合わせると、現場の「何が問題か」が見えやすくなります。数字だけを追うと現場の現実が見えにくくなるため、定期的にデータを確認し、実務の改善につなげていくことが大切です。ブレが生じたときには、原因の仮説を立てて検証する小さなサイクルを回すと良いでしょう。最後に、顧客視点の改善を最優先に考え、待ち時間のストレスをできるだけ減らす工夫を続けることが、あふれ呼と放棄呼の両方を減らす最短ルートになります。
友達と昼休みに放棄呼とあふれ呼の話をしていた。私がたずねると、友達は「放棄呼は待っている人が長く待たされて自分から電話を切ってしまう現象だよね。その一方であふれ呼は、行列が長くなって別の回線へ移される現象のこと。どちらも待つ人と受ける側のキャパシティの問題を指すんだ」と教えてくれた。実務の場では、待ち時間を短くする工夫や、案内のわかりやすさ、転送の頻度を減らす努力が大切なんだと話し合い、私たちは「顧客視点を最優先に」という結論に落ち着いた。雑談の中で、数字だけでなく体験の質も改善の鍵だと再認識した。





















