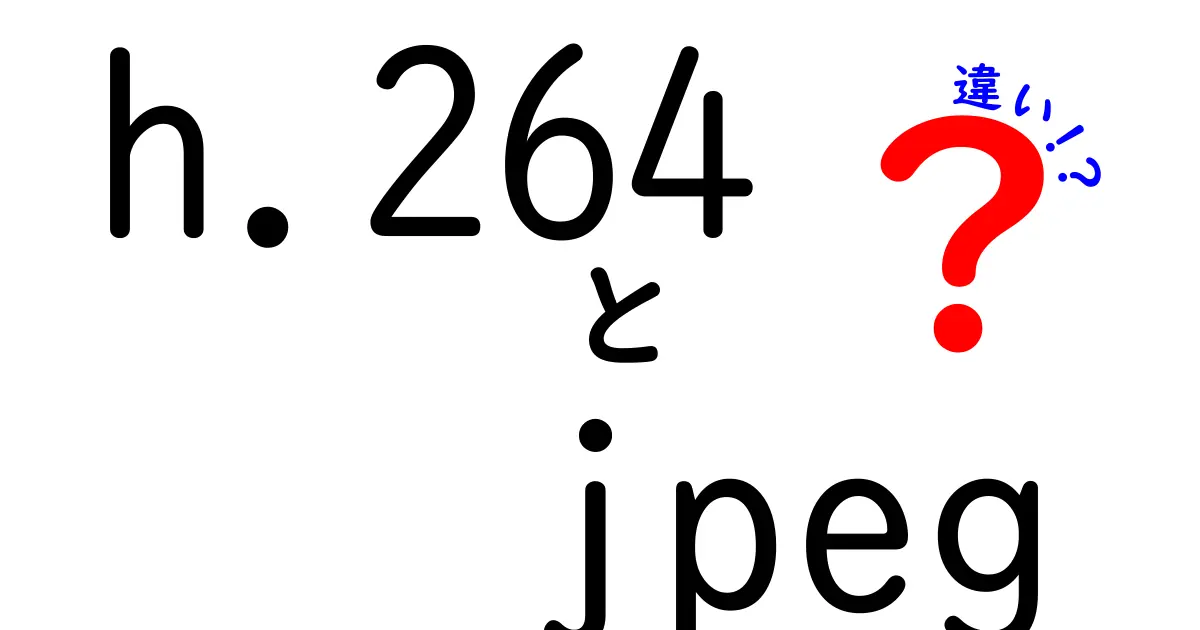

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:h.264とJPEGの基本を押さえる
現代のスマホやパソコンには、動画と写真の両方を扱う機能がついています。h.264は動画を圧縮するコーデック、JPEGは静止画を圧縮するフォーマットです。この違いを知ると、動画を作るときと写真を保存するときの選び方が変わります。
本稿では、中学生でも理解できる言葉で、両者の基本と使い分けのポイントを解説します。
まず前提として覚えておきたいのは、h.264は動画を「連続する絵の列」として扱い、JPEGは一枚の写真だけを扱う点です。動画は動く部分と止まる部分の情報を別々に圧縮することで、全体のデータ量を減らします。これが動画の軽さと滑らかさを両立させる秘密です。これを理解すると、配信の仕方や機材の設定を選ぶ際に役立ちます。
対してJPEGは一枚の静止画を対象とし、細かい色の違いを小さなデータに詰め込む技術です。ここでは動きの情報は必要ありませんから、画像の静的な部分の情報を効率よく表現します。結果として、JPEGは静止画の画質を保ちながらファイルサイズを抑えるのが得意で、Webの写真やSNSの投稿などに広く使われています。
ただし編集を重ねると画質が劣化しやすいので、元データを大事にする運用が大切です。
次に、実務面の違いを見ていきましょう。
h.264はビットレートを調整することで、動画の品質とデータ量のバランスを取りやすいのが特徴です。動画を高品質で再生したいときはビットレートを上げ、通信が不安定なときは下げるといった調整が可能です。GOPと呼ばれる構造を知っておくと、編集時の再エンコードの負担を下げるヒントにもなります。
一方JPEGは、写真を一枚ずつ圧縮するための規格です。ここでの最も重要なポイントは、色の情報と細かいディテールの表現をどう保つかという点です。高解像度の写真ほど、圧縮後のブロックノイズや色の帯状の変化が目立ちやすくなります。Web表示を想定するならProgressive JPEGの利用で読み込み体験を向上させることができます。JPEGは編集・再保存を繰り返すと画質が落ちる可能性があるため、元データを保つ運用が基本です。
実務での使い分けと注意点
動画と写真の違いを理解しておくと、素材を作るときの手間が減り、無駄なデータ量を避けられます。例えば、学校の発表用に動画を作る場合はh.264のビットレートを低めに設定しても、解像度を保つ工夫をすれば視聴体験は十分に良くなります。写真は高解像度のまま保存しておくと、後でプリントやWeb投稿のときに選択の幅が広がります。
動画は一般にh.264を軸に、配信形式に合わせてビットレートや解像度を設定します。対してJPEGは写真を静止画として扱い、用途に応じてProgressiveJPEGや品質設定を調整しますが、ここでは編集後の再エンコード時の劣化を避けるため、元データの保存を前提とします。実務では、動画は動画コーデックとコンテナを組み合わせ、写真は静止画フォーマットで保存するのが基本ルールです。
動画の世界では圧縮は技術の進歩と直結しています。h.264は動き情報を効率的に保存するので、滑らかな映像を少ないデータ量で届けられます。JPEGは静止画の美しさを保ちつつファイルを小さくしますが、動きのある映像には不向きです。私は友達と話していたとき、動画をスマホでダウンロードして容量を気にしている友人を見て圧縮の仕組みに興味を持ちました。圧縮は難しく聞こえるけど、私たちの視聴体験を快適にする“魔法”のようなものだと気づきました。





















