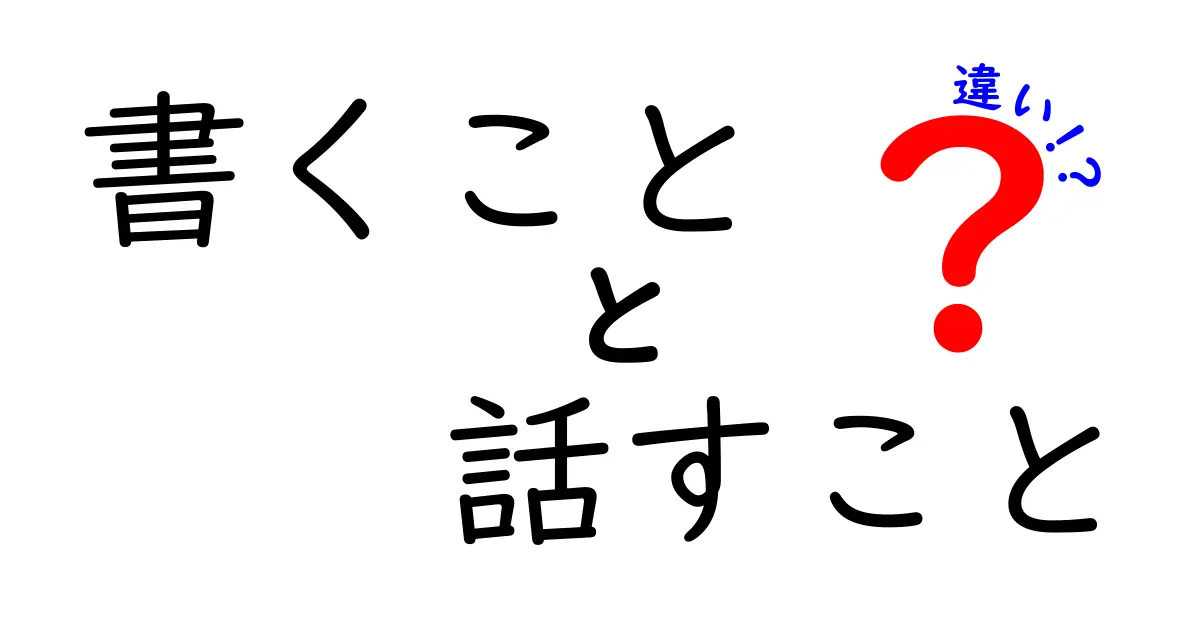

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
書くことと話すことの基本的な違い
まず、書くことと話すことには「時間の使い方」「伝え方の設計」「聴き手の受け取り方」など、根本的な違いがあります。書くことは時間をかけて言葉を選び、文の構成を考え、読み手が読み返しやすい形で記述します。話すことはリアルタイムで相手の反応を読み取り、声のトーンや表情、間合いを使って伝えます。これらの差を理解するだけで、伝わり方はぐんと変わります。
書くことは「正確さ」と「持続性」を大事にします。読み手が理解できる順序で情報を提示し、後から見直せる分、誤解があれば修正しやすくします。話すことは「瞬発力」と「共感」を重視します。相手の反応を見て言い方を変え、質問を受け止めながら会話を進める柔軟さが求められます。
さらに、書くことは「推敲」というステップを通じて文章の質を高めます。語彙の選択、文の長さ、段落のつながりを整える時間を取り、誤字脱字を少なくします。話すことは「リズム」が大事です。話のテンポ、言い淀みのない発音、相手のペースに合わせるための呼吸法など、声の調子が伝わり方を左右します。
書くことの特徴と練習法
大事な点:構成の力をつけるには、まず伝えたい結論を決め、それを支える根拠を並べる練習を繰り返します。日記を書く、要点をメモする、要約する、アウトラインを作成するなど、段落の役割を意識して練習すると良いです。文章力はセンスよりも習慣です。毎日5分でも良いので、短い文を積み重ねる練習を続けましょう。
読者の視点に立つことも忘れてはいけません。読み手が何を知りたいのか、どんな疑問を先に解決すべきかを考え、見出しや導入文を工夫します。見出しをつける練習、段落のつなぎ方、引用の使い方などの技術を身につけると、文章全体が読みやすくなります。
自分の文章を客観的に評価する習慣も大切です。友だちや先生に読んでもらい、具体的な改善点をもらいましょう。
話すことの特徴と練習法
話すときは相手の反応を観察する力が鍵です。相手がうなずく、表情を変える、質問をしてくるなどのサインを読み取り、内容を適宜調整します。声の大きさ・速さ・抑揚を使い分ける練習として、鏡の前や自分のスマホで声を録音してチェックするのがおすすめです。
練習方法としては、短いスピーチを用意して友人や家族に発表する「プレゼン練習」や、身近な話題を10分程度の会話としてまとめる「日常会話練習」が有効です。
また、話す技術には「要点を絞る」コツも大切です。長く話しすぎると要点がぼやけ、聞き手は混乱します。伝えたい結論、根拠、事例の3点を意識して組み立てましょう。
相手に伝わる情報の順番を整理する訓練も有効です。最初に結論を伝え、その後に理由を順序立てて話す「結論→理由→例」という構成を練習します。
実践シーン別の使い分けとコツ
授業の発表・プレゼン・LINEの文章・日報など、普段の生活の中には書く場面と話す場面が混在します。ここでは具体的な場面別のコツを紹介します。まず、学校の授業での発表では、結論を最初に伝えることが鉄則です。続いて理由と具体例を3つ程度挙げ、最後にもう一度結論を言うと、伝わりやすくなります。次に、書く場面では、導入・本論・結論という三部構成にすると、読み手は理解しやすく、誤解を避けられます。表現の見直しには、語彙の多様性と簡潔さを両立させる練習が有効です。
さらに、実際の場面では質問への対応力も重要です。話すときは相手の質問をよく聞き、誤解を生んでいる点を即座に補足します。書くときは、誤字脱字をなくし、専門用語の説明や注釈を加えると良いです。
下のリストは、書くと話すの基本的な違いと、使い分けの目安を簡潔にまとめたものです。
- 側面:情報の伝達と記録 vs 説得と共感
- ポイント:構成と語彙の選択 vs 声のトーンと間の取り方
- 時間感覚:長い準備と推敲が可能 vs 即時反応が多い
書くことと話すことは、頭の中の思いをどう形にするかの違いです。書くときは静かに自分と対話し、言い回しや順序を丁寧に組み立てます。話すときはその場の空気を読み取り、相手と会話を作りながら調整します。だから同じ内容でも、書くときには段落と論理、話すときには声の強弱と間の取り方を意識するだけで、伝わり方が大きく変わります。





















