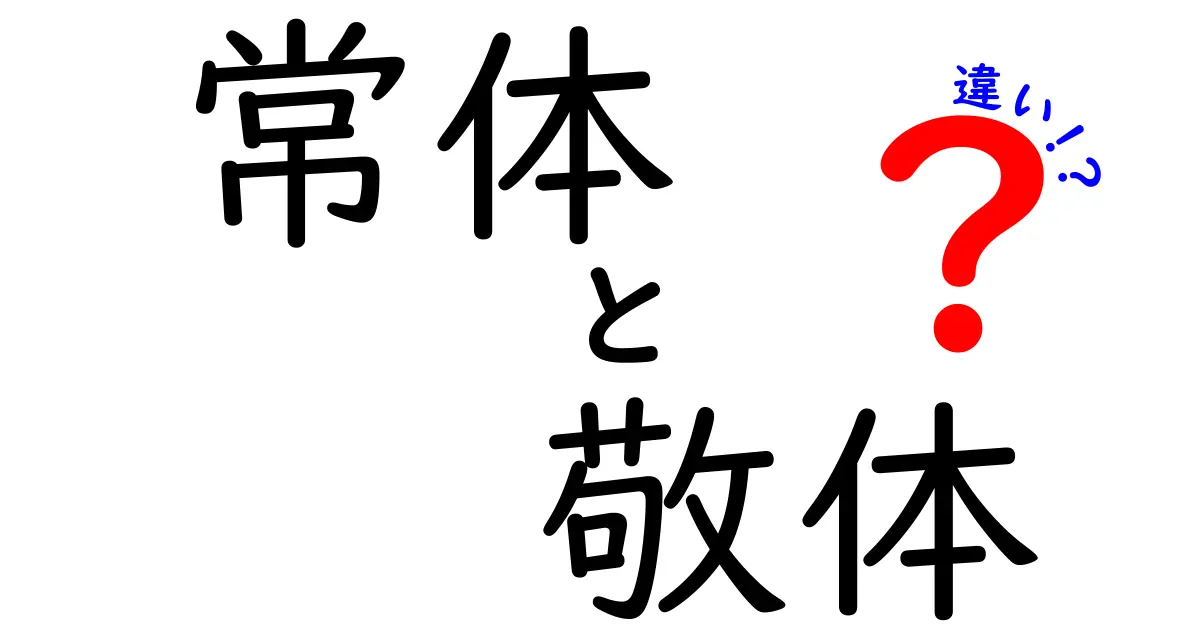

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
常体と敬体の基本を押さえる
常体と敬体は、日本語の文章をどう書くか、どう話すかという「話し方のスタイル」の違いです。
日常会話でも、友だちと話すときは自然に常体寄りの話し方になることが多いですね。これを文章に落とすとき、物語や日記、私たちのブログのような個人的な文章では常体が使われやすい傾向があります。一方、先生や上司、初対面の人とやり取りするときには、相手に敬意を表すために<敬体(です・ます調)を選ぶのが基本です。
この使い分けは、相手との距離感や場の格式を示す大切なサインです。
最初は覚えるのが難しく感じるかもしれませんが、例文を通して感覚をつかむと自然に出てくるようになります。
常体と敬体の違いを理解するには、終止形の違い、代名詞の扱い、表現の丁寧さ、そして使われる場面を意識することが近道です。以下の要点を押さえておくと、文章の印象をコントロールしやすくなります。
まずは終止形の違いです。常体はだ・だろう・〜だねのように断定的で力強い印象を与えやすく、敬体はです・ます・でしょうの丁寧さで相手に配慮している感じを出します。
次に、文末の結び方にも差が現れます。常体は結びの語尾が硬く感じられることがあり、敬体は文全体が柔らかく滑らかな印象になります。
そして、場面の違い。創作作品の描写や日記・ブログでは常体が適していることが多いのに対し、学校の連絡、先生への問い合わせ、ビジネスのやりとりでは敬体が基本です。
この3点を意識すれば、読み手が誰かを判断する材料を提供でき、読みやすさと信頼性が高まります。
場面別の使い分けのコツ
この節では、具体的な場面ごとに「常体」と「敬体」をどう使い分けるか、コツを整理します。
まず、友だち同士の会話・日記・創作・ブログなどの私的な場面では常体が自然です。話し言葉のニュアンスを文章に落とし込むとき、語尾の変化やリズム感を活かせます。
次に、学校・職場・公式文書・先生への質問・問い合わせなどの公的・公式な場面では敬体を選ぶのが基本です。相手への敬意を表すだけでなく、読み手の立場を想像して文末を整えることで、誤解を減らせます。
使い分けの練習として、以下のような練習をすると効果的です。
- 身近な場面の短い文章を、敬体・常体の2パターンで書いてみる。
- ニュース記事やエッセイの一節を読み、どの場面でどのような終止形が使われているか分析する。
- 先生への質問メールを、敬体で書く練習をする。
よくある誤解と注意点
敬体=「丁寧=良い」という短絡的な考えは危険です。場面に適した敬意の度合いを見極めることが大切です。たとえば、友人宛の連絡で過度に敬語を使うと、堅苦しくなり話の雰囲気が崩れることがあります。また、学術的な文章や文学的なテキストでは、「です・ます」を多用する敬体が必ずしも適切とは限りません。著者の意図に合わせた調整が必要です。
もうひとつの注意点は、相手との関係性によって使い分けを誤ると、距離感が不自然になることがある点です。初対面の相手には敬体を選ぶのが安全ですが、長い付き合いの中では徐々に常体へと移行する場面も出てきます。
このように、状況判断と文の目的を最優先に考え、相手に伝えたい印象を意識して使い分けることが大切です。
敬体と常体、どちらを使うか迷うときは、相手と自分の関係、場の公式さ、文章の目的の3つをまず確認します。私の経験では、友だちへの連絡で敬体を過剰に使うと、逆に距離が生まれてしまうことがありました。敬体は場を整え、丁寧さを伝える道具ですが、使いすぎると窮屈に感じさせることも。だからこそ、相手が誰か、どんな場か、何を伝えたいかを先に決めておくと、自然な使い分けが身についていきます。日常の小さな練習として、友だちへの話題を敬体で書く練習と、先生への質問を敬体で書く練習を交互に行うのが効果的です。私もこの方法で、場面ごとの表現感を体に染み込ませました。
前の記事: « メタファーと比喩の違いを完全に解説!例文でわかる基礎と使い分け
次の記事: 句読点と訓点の違いを徹底解説!中学生にも分かる読み方のコツ »





















