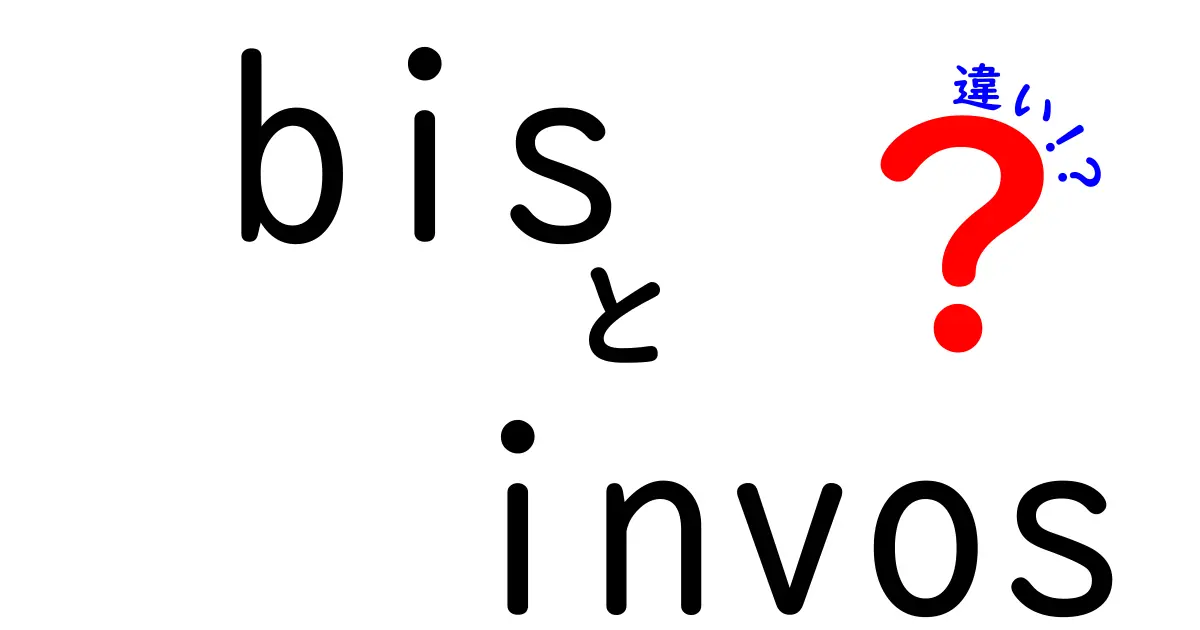

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
bisとinvosの違いを理解する基本の考え方
「bis」と「invos」は、手術中やクリニックで使われるモニタリング機器ですが、目的と測るものが異なります。BISは脳の電気信号を分析して、患者さんがどのくらい眠っているか(麻酔の深さ)を数値で示します。0から100までのスケールで表示され、多くの場合40〜60の範囲が適切とされます。これにより、麻酔薬の量を適切に調整する手掛かりになります。反対にINVOSは脳の酸素の供給と消費のバランスを測る機器です。近赤外線という光を使って、脳の血液中の酸素の割合を%で示す“rSO2”という値を表示します。
この値が低下すると、脳が酸素不足になっているサインかもしれません。BISとINVOSは同じ人の脳を見ているように思えるかもしれませんが、見る場所と意味が違います。
次に、測るものが違うという点を押さえましょう。BISは「眠さの深さ」という抽象的な状態を、INVOSは「脳の酸素の状態」という物理的な数値を示します。BISは EEG(脳波)データを処理して算出され、INVOSはヘモグロビンの酸素飽和度を測る光の反射を解釈します。つまり、BISは“眠りの深さの指標”、INVOSは“脳の酸素供給の指標”です。ここが大きな違いです。
これらは補完的に使われることが多く、同じモニタリング装置として混同されがちですが、目的が異なる点を覚えておくと理解が進みます。
なお、どちらも万能の指標ではありません。BISは薬の効き方や個人差、ノイズの影響を受けやすく、INVOSは血流の変化や髪・頭皮の影響、術中の体温変化などの要因に左右されることがあります。したがって、手術の安全を確保するには、これらを単独で判断せず、患者さんの状態全体を見ながら総合的に判断することが大切です。
医師は麻酔の深さだけでなく、呼吸・循環・血圧・体温など、複数の情報を組み合わせて判断します。そのうえで、BISとINVOSは互いの弱点を補い合う役割を果たすのです。
実践での使い分けと知っておくべきポイント
実際の病院やクリニックで、BISとINVOSはどのように使われるのでしょうか。大切なポイントをわかりやすく整理します。
まず、手術を受ける患者さんでは、BISが麻酔科医の“眠らせ方の指針”として働きます。適切な麻酔の深さを保つことで、患者さんが手術中に痛みを感じにくく、術後の回復もスムーズになることを目指します。BISの数値を見ながら薬の量を調整するのが基本です。
一方、INVOSは術中だけでなく術後の回復にも役立ちます。特に長時間の手術や高齢者の手術では、脳の酸素不足が起こりやすい場面があります。INVOSが低めの値を示すときには、体位の変更、呼吸のサポート、血圧の調整などを行い、脳への酸素供給を改善します。
ここでのポイントを短く並べておきましょう。
1) BISは眠りの深さに焦点、INVOSは酸素の状態に焦点、
2) 互いに補完し合うが、同じ情報ではない、
3) 設定や読み取りには個人差や環境要因が影響する、
4) 最終判断は医師の総合的な評価で行われる、という点です。
また、実務での注意点を覚えておくと、初心者でも落ち着いて対応できます。BISの数値が理論上は適正でも、患者さんの体調や薬の影響で実際の深さが異なることがあります。INVOSは一時的な低下が必ずしも脳障害を意味するわけではありませんが、長時間の低下はリスクサインです。
このようなケースでは、多職種チームでの情報共有が鍵となります。麻酔科医だけで判断せず、看護師・循環器の専門家・麻酔補助のスタッフが協力して、最適な対応を探ります。
ねえ、INVOSの話、聞いたことある? BISは睡眠の深さを測るやつで、INVOSは脳の酸素の状態を測るやつなんだ。私が手術の勉強をしていて気づいたのは、この二つが同時に役立つのに、それぞれ別の“見方”をしているってこと。BISの数字がきれいでも、INVOSが低いと脳は酸素不足になっている可能性がある。だから医師は二つの情報を同時に見て、薬の量と呼吸・血圧を調整するんだ。私たちがスポーツの点取り表みたいに、一つの情報だけ見てはいけないのと同じだね。そういう“両方見る”感覚が、安全な手術には欠かせないんだなと実感したよ。もし君が医療の勉強を始めるなら、まずはこの二つの違いを整理して、どんな場面でどんな意味を持つのかを頭に入れておくと、現場で混乱せず理解が進むと思う。
次の記事: 体長と体高の違いって何?図解つきで学ぶ見分け方と例 »





















