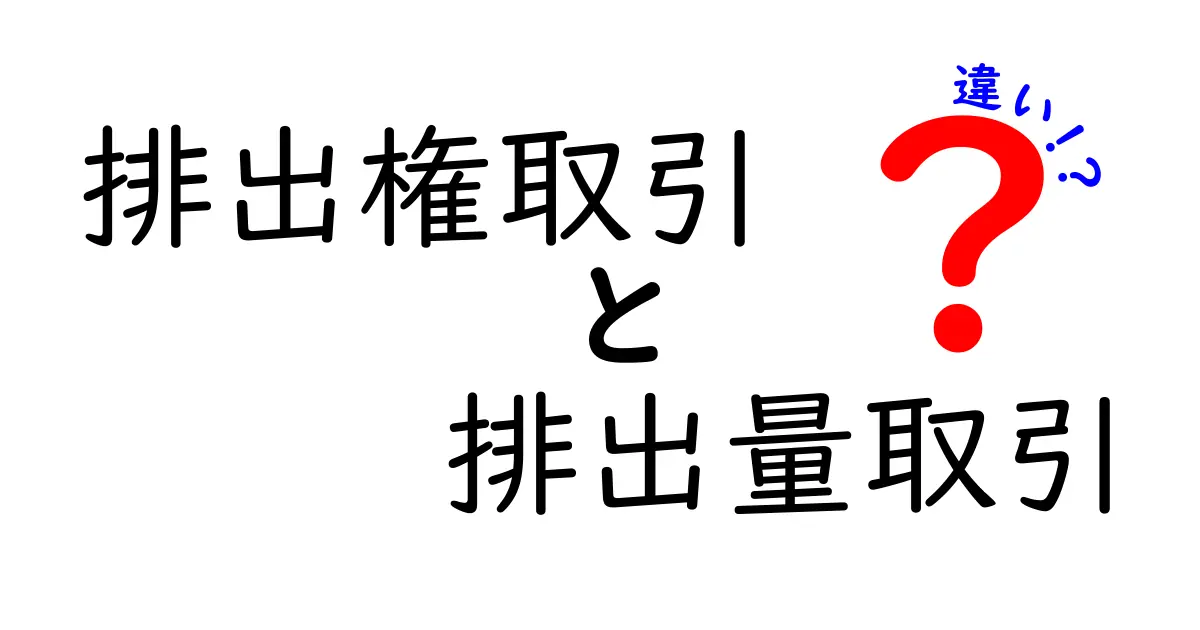

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
排出権取引と排出量取引の基本的な違い
みなさんは「排出権取引」と「排出量取引」という言葉を聞いたことがありますか?どちらも環境問題に関係する取引ですが、中学生にもわかりやすく言うと、少し意味が違います。
まず「排出権取引」とは、企業が温室効果ガスを排出できる量の権利を売り買いする仕組みです。例えば、ある会社には温室効果ガスを1年間で100トンまで出していいという権利(排出権)が与えられており、それを使いきれなければ他の会社に売ることができます。
一方の「排出量取引」は、実際に排出した温室効果ガスの量を証明して、その量に基づいて取引が行われます。排出権取引と似ているところもありますが、大きな違いは、排出権取引が“排出していい権利”を売買するのに対して、排出量取引は“実際の排出した量”を管理・調整することにより成立する取引だという点です。
つまり、両者は似ているものの、「権利ベース」と「実際の量ベース」で考えられているのです。
排出権取引と排出量取引の仕組みの違い
では、それぞれの仕組みをもっと詳しく見てみましょう。
排出権取引は、国や政府が「これだけの温室効果ガスの排出上限を設定し、その範囲内で企業が自由に排出権を売買してね」という方式です。これを「キャップ&トレード方式」とも言います。
例えば、A社は排出権を使いきれなかったので、余った排出権をB社に売り、B社はその排出権を買って環境基準をクリアします。こうすることで全体の排出量が制限され、環境負荷を減らせるようにしています。
一方、排出量取引は排出量の削減を目的とした取引で、実際に排出した温室効果ガスの量を監視し、それを基準に取引価格が決まります。排出量が多いところは削減し、少ないところは多く排出できる枠を売ることができます。
このように、排出権取引は権利の売買、排出量取引は実際の排出量の調整という形で違いが現れます。
排出権取引と排出量取引の主なメリットと課題
どちらの取引も環境保護のために大事な役割を担っていますが、メリットと課題があります。
【排出権取引のメリット】
- 企業に排出削減を促すインセンティブが生まれる
- 排出上限が明確で全体の環境負荷を抑制できる
- 市場を通じた効率的な削減コストの配分が可能
【排出権取引の課題】
- 初期配分の問題で不公平感が生じることがある
- 権利価格の変動が企業経営に影響する場合がある
【排出量取引のメリット】
- 実際の排出量に基づく取引でより正確な管理が可能
- 環境負荷が大きい企業に直接的な削減プレッシャーがかかる
【排出量取引の課題】
- 測定や監査が複雑でコストがかかる
- 排出量の計測誤差が取引に影響を与える可能性がある
排出権取引と排出量取引の比較表
| 項目 | 排出権取引 | 排出量取引 |
|---|---|---|
| 取引の基準 | 排出できる権利の量 | 実際に排出した量 |
| 仕組みの名称 | キャップ&トレード | 排出量調整取引 |
| メリット | 削減目標の明確化と市場での効率的配分 | 正確な排出量管理と直接的削減促進 |
| 課題 | 初期配分の不公平や価格変動 | 測定の複雑さと誤差リスク |
まとめ:どちらも未来の環境を守るために役立つ取引
「排出権取引」と「排出量取引」は似ているようで異なる仕組みですが、どちらも地球温暖化を防ぐために、とても重要な役割を持っています。
排出権取引が“どれだけ排出していいかの権利”を売買することで企業の排出量全体を抑えようとするのに対し、排出量取引は“実際に排出した量”を基に環境負荷を調整していく仕組みです。
環境問題に興味がある人や将来の仕事で関わるかもしれない人は、これらの違いをしっかり理解しておくと役立つでしょう。
「排出権取引」という言葉はよく聞きますが、実は「排出権」とは=“排出していい量の権利”のことです。つまり、単にガスをたくさん出さないようにするだけでなく、法律やルールで“どれくらいなら出していいか”を数字で決め、その権利を企業同士で売り買いする仕組みなんです。これにより、環境負荷を抑えつつ経済活動も続けられるようにバランスをとっています。面白いのは、権利を使いきれなかった企業は他社に売って利益を得ることもできること。環境を守るだけでなく、企業にとっても経済的なメリットがあるシステムという訳ですね。
前の記事: « カーボンニュートラルと温室効果ガスの違いとは?わかりやすく解説!





















