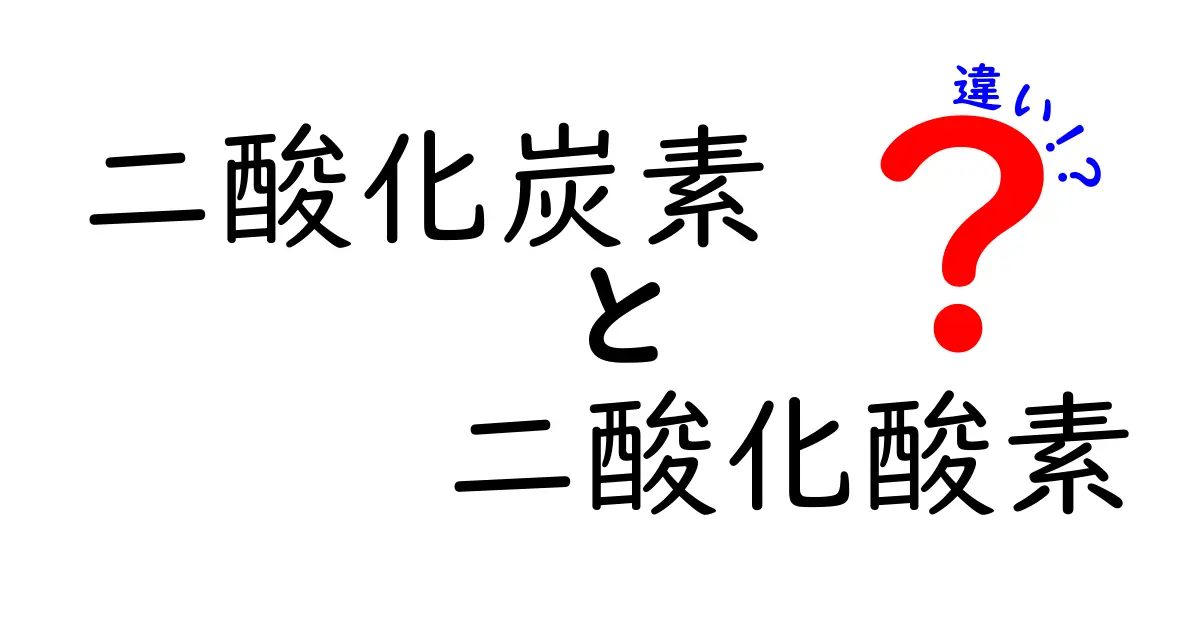

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
二酸化炭素と二酸化酸素の名前の違いって何?
まず、二酸化炭素(にさんかたんそ)と聞くと、私たちはよく地球温暖化の話題や炭酸飲料の泡のイメージを持っていますね。一方で、二酸化酸素という言葉はあまり使われません。実はここで皆が混乱しやすいポイントがあります。二酸化炭素(CO2)は炭素(C)と酸素(O)からできた化合物で、炭素が1つと酸素が2つ結びついています。一方、二酸化酸素という物質は通常存在しません。酸素(O2)は酸素分子の形で存在し、空気の約20%を占めています。
つまり「二酸化酸素」という言葉は化学的には正しくないか、存在しない物質なのです。普通は酸素分子、二酸化炭素を区別するようにします。
この違いは科学の基礎ですが、日常生活では特に地球温暖化や呼吸で覚えておくとわかりやすいですよ。
二酸化炭素と酸素の性質の違い
では、この二酸化炭素と酸素の性質や働きはどのように違うのでしょうか。
下の表でそれぞれの特徴をまとめてみました。
| 特徴 | 二酸化炭素 (CO2) | 酸素 (O2) |
|---|---|---|
| 化学式 | CO2 | O2 |
| 色・におい | 無色・無臭 | 無色・無臭 |
| 存在場所 | 空気中 約0.04% 火山・温泉ガスなど | 空気中 約21% |
| 人の体への役割 | 呼吸の時に体から出る不要なガス | 呼吸に必要なガス エネルギー生成に使う |
| 環境への影響 | 温室効果ガスとして地球温暖化の原因になる | 特に環境問題には直接関係しない |





















