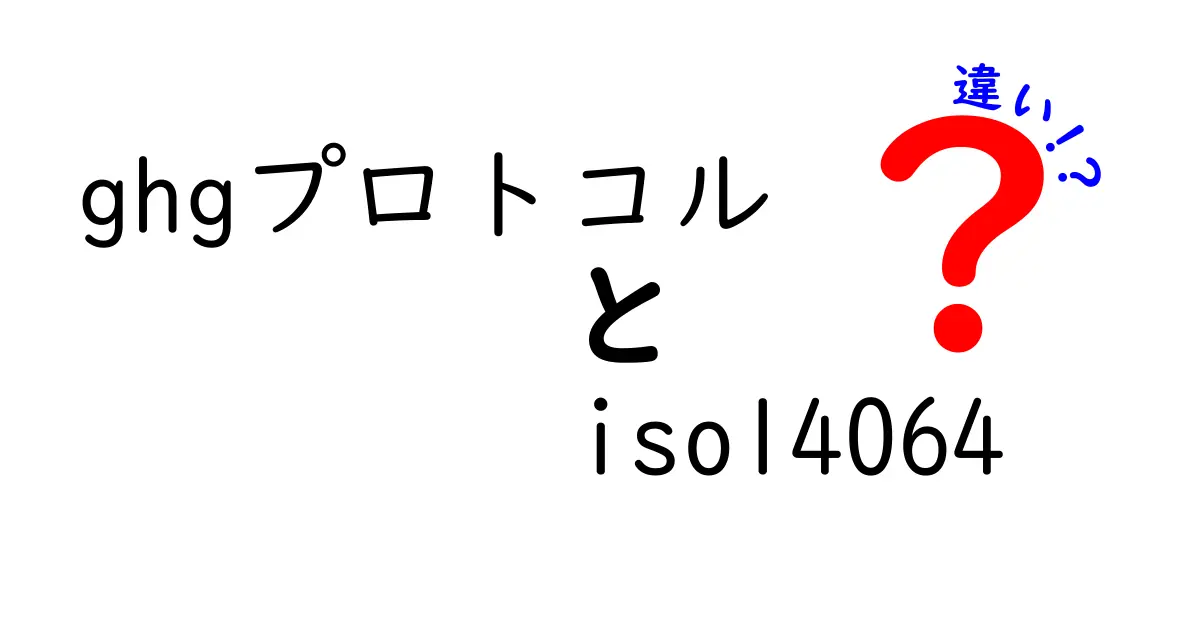

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
GHGプロトコルとは何かを理解する
GHGプロトコルとは世界で最も広く使われている温室効果ガスの排出量の測定ルールです。企業や自治体が自社の排出量を正確に把握し、削減の計画を立てるための基準です。
この仕組みは複数の国や団体が協力して作っており、データの計算方法を統一することで比較可能性を高めています。つまり、同じルールで計算すれば異なる企業の数字も並べてみやすくなり、改善の方向性を見つけやすくなるのです。
GHGプロトコルの中心的な考え方の一つがスコープという区分です。スコープ1は自社が直接排出するガス、スコープ2は購入した電力など間接的な排出、スコープ3は製品のライフサイクル全体で発生する排出を指します。この区分を覚えると現場の集計がぐんと楽になることが多いです。例えば自社が車両を所有・運用している場合はスコープ1、使っている電力の排出はスコープ2、物流・部品調達・製品の使用段階など他部門にも関わる排出はスコープ3、というように整理できます。
もう少し具体的なイメージとして、ある製造会社を想像してみましょう。工場の燃料消費に伴う排出はスコープ1、工場で使う電力の排出はスコープ2、製品を外部へ配送する際の経路の排出やサプライチェーン全体の影響はスコープ3、というように分けて考えるのです。こうした整理はデータの欠落を減らし、後で外部に報告する際にも整合性を保ちやすくします。
ISO 14064との違いと使い分けの実務
ISO 14064は国際標準化機構が出したガイドで、温室効果ガスの報告と検証に焦点を合わせています。
この枠組みはデータの信頼性を高め、第三者が同じ基準で検証できるようにする点が特徴です。
つまり、GHGプロトコルが“何を測るか”を決める設計図だとすれば、ISO 14064は“その測定データをどう公開し、検証するか”のルールになります。
現場での使い分けは、日常の排出量を正しく把握して改善計画を作るにはGHGプロトコルが基盤となることが多いです。一方で外部の信用力を高めたいとき、レポートの信頼性を示す検証を重視したいときにはISO 14064の要件を取り入れると良いです。
以下の表は代表的な違いを整理したものです。
表を読めば何をどう組み合わせるべきかが分かり、実務の進め方が見えてきます。
この表を読むと、どちらを優先して使うべきか、またどの順序で進めるべきかが見えてきます。
実務では、まずGHGプロトコルで排出量を正確に把握し、次にISO 14064の検証要件を満たす形で報告を整える、という流れが一般的です。
途中で専門家の助言を受けると、より速く確実に公開用データを作ることができます。
実務の現場では、データの整合性を保つための前提条件を清書しておくことが重要です。データ源、計算式、使用したデータの時点、更新頻度などを文書化しておくと、外部検証時の説明がスムーズです。さらに、組織内の関係部門と連携してデータ収集の責任分担を明確にすると、作業の遅れを防ぐことができます。
放課後、友達とカフェでのんびり話していたときのこと。GHGプロトコルは企業の排出量を測るための地図のようなもの。どの排出をカウントするのかスコープの考え方を決める設計図。ISO 14064はその地図に基づいて出た数字を第三者が検証して“正しいかどうか”を確認する検証手順。地図と検証、二つセットで初めて信頼できる旅が始まる、そんな感じだよ。





















