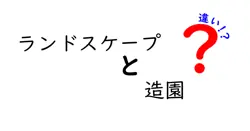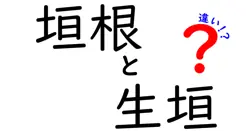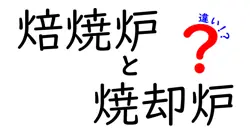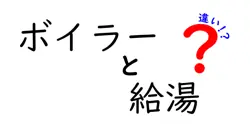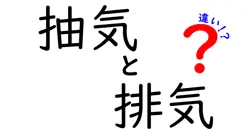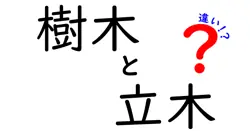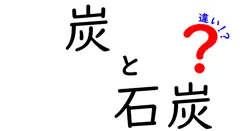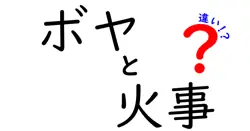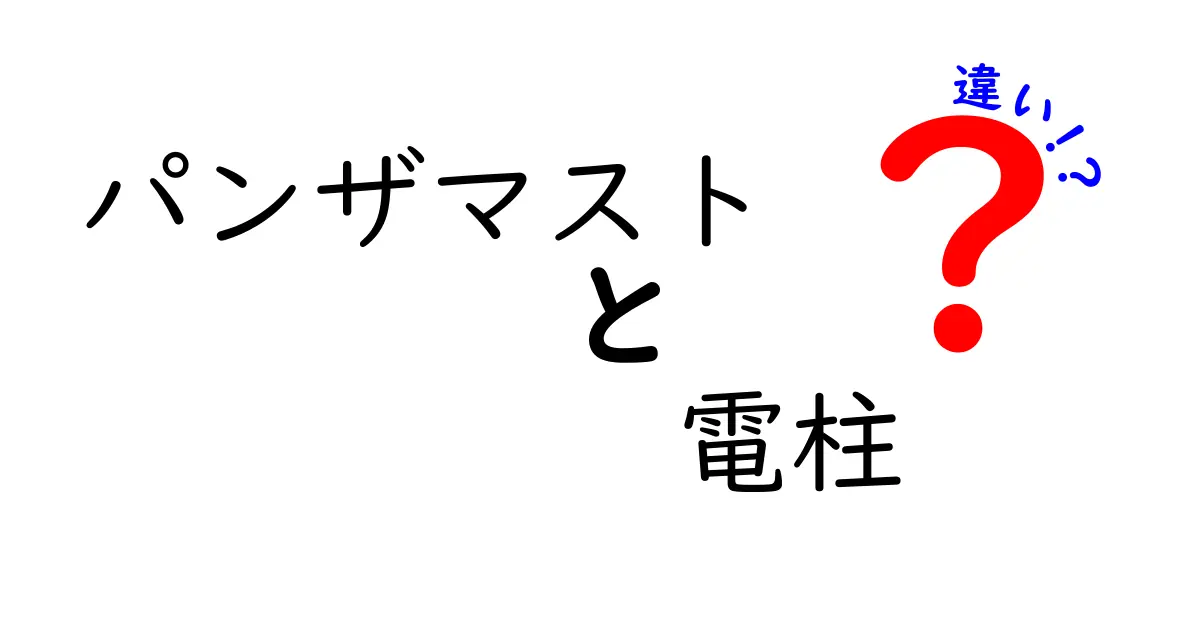
パンザマストと電柱の基本的な違い
まずは、パンザマストと電柱が何なのかをはっきりさせましょう。
パンザマストは、鋼製や金属製でできた細長い支柱で、通信設備やアンテナを高く設置するために使われます。港や工場、放送局などでよく見られるもので、強風や荷重に耐えるようにワイヤーで支えられていることが多いのが特徴です。
一方、電柱は主に電線を支えるための柱で、木製やコンクリート製、鋼製のものがあります。住居の近くや道路沿いに設置され、電気の供給や電話線の配線などに使われています。
この両者は見た目が似ていることもありますが、目的や構造に大きな違いがあります。
構造と設置方法の違い
パンザマストは、多くの場合、細長くて高い支柱であり、風の負荷に耐えるために周囲にワイヤーが複数張られています。この張力があるワイヤーこそがパンザマストの最大の特徴です。ワイヤーによって倒れにくく、軽くて高い構造を実現しています。
電柱は、通常太く頑丈な柱で、支えのワイヤーは使用しないか、短いものだけです。地中にしっかり埋め込まれていて、電線の重さを支える構造になっています。
つまり、パンザマストは「ワイヤーで支えることで軽量化・高所設置を可能にした支柱」で、電柱は「地中に固定して電線の荷重を支える柱」と言えます。
役割と使用場所の違い
パンザマストは、主に通信設備や気象観測器、アンテナなどの設置に利用されます。風の強い場所や高さが必要な場所に向いています。港湾や工場、放送局付近でよく見かけます。
対して、電柱は、街中の電気や電話の配線のための柱として欠かせません。地域のインフラを支える役割が大きいです。
それぞれの用途の違いは、使用環境や求められる機能に直結しているため、選び方や設置方法も変わってきます。
パンザマストと電柱の違いを表で比較
| 項目 | パンザマスト | 電柱 |
|---|---|---|
| 主な材質 | 金属製(鋼製など) | 木製、コンクリート製、鋼製 |
| 構造 | 細長く高い柱+支線(ワイヤー)で支えられる | 太く頑丈な柱で直接地中に固定 |
| 使用目的 | アンテナ、通信設備、気象観測など | 電線や電話線の配線支柱 |
| 設置場所 | 港湾、工場、放送局など | 街中、住宅地、道路沿い |
| 特徴 | 軽量で高所設置に適する、ワイヤーで倒れにくい | 安定性重視、荷重に強い |
まとめ:用途や構造で使い分けることが重要
パンザマストと電柱は似ているようで、役割や構造、設置場所が大きく異なります。高所で軽量かつ安定した支えが必要ならパンザマスト、電気や電話の配線インフラなら電柱です。
両者の機能を理解することで、街中や工場などで見かけるこれらの柱が何のためにあるのか、より身近に感じられるでしょう。
これからも身近なインフラの違いに注目してみてくださいね!
パンザマストの「ワイヤー支え」って実は風にはかなり強いんです。細い柱自体は軽い金属製だけど、ワイヤーでしっかり引っ張っているから、強風でも倒れにくいんですよ。これはロープを使ったテントに似ています。意外とシンプルな仕組みですが、長く高く設置する技術としてはとても効率的なんです。