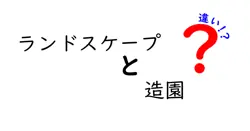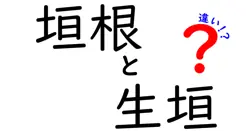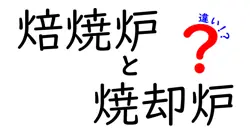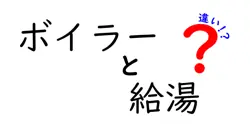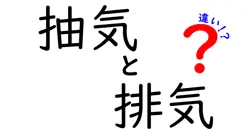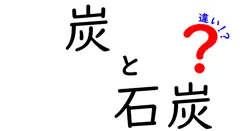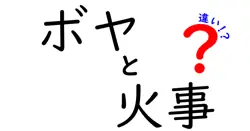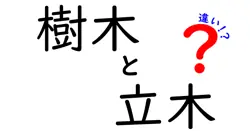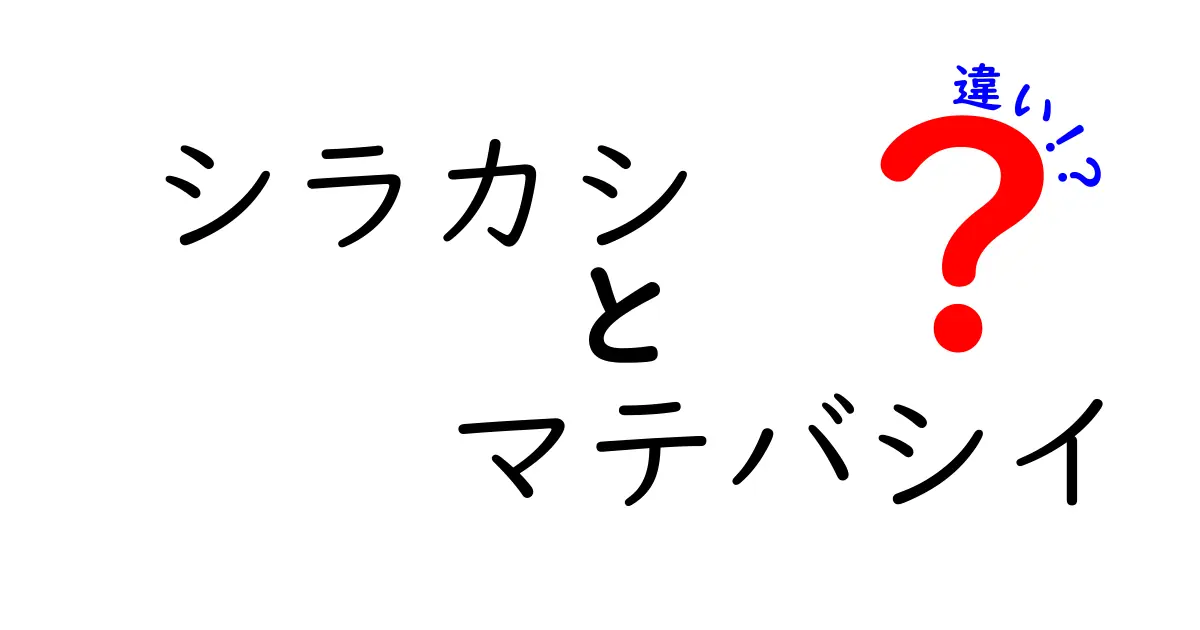
シラカシとマテバシイの基本的な違いとは?
こんにちは!今回は、シラカシとマテバシイという二つの木について詳しく解説していきます。どちらも日本の森でよく見かける木ですが、見た目や特徴が似ているため、違いがわかりにくいこともあります。
シラカシは常緑広葉樹で、硬くて耐久性のある木材が特徴です。葉っぱは光沢があり先が少しとがった形をしています。秋になるとドングリができますが、比較的小さめで丸っこい形が特徴です。
一方、マテバシイも常緑の広葉樹ですが、シラカシとは葉の形やドングリが少し違います。葉っぱはやや長くて葉脈がはっきりしていることが多いです。ドングリはシラカシよりも大きく、丸みがかった楕円形で、硬い殻に包まれています。
このように、シラカシとマテバシイは見た目だけでは分かりにくいですが、葉の形やドングリのサイズ・形状で見分けることができます。
シラカシとマテバシイの生息環境と利用方法の違い
こちらでは、シラカシとマテバシイの好む環境や人間の生活での使われ方の違いについて紹介します。
シラカシは山地のやや乾燥した場所に多く生育し、庭木や公園樹としても人気があります。硬くて重い木材は家具や建築材、炭などに利用されることが多いです。特に炭にすると火持ちがよく、昔から薪炭の材料として重宝されてきました。
一方で、マテバシイはシラカシよりも湿った場所や海に近い土地でも育ちやすいという特徴があります。また、木材としての耐久性も高く、特に堅牢性が求められる場所の建材や炭に使われます。マテバシイの炭は強い火力が得られるため、バーベキューなどに使われることもあります。
このように、両者は似ていても、生育環境や使い方に少し違いがあり、用途を理解すると選びやすくなります。
シラカシとマテバシイを見分けるポイントまとめ
ここまでシラカシとマテバシイの特徴と利用の違いを説明してきましたが、最後に簡単に見分けるポイントを表にまとめました。
| 特徴 | シラカシ | マテバシイ |
|---|---|---|
| 葉の形 | 光沢があり先が少し尖っている | 葉脈がはっきり見え、やや長めの楕円形 |
| ドングリの形 | 小さめで丸っこい | 大きくて楕円形、殻が硬い |
| 生育環境 | やや乾燥した山地 | 湿った場所や海辺近くも可 |
| 利用 | 家具、建材、炭 | 堅牢材、炭(バーベキュー用にも) |
これらのポイントを参考に森や公園で見かけたら、ぜひシラカシかマテバシイか自分で判断してみてください。どちらの木も自然の中でとても大切な役割を持っているんですよ。
最後まで読んでいただきありがとうございました!また他の木の違いも紹介していく予定ですのでお楽しみに!
シラカシのドングリは形が丸っこくて小さいですが、実はこのサイズや形には理由があります。小さなドングリは風や動物によって運ばれやすく、新しい場所で育ちやすい特徴があるんです。だからシラカシは森の中で広がりやすく、たくさんの場所で見かけます。単に見た目の違いだけでなく、生態的な意味も考えると面白いですよね!