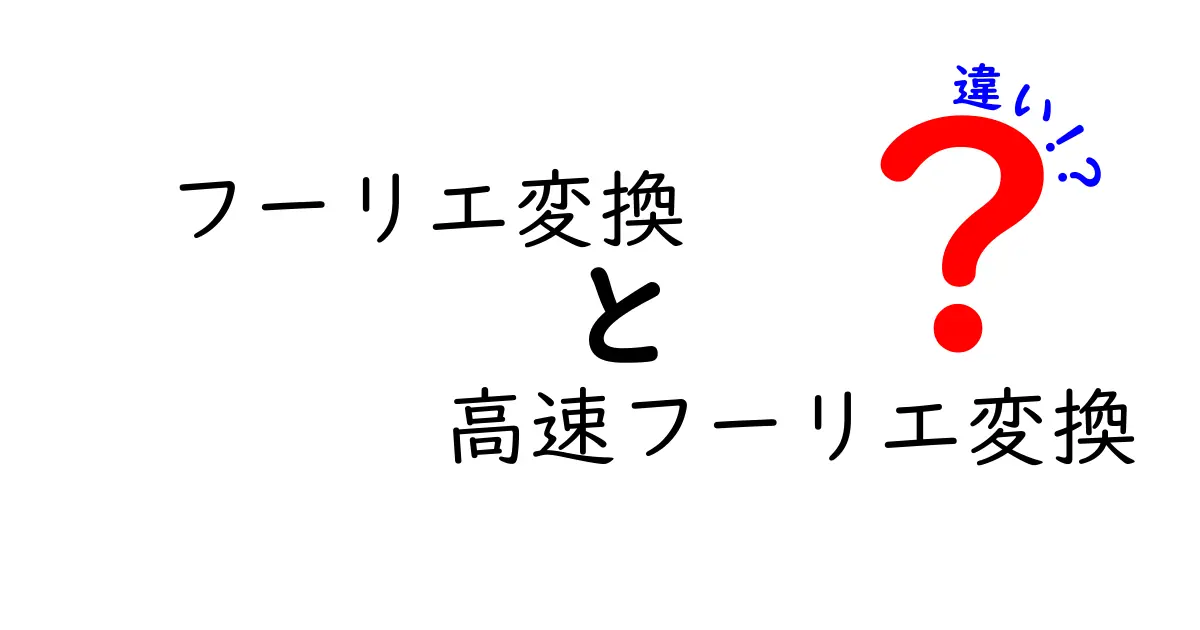

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
フーリエ変換とは何か?その基本をわかりやすく説明します
みなさんは音楽やテレビ、ラジオなどで波のようなものをよく見たり聞いたりしますよね。その波を数学的に調べたり、解析したりする方法の一つにフーリエ変換があります。フーリエ変換とは、簡単に言うと複雑な波をたくさんのシンプルな波に分けて、それぞれの波の強さや形を調べる技術です。これによって、音や信号の特徴がわかったり、画像の処理ができたりします。
例えば、ギターの音は単純な音だけでなく、いろいろな波が混ざり合ったものです。フーリエ変換を使うと、その中にどんな波がどれくらい含まれているかがわかります。
この技術は工学や物理、医学などいろいろな分野で使われていて、特に振動や音声の分析に欠かせないものなんです。
高速フーリエ変換(FFT)とは?フーリエ変換とここが違う!
では、よく聞く高速フーリエ変換(FFT)は何でしょうか?これは、普通のフーリエ変換よりもはるかに早く計算できる方法のことを指します。
実は、フーリエ変換は計算量がとても多い方法で、波の数が多くなればなるほど計算が大変になります。昔はコンピューターの性能も低くて、解析にとても時間がかかっていました。そこで1980年代に開発されたのが高速フーリエ変換です。FFTは計算の仕組みを工夫して、作業をグループに分けて効率よく計算します。これによって計算時間がかなり短縮されました。
つまり、普通のフーリエ変換は理論的な技術そのもので、高速フーリエ変換はその計算方法を速くした実用的な技術とイメージするとわかりやすいです。今ではほとんどの解析でFFTが使われています。
フーリエ変換とFFTの違いを表で整理しよう
このように、性能や使い方が違いますが、どちらも波の分析に欠かせない技術です。
これから音楽や物理、ITなどで波について学ぶとき、この二つの言葉を知っておくと理解が深まりますよ。
「高速フーリエ変換(FFT)」の話になると、実は計算速度の違いだけじゃなくて、どうやって計算を分けるかの工夫がすごいんです。例えば、大きな波を小さなグループに分けて、それぞれを順番に解くことで全体の計算時間を大幅に減らしています。まるで大人数での作業をチームに分けて効率アップするイメージ。数学の面白さを感じるテクニックですよね。今のスマホや音楽プレーヤーもこうした技術のおかげで高速処理が可能になっています。だから身近なところでもFFTは活躍しているんです。
次の記事: 伝達関数と周波数応答の違いをわかりやすく解説!基礎から理解しよう »





















