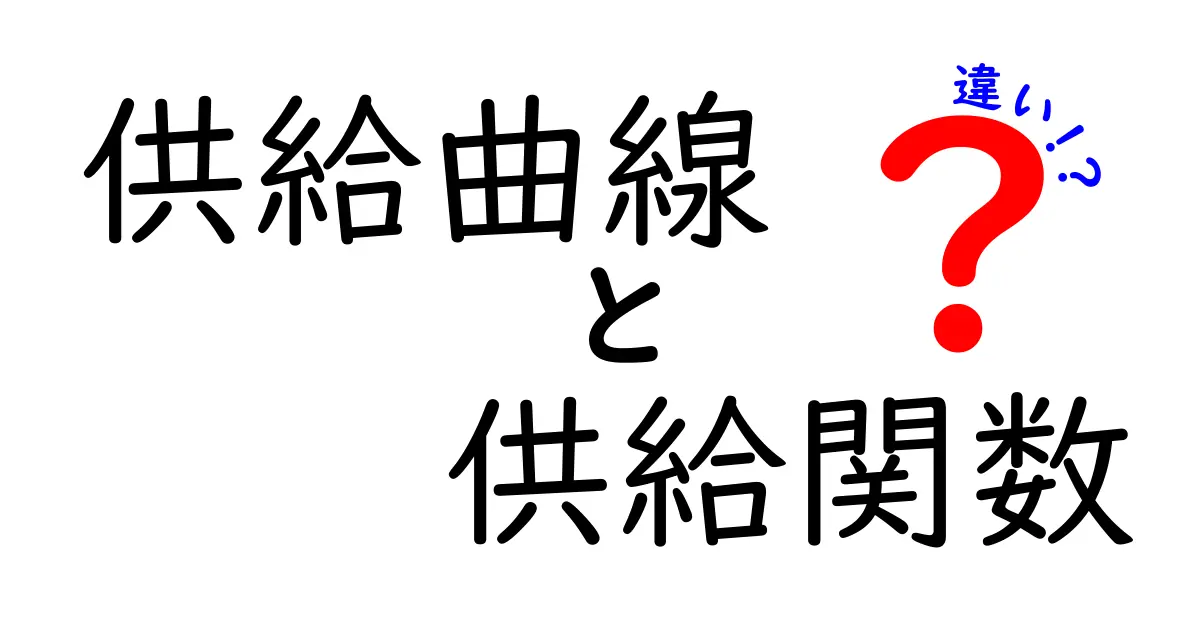

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
供給曲線と供給関数の基本とは?
まずはじめに、供給曲線と供給関数が何を意味するのかを理解することが大切です。経済の世界では、供給とは商品やサービスが市場にどれだけ提供されるかを示します。ここで使われる供給関数とは、価格という数値を入力したときに、どれだけの量が供給されるかを計算できる数式のことです。
一方、供給曲線はその供給関数をグラフで表したもの。横軸に供給される量(数量)、縦軸に価格を取り、価格が上がれば供給量も増える関係を線で表します。つまり、数式(関数)をわかりやすく視覚化したものが曲線というイメージです。
中学生でもイメージしやすいように言うと、供給関数はレシピで、供給曲線はそのレシピから作った料理の見た目のようなもの。どちらも関係が深いですが、役割が違います。
供給関数と供給曲線の違いを表で比較
わかりやすく、それぞれの特徴を表にまとめました。
供給曲線と供給関数の使い分けとまとめ
経済学者やビジネスの専門家は通常、供給関数を使って計算や予測を行い、その結果を供給曲線で表して説明します。
また、供給関数は価格以外の要素(原材料費や技術の進歩など)を入れ込むこともできるため、変化を数式で管理しやすい特徴があります。
一方で、グラフの供給曲線はシンプルに動きを見て理解したいときに最適です。価格が上がると量が増えるという直感的な内容が盛り込まれているので、経済の入門段階では役立ちます。
まとめると、供給関数は供給の数量を計算する数式で、供給曲線はその関数を基に描かれたグラフであると覚えておけば良いでしょう。どちらも経済の供給量を理解するうえでは欠かせない存在です。
これを知っておくと、経済ニュースや教科書の内容もより深く理解できるようになりますよ。
「供給関数」という言葉を聞くと、なんだか難しい数式を想像しがちですよね。でも、実は供給関数は単に「値段が変わると、どれだけ商品を売るか計算するルール」なんです。例えばジュースの値段が高くなると、ジュース工場はもっとたくさん作ろうとしますよね。その関係を数式にしたものが供給関数なんです。だから、算数が苦手でもイメージは簡単。値段と供給量の「ルールブック」と思うとわかりやすいですよ!
前の記事: « 希望小売価格と販売価格の違いとは?わかりやすく解説します!





















