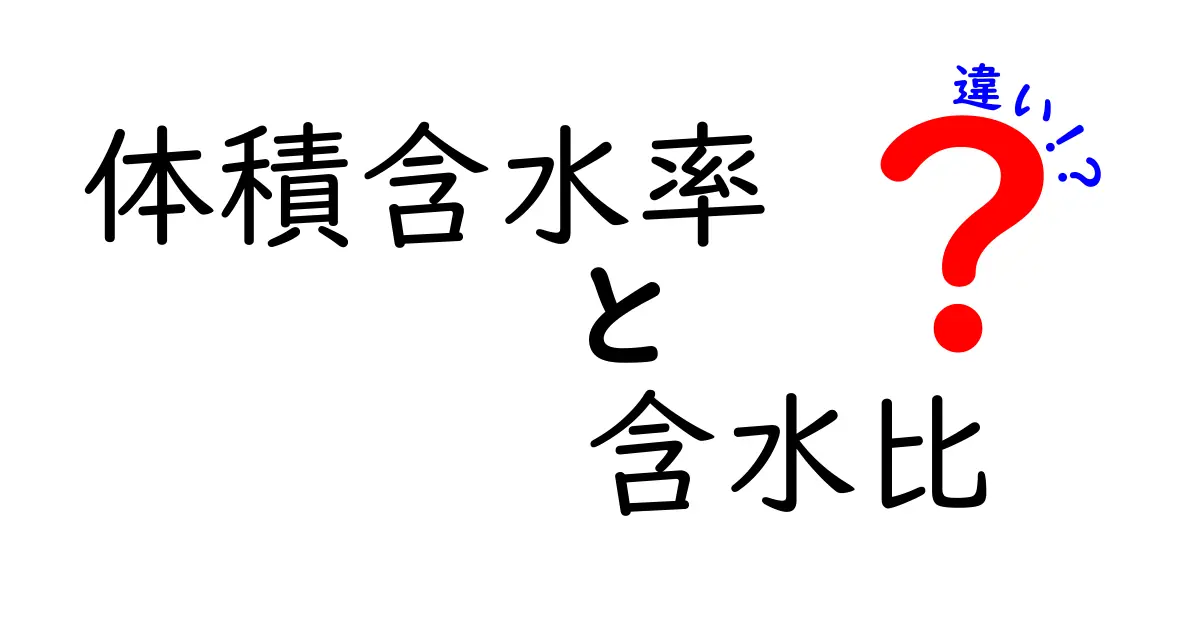

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
体積含水率と含水比の基本とは?
土や物質の中に含まれる水分を表す指標として、「体積含水率」と「含水比」という言葉をよく耳にします。これらは似ているようで、実は意味や使い方が異なる大切な用語です。
まず体積含水率とは、土全体の体積に対してどれくらいの水分が含まれているかを示す割合です。たとえば、100リットルの土の中に10リットルの水があれば、体積含水率は10%となります。この値は地盤の性質や植物の生育に重要な影響を与えます。
一方で含水比は、土の固体部分の重量に対する水の重量の割合を示します。つまり、水の重さを土の乾燥した部分の重さで割った値で表されます。例えば、乾燥土の重さが1キログラム、水が0.2キログラムならば、含水比は20%となります。
このように、体積含水率は体積ベース、含水比は重量ベースという違いがあるため、土壌調査や工学の分野では正確に使い分けが必要です。
体積含水率と含水比の違いを表で比較
なぜ違いが重要?活用シーンのポイント解説
体積含水率は、水が土の空間をどれだけ占めているかを示すため、植物の根が吸収できる水量の予測や土壌の保水能力の評価に適しています。乾燥や湿潤状態を客観的に把握しやすいため、農業や環境科学で重宝されています。
対する含水比は、土の重さに対する水分の割合を示すため、土の硬さや強度計算に必要な材料物性として重要です。コンクリートの配合設計や土質試験で活用され、工事現場などでは材料の安定性を測る指標として使われています。
つまり、体積含水率は土の水分空間に焦点をあて、含水比は重量の視点に焦点をあてているため、目的に応じて正確に使い分けることが非常に重要なのです。
この違いを知ることで、土壌や材料の性質をより深く理解し、適切な管理や利用に繋げられます。
今回は“含水比”をちょっと深掘りしてみましょう。含水比は単に『水の重さの割合』と紹介されがちですが、実は建設現場や土質試験でとても重要な役割を果たしています。
重量基準なので、湿って重くなった土の安定性や強度を測定しやすいんです。例えばコンクリートを作る時の配合にも含水比は欠かせません。
つまり、含水比は土の“どれくらい湿っているか”を物理的に示す指標で、建築や土木の安全性を支える縁の下の力持ち的存在なんですね。
こうした視点から見ると、ただの数字ではなく現場の信頼を支える大切な指標だとわかります。面白いですよね!





















