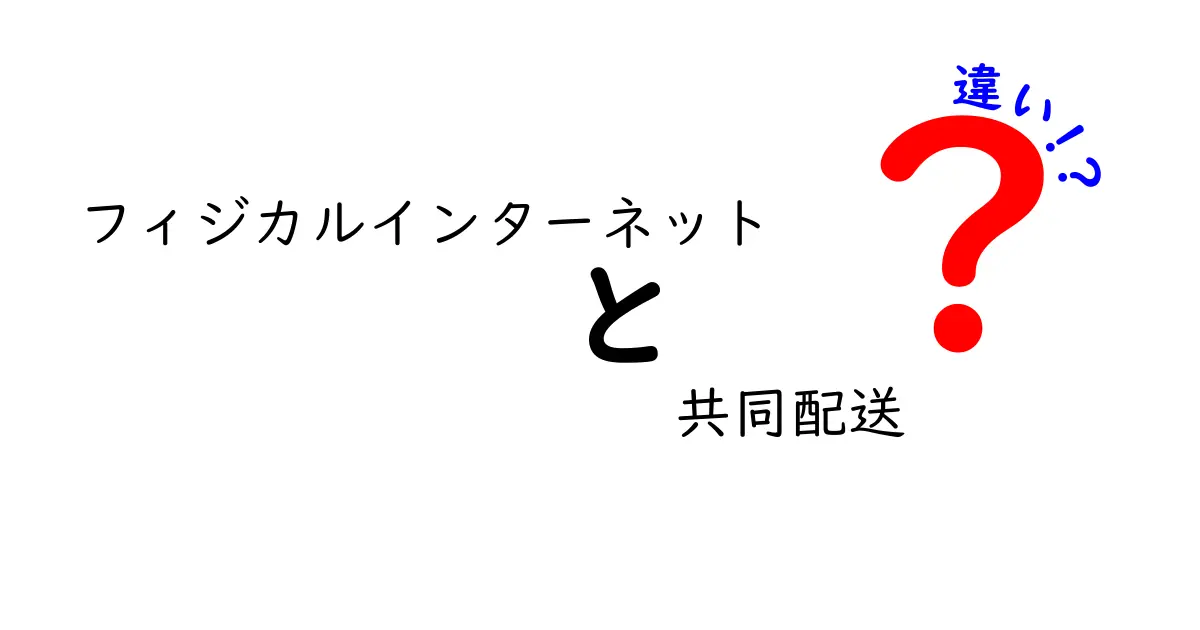

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
フィジカルインターネットとは何か?
フィジカルインターネットは、インターネットの考え方を物流に応用した新しい物流システムのことを指します。モノの流れをデジタルのデータのようにネットワーク化し、効率的に配送する仕組みです。
このシステムは、商品を小口に分けて多くの荷主の貨物を共同でまとめ、ネットワークを使って最適なルートと方法で配送することが特徴です。物流の効率化や環境負荷の軽減、コスト削減を目指しています。
フィジカルインターネットは、交通や倉庫、配送の情報を一元化し、物流全体を見える化して、スマートに管理するイメージです。
つまり、モノの移動がデジタル情報のように管理される新しい形の物流ネットワークなのです。
共同配送とは何か?
共同配送は、複数の企業や店舗が自分たちの荷物をまとめて、一緒に配送する方法です。例えば、近くにあるお店が協力して一台のトラックに商品を積み、効率よく配達するイメージです。
この方法のポイントは、物流のムダやコストを減らすことにあります。個別に運ぶよりも、まとまって配送したほうがガソリンや人件費、時間を節約できます。
共同配送は、主に地域内での配送や特定の範囲での配達に使われることが多いです。持続可能な物流のために注目されています。
つまり、実際の配送段階で荷物をまとめて運ぶ仕組みと言えるでしょう。
フィジカルインターネットと共同配送の違いを比較!
フィジカルインターネットと共同配送は、どちらも物流の効率化を目指している点では共通していますが、その仕組みや範囲に大きな違いがあります。
以下の表でわかりやすく比較してみましょう。
| 特徴 | フィジカルインターネット | 共同配送 |
|---|---|---|
| 基本概念 | 物流全体をネットワーク化したスマート物流システム | 複数企業が配送物をまとめて輸送する方法 |
| 範囲 | 全国・グローバル規模まで展開可能 | 地域や特定エリア内が中心 |
| 主な目的 | 物流の最適化と環境負荷削減 | 輸送コスト削減と効率化 |
| 技術 | IT/IoT/センサーなどを活用し動的管理 | 主に配送計画と協力による固定的管理 |
| 荷物管理 | 小口貨物をネットワーク内で最適にルート分配 | 複数の荷主が荷物をまとめて配送 |
| メリット | 柔軟性が高く、将来的な物流変革の基盤 | 手軽にコストダウンできる現実的な手法 |
このように、フィジカルインターネットは最新の技術で物流全体をひとつの大きなネットワークに変える未来志向の仕組みです。一方、共同配送はすでにある複数企業の配送を協力して効率化する、実践的な方法としての違いがあります。
まとめ
フィジカルインターネットと共同配送は、どちらも物流をもっと効率的にするための方法ですが、対象範囲や使う技術、目的の規模が異なります。
フィジカルインターネットは、物流の未来を支える大きなネットワークの考え方で、ITやAIを使って動的に荷物の流れを管理し、環境にも優しい持続可能な社会を目指します。
共同配送は、すでに広く取り入れられている身近な方法で、地域や企業単位で協力し合い、すぐに効率アップとコストカットが可能な実用的手法です。
物流の世界は日々進化しています。これらの違いを理解することで、物流の仕組みや未来の社会を身近に感じられるでしょう。
共同配送って、単に荷物を一緒に運ぶだけじゃないんです。例えば、近所のいくつかのコンビニが協力して、まとめて商品を届けることなんて日常茶飯事ですよね。これがうまく行くと、トラックの数が減り、排気ガスも減るので地球にも優しいんです。しかも、共同配送はフィジカルインターネットの考え方の一部としても捉えられています。つまり、共同配送は「物流の未来を作るためのヒント」なんですよ。これからもっと進化して、配送がスマートになるのが楽しみですね!
前の記事: « チャーター便と宅配便の違いを徹底解説!選び方や特徴まとめ





















