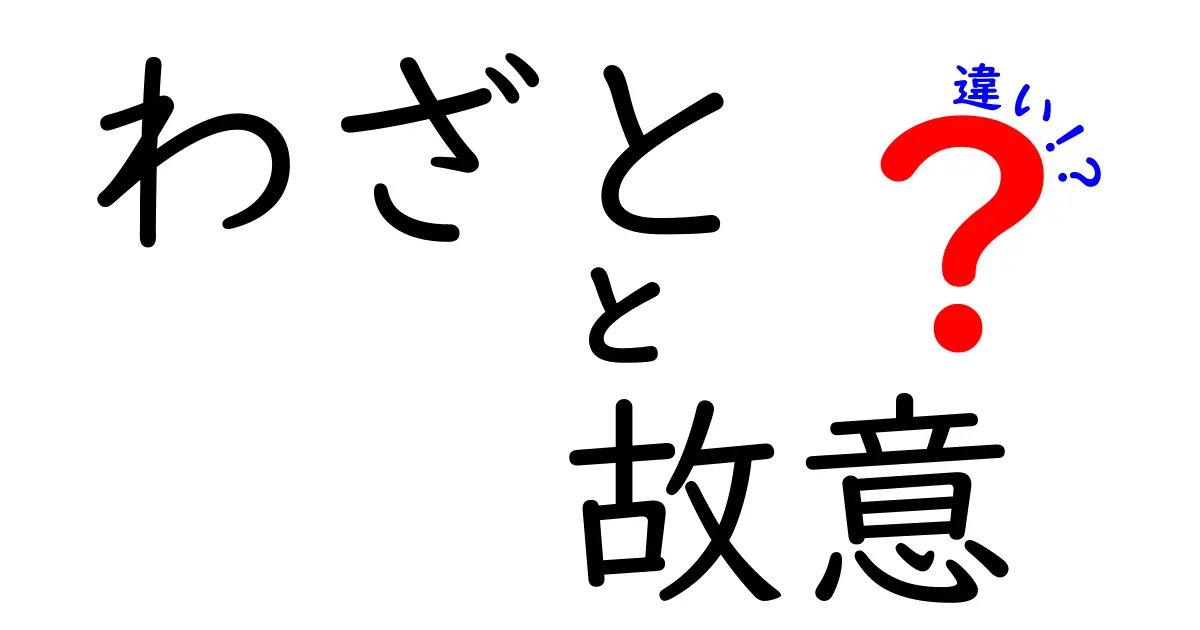

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
「わざと」と「故意」の違いを理解しよう
日常会話や法律の話でよく出てくる言葉に、「わざと」と「故意」があります。どちらも何かを意図して行うという意味ですが、実は使い方やニュアンスに違いがあります。今回は、中学生にも分かりやすいように、「わざと」と「故意」の違いについて詳しく解説します。
「わざと」は普段の話し言葉で、意図的に何かをすることを意味します。例えば、「わざと遅刻した」という場合は、遅刻することを計画して意図的に行ったことを表します。
一方、「故意」は主に法律用語で使われ、行為者が結果を知りながら、その行為をしたことを指します。法律の世界では、「過失」と違って、結果を避けられたのにあえてした場合に「故意」と呼びます。
「わざと」と「故意」の具体的な違いを比較!
それでは、「わざと」と「故意」の違いをわかりやすく表でまとめましょう。
| ポイント | わざと | 故意 |
|---|---|---|
| 使う場面 | 日常会話や軽い行為の意図 | 法律や厳密な場面での意図 |
| 意味 | 意図的にやること。意図して行動 | 法律的に認められる意図。結果を知りながらすること |
| ニュアンス | 軽いイメージもあり、悪意がないこともある | ほとんど悪意が伴う場合が多い |
| 使い方の例 | わざと宿題を忘れた | 故意に人を傷つけた |
このように、「わざと」は日常的に意図的な行動を指し、場合によっては軽いニュアンスですが、「故意」は法律で使われることが多く、悪意や責任が問われる行為に使われます。
ですから、誰かに何かをするとき、ただのうっかりではなく、計画的にやったかどうかで言葉が変わってくるわけです。
言葉の使い分けを意識しよう
普段の会話では、「わざと」という言葉をよく使いますが、法律関係やニュースでの言葉としては「故意」が使われます。
例えば、友達にちょっとした悪戯(いたずら)をするとき、「わざとやったんだよ」と冗談めかして言いますね。
しかし、もし人のものを壊したり、傷つけたりしたとして、それが計画的であれば法律では「故意」です。これが認められれば処罰の対象となります。
つまり、「わざと」は日常の軽い意味合いがあり、「故意」は法律的に重要な意味を持つ言葉だということを覚えておきましょう。
言葉の違いを理解すると、ニュースや本を読んだときに意味がよりはっきり分かりますし、自分の言葉使いも正確になりますよ。
「故意」という言葉、法律でよく聞きますが、実は少し面白いんです。ただ単に「わざとする」ことではなく、行動した人が結果を知っていて、それもあえて選ぶという意味があります。例えば、お友達を意地悪する「わざと」と「故意」は似ているけど、後者は法律的に重い意味があるんですよ。だから、「故意」はちょっと特別な意図があると考えてくださいね。日常会話と法律用語の違いって意外に深いんです!
前の記事: « 「判決」と「結審」の違いとは?裁判の流れをわかりやすく解説





















