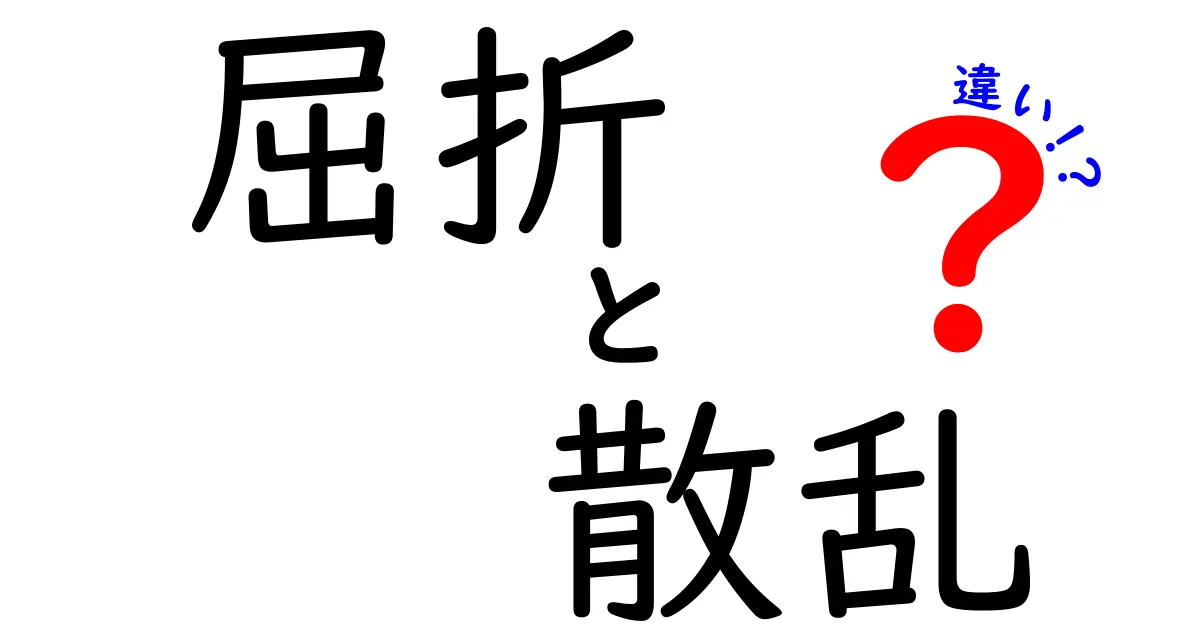

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
屈折と散乱の基本とは?
私たちの身の回りには光がたくさんあふれていますが、光はただまっすぐ進むだけではありません。屈折や散乱という現象によって、光の向きや広がりが変わることがあります。
まずは、屈折と散乱の基本的な意味を理解しましょう。
屈折は光がある物質から別の物質に入るときに、その進む方向が変わる現象です。例えば、プールの中を見ると水面が曲がって見えるのは屈折のせいです。
一方、散乱は光が物質の中の小さな粒子などにぶつかって、あらゆる方向に跳ね返る現象です。空が青く見えるのも散乱が関係しています。
このように、屈折と散乱は光の動きに変化をもたらす違った現象です。
屈折と散乱の仕組みを詳しく解説!
屈折は光の速度が変わることで起こります。光は空気中よりも水やガラスの中を進むとき速度が遅くなるため進む方向が変わります。
これを数式で表したものがスネルの法則というもので、入射角と屈折角の関係を示しています。屈折があるからこそ、メガネやカメラのレンズはきれいに物が見えるようになるのです。
一方、散乱は光が微細な粒子にあたって飛び散る現象です。例として、空気中の分子が太陽の光を散乱させることで空が青く見えます(レイリー散乱)。
散乱には光の波長によって影響が変わる性質があるため、波長の短い青い光が特によく散乱されるのです。
屈折と散乱の違いをわかりやすく比較!
ここでは屈折と散乱の違いを表形式で比較してみましょう。
| 特徴 | 屈折 | 散乱 |
|---|---|---|
| 光の進み方 | 一方向に曲がる | 多方向に広がる |
| 原因 | 光の速度変化 | 小さな粒子への衝突 |
| 日常例 | メガネや水面のゆがみ | 空の青さや霧の白さ |
| 関わる法則 | スネルの法則 | レイリー散乱など |
このように屈折は光の方向が変わる現象、散乱は光が色々な方向に飛び散る現象として大きく異なります。
光のふしぎを理解する手助けになるので、ぜひ身近な例を探してみてくださいね。
散乱という言葉を聞くと難しそうに感じますが、実は空の色を作る大切な現象です。
例えば、夕焼けが赤く見えるのは太陽の光が地平線近くを長く通るときに、短い波長の青い光が散乱されてしまい、残った長い波長の赤い光が届くからです。この仕組みを知ると毎日の空の表情がさらに面白く見えてきますよ。





















