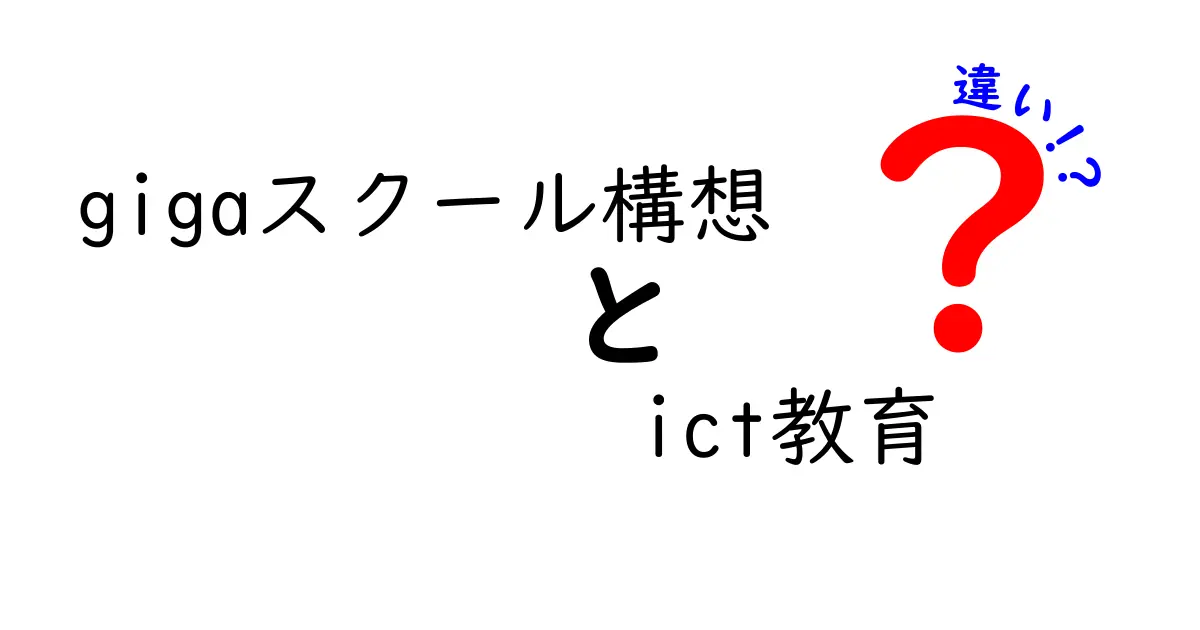

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
GIGAスクール構想とは何か?
まずはじめに、GIGAスクール構想について説明します。GIGAスクール構想は、日本の政府が進めている教育の取り組みで、2020年代に本格的に始まりました。これは、小中学校の子どもたちが1人1台のパソコンやタブレットを使えるように整備することを目指しています。
具体的には、高速のインターネット回線を学校に整え、全ての児童・生徒が同じように情報機器を使って勉強ができる環境を作ろうという計画です。これにより、先生も児童もデジタルを活用して効率よく学べるようにしたいのが目的です。
要するに、GIGAスクール構想は「学校でのICT(情報通信技術)環境を整備するための国家プロジェクト」というイメージです。
ICT教育とはどんなもの?
次に、ICT教育について説明します。ICT教育は、「Information and Communication Technology」の頭文字をとったもので、日本語では情報通信技術を使った教育のことを指します。
これは、パソコンやインターネット、デジタル教材などを使って行う授業や学習活動全般をいいます。たとえば、プログラミングの授業、オンラインでの調べ学習、デジタル教科書の使用などがICT教育の例です。
ICT教育の目的は、子どもたちがデジタル技術を使いこなせる力を育て、将来社会で役立つスキルを身につけることです。つまり、ICT教育は「実際にパソコンやネットを使って行う学び」のことだと考えることができます。
GIGAスクール構想とICT教育の違いは?
それでは、GIGAスクール構想とICT教育の大きな違いは何でしょうか?
下の表にポイントをまとめました。
つまり、GIGAスクール構想はICT教育をするための土台作りであり、ICT教育はその土台の上で行われる学びだと覚えておきましょう。
この違いを理解しておくと、ニュースや学校の話を聞くときに混乱しにくくなりますよ。
今回の話で面白いのは、GIGAスクール構想はただの"整備計画"だけど、その背景には日本の教育を世界基準に引き上げようという大きなビジョンがあるという点です。実は、世界の多くの国では既に1人1台の端末や高速ネット環境を整えてICT教育を進化させています。日本も遅れを取らないよう国として積極的に動いているのです。
だからGIGAスクール構想は単なる設備投資に見えて、実は未来の教育の形を変える最重要プロジェクトなのです。こういう背景を知ると、学校で使うタブレットを見る目も少し変わるかもしれませんね。





















