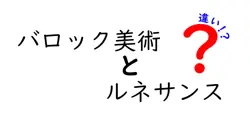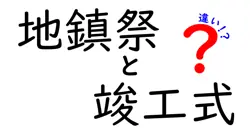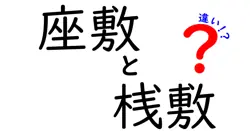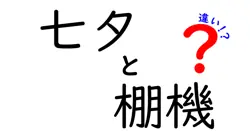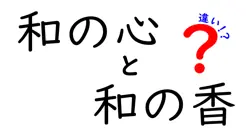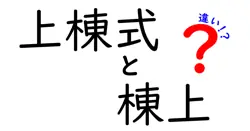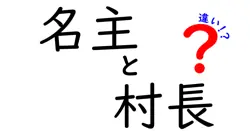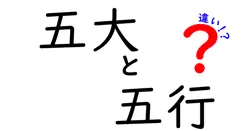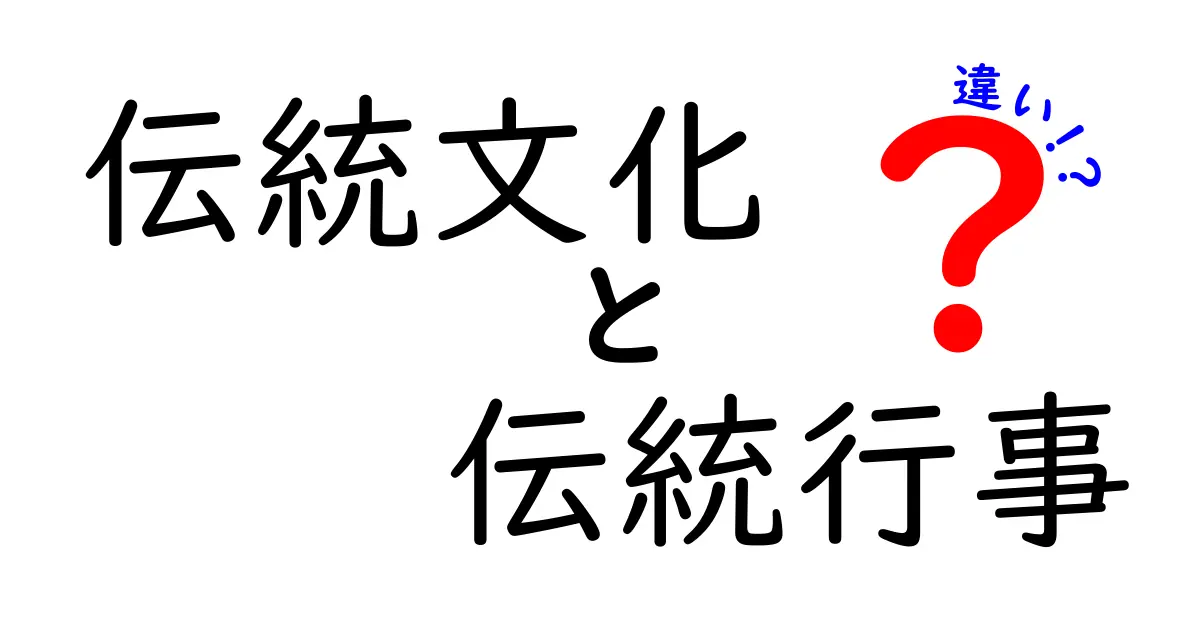
伝統文化と伝統行事の基本的な違いとは?
みなさんは「伝統文化」と「伝統行事」という言葉を聞いたとき、どんな違いがあるか考えたことはありますか?
伝統文化とは、長い年月をかけて人々によって受け継がれてきた生活の知恵や技、習慣、考え方のことを指します。例えば、茶道や書道、工芸品の作り方などがその一部です。
一方で伝統行事は、その伝統文化の中でも特に決まった日に行うお祭りや式典のこと。例えばお正月の初詣やお盆の迎え火、地域で行われる祭りなどが伝統行事にあたります。
簡単に言うと、伝統文化は人々の暮らしや考え方そのものを表し、伝統行事はそれを形にして、みんなで集まって行う特別なイベントなのです。
違いを理解すれば、普段見かける行事の意味や背景がもっと深くわかるようになりますよ!
伝統文化と伝統行事の特徴を比較してみよう
具体的には伝統文化と伝統行事はどんなところが違うのか、次の表でまとめてみました。ポイント 伝統文化 伝統行事 意味 生活様式や技術、考え方の総称 特定の日に行われる行事や祭り 伝え方 技術や習慣を世代から世代へ 地域や家族、コミュニティでの参加体験 目的 生活や精神の維持、価値観の継承 記念・祈願・感謝などを示す 例 茶道、着物の着付け、和食の作法 お祭り、初詣、七五三
このように伝統文化は日々の暮らしの中にある“文化の土台”であり、伝統行事はその文化を広く感じたり表現したりする場といえます。
たとえば、和食の作法は伝統文化の一部ですが、お正月に家族みんなで料理を囲む行事がお祝いの伝統行事となります。
また、伝統行事は地域によって特色が強く、参加することで地域の歴史や人々の心に触れることができます。
それぞれがどのようにして受け継がれているのか、その仕組みもユニークです。伝統文化は昔ながらの技術や考え方を教えることが多いですが、伝統行事は開催を企画したり、準備をみんなで協力したりすることで、次の世代に伝わっていきます。
なぜ伝統文化と伝統行事を知っておくことが大切なの?
日本の伝統文化と伝統行事は、私たちのアイデンティティを作る大切な部分です。
それを知ることで、自分たちのルーツを理解し、自信を持てるようになります。
例えば、伝統的な茶道に触れることで礼儀作法や日本独特の美意識を学べますし、伝統行事に参加すれば、地域の人たちとのつながりや助け合いの心を感じられます。
現代は便利な生活が増え、忘れられがちな伝統も少なくありません。
だからこそ、伝統文化と伝統行事の違いを理解して、積極的に学んだり参加したりすることが、日本の文化を未来に残すためにとても大切です。
さらに、学校の授業や地域の活動でも知識が役に立ち、友達や家族に説明できるようになるかもしれません。
伝統はただ古いものではなく、今も生きている文化の一部。みんなで大切にしていきましょう!
伝統行事の「行事」という言葉、元は『みんなで集まって何かをすること』を意味しています。つまり単なるお祭りだけでなく、地域の人が一堂に会し、祈りや感謝、希望を共有する場なんです。
だから伝統行事には人とのつながりやコミュニケーションがすごく大切で、参加するとその土地の人たちの温かさや歴史の深さを感じられます。
知っていると、ただのイベント以上に特別な時間として楽しめるんですよ!
前の記事: « 英検の受験料って何が違うの?級別・種類別の料金を徹底解説!
次の記事: 共通テストと過去問の違いを徹底解説!効果的な勉強方法とは? »