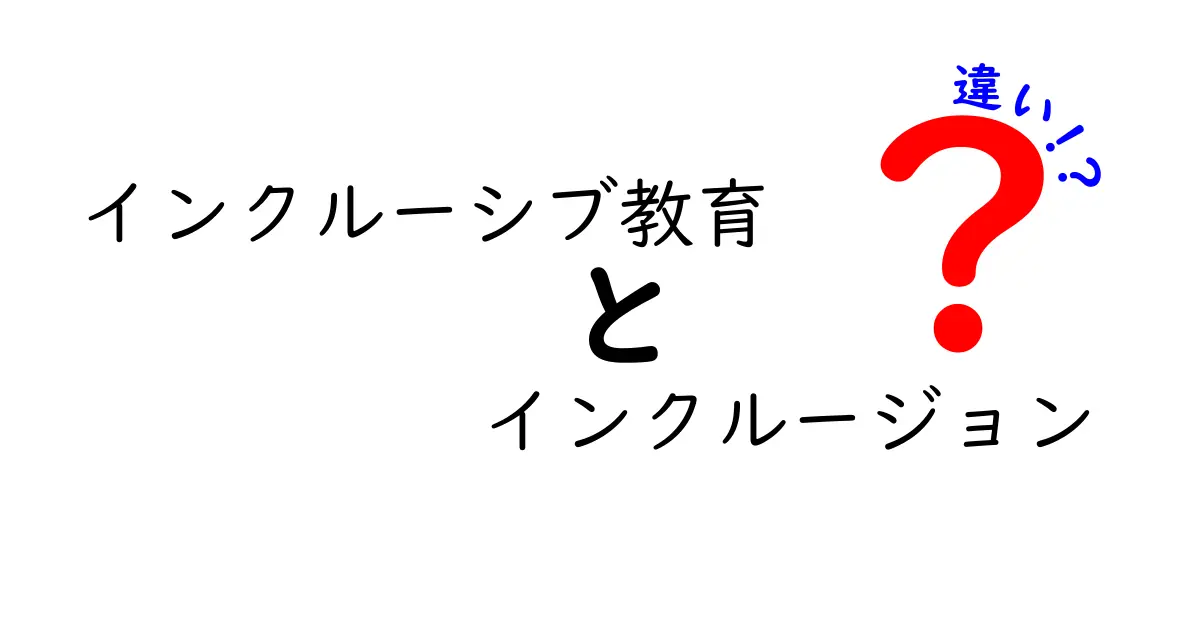

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
インクルーシブ教育とインクルージョンの基本的な違いとは?
みなさんは「インクルーシブ教育」と「インクルージョン」という言葉を耳にしたことがありますか?どちらも聞きなじみが薄いかもしれませんが、教育や社会でとても大事な考え方です。
インクルーシブ教育とは、障がいのある子どももない子どもも、みんなが同じ学校やクラスで一緒に学べる環境を作る教育のことを指します。つまり、特別な支援が必要な子どもを別の場所で学ばせるのではなく、みんなで一緒に学ぶことを重視しています。
一方、インクルージョンは、もう少し広い意味で使われることが多くて、社会や組織の中で誰もが排除されることなく、みんなが参加できる状態を指します。学校だけでなく職場や地域社会でも使われる言葉です。
つまり、「インクルーシブ教育」は教育の現場での実践を指し、「インクルージョン」はもっと広い考え方として理解されます。
インクルーシブ教育とインクルージョンが大切な理由
では、なぜこれらが重要なのでしょうか。まず、障がいの有無に関係なく同じ場所で学ぶことで、「みんな違ってみんないい」という考え方を実感できます。お互いを理解し合い、助け合う心を育てるのにとても役立つのです。
また、障がいのある子どもが社会で活躍するためには、学校の段階から一緒に学ぶ経験が大切です。孤立してしまうと、自信がなくなったり社会に出た時に困ったりしてしまうこともあります。
同時に、教員や周りの大人も多様な子どもに対応するためのスキルが必要になり、より優しい社会作りにつながります。インクルージョンの考え方が広がることで、障がいの有無に関係なく誰もが尊重される社会の実現が期待できます。
インクルーシブ教育とインクルージョンの具体的な違いを表で比較
少しわかりやすくするために、インクルーシブ教育とインクルージョンの違いを表にまとめてみました。 こうして見ると、インクルーシブ教育はインクルージョンの一部と言うことができます。教育を通じて社会全体のインクルージョンが進むイメージです。 「インクルージョン」という言葉は、教育だけではなく社会全体で使われているのが面白いところです。例えば、職場でみんなが意見を言いやすくしたり、多様な人が活躍できる場を作ったりするのもインクルージョンです。だから学校のインクルーシブ教育は、その社会へのインクルージョンの入り口とも言えます。社会全体がみんなを受け入れる雰囲気になることが、未来の明るい社会に繋がるんですね。 前の記事:
« 研修と研修会の違いとは?わかりやすく徹底解説!ポイント インクルーシブ教育 インクルージョン 主な対象 学校や教育現場 社会全般、職場、地域社会など 意味 障がいのある子どももない子どもも一緒に学ぶ教育方法 誰も排除せず、全ての人が参加できる状態 適用範囲 教育分野が中心 教育だけでなく社会全体 具体例 特別支援学校ではなく普通の学校で学ぶ 障がい者も働きやすい職場づくりや地域での交流促進 目的 個々の学習機会の平等化 全ての人が尊重される公平な社会
言語の人気記事
新着記事
言語の関連記事





















