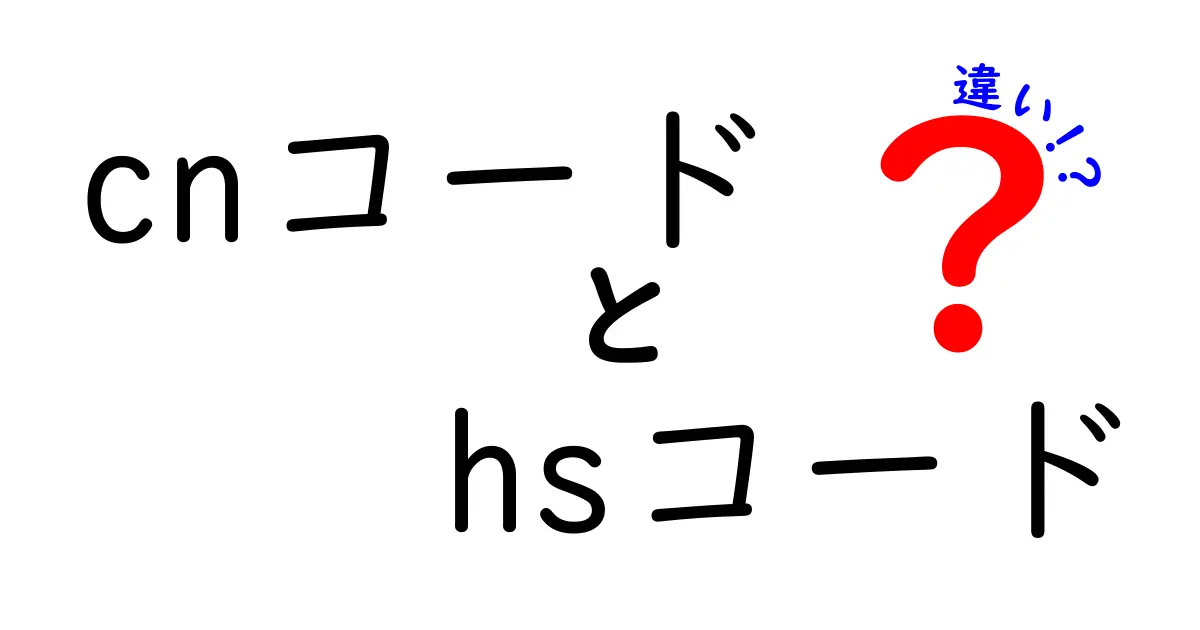

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
CNコードとHSコードとは何か?基本の理解を深めよう
輸出入の際に聞くことが多い“CNコード”と“HSコード”。これらは商品を分類するためのコードで、貿易に欠かせないものです。
まず、HSコード(Harmonized System Code)は世界共通の国際的な商品の分類システムであり、世界関税機構(WCO)が管理しています。商品の種類を6桁で表し、どの国でも基本的には同じコードを使っています。
一方、CNコード(Combined Nomenclature)は、EU加盟国で使われるHSコードを基にした独自の分類方法で、輸出入の際に細かい規定や税率を決めるために8桁で表されます。つまり、CNコードはHSコードの拡張版とも言えます。
このように、HSコードは世界共通、CNコードはEU域内でより細かく分類したものです。
CNコードとHSコードの違いを徹底比較!具体的な使い道と特徴
両者は似ているようで目的や規格が異なっています。
まずHSコードは6桁のコードで、世界中の国が基本的に同じ分類を使うことで、貿易をスムーズにし、商品の種類を共通認識にする役割があります。
一方で、CNコードはEU独自の規定に合わせて8桁で作られており、EU加盟国間の税関での扱いがより正確にできるようになっています。この追加の2桁によって、EU内の通関手続きや関税率の適用が正確に行われるのです。
さらに表で項目ごとに比較するとわかりやすいです。
| 項目 | HSコード | CNコード |
|---|---|---|
| 桁数 | 6桁 | 8桁 |
| 管理機関 | 世界関税機構(WCO) | EU加盟国 |
| 使用範囲 | 世界共通 | EU内部 |
| 目的 | 世界的な商品の分類 | 関税率決定や通関手続きのためのより細かい分類 |
| 更新頻度 | 数年に一度(WCOが管理) | 毎年(EUが独自に修正) |
つまり、世界共通のベースがHSコード、地域特化で進化したのがCNコードと考えるとわかりやすいです。
CNコードやHSコードがわかると貿易がスムーズ!覚えておきたいポイント
実際に貿易に関わると、CNコードやHSコードを正確に書くことがとても重要です。間違うと通関で止まったり、関税率が変わることで余計なコストが発生したりします。
特にCNコードは、EU域内で一層細かく商品を分けているので、正しいコードを理解して使い分けることが求められます。
また、HSコードは世界共通ですが、国や地域によって細かい解釈が少し違うこともあります。
そのため、これらのコードは単なる数字の羅列ではなく、商品の内容や輸出入のルールを表す重要な言語として使われています。
もしこれから貿易にチャレンジするなら、これらのコードの基本をしっかり押さえておくことが成功への第一歩です。
HSコードは世界中で使われる6桁の商品分類コードですが、その後ろに数字を付け足し各国独自の分類を作ることがよくあります。例えば、日本ではさらに細かい区分を示す「日本標準商品分類番号」があります。こうしたコードの拡張により、各国のニーズに合わせた詳細な輸出入管理が可能になっているんです。このようにHSコードは基本形でありながら、世界の貿易環境に柔軟に対応しているのが面白いポイントですね。
次の記事: 【初心者向け】HSコードとタリフコードの違いをわかりやすく解説! »





















