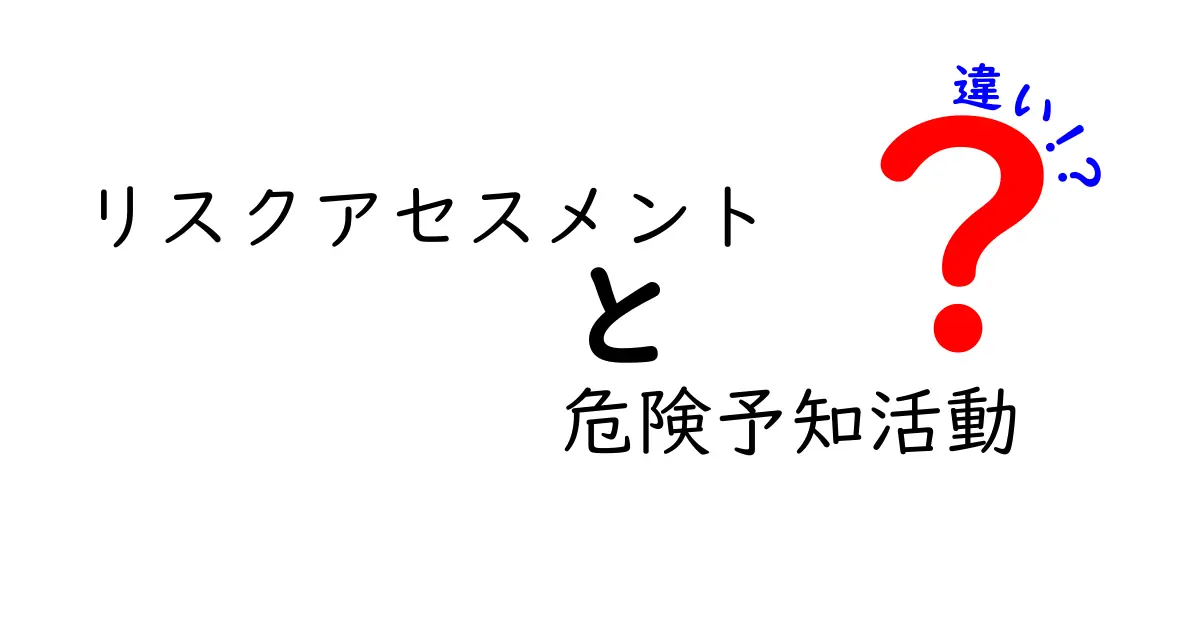

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
リスクアセスメントとは何か?
リスクアセスメントは、仕事や生活の中で起こりうる危険やリスクをあらかじめ調べ、どのような対策を取ればいいかを考える活動です。
例えば工場や建設現場では、作業中にケガをしたり事故が起こったりする危険があります。リスクアセスメントでは、そういった危険を一つひとつ洗い出し、どの程度危険かを評価し、安全に作業できるように準備を進めます。
つまり「事故を未然に防ぐための計画や対策をつくること」だとイメージしてください。
リスクアセスメントは、専門のルールや手順が決まっていて、正式に書類を作ることもあります。それによって、会社やみんなの安全を守る基盤になるのです。
このようなしくみを使うことで、事故の危険をぐっと減らせるので、とても大事な活動と言えます。
危険予知活動(KY活動)とは何か?
危険予知活動は、リスクアセスメントと似ていますが、もっと手軽でみんなで話し合いながら行う活動です。
現場で働く人たちが、その日の作業や周りの状態を見て危ないところを見つけ出し、どうしたら事故を防げるかを話し合います。
言ってみれば、毎日のちょっとした安全点検や会話です。「今日の仕事でどんな危険があるかみんなで考えて、注意しよう」という感じです。
危険予知活動は形式ばらず誰でも参加できて、すぐに行動に移せます。たとえば、滑りやすい場所を見つけたら注意標識を置いたり、道具の使い方をみんなで確認したりします。
このように作業現場の安全を日々守るための実践的な活動が危険予知活動なのです。
リスクアセスメントと危険予知活動の違い
リスクアセスメントと危険予知活動はどちらも安全に関わる重要な活動ですが、以下のような違いがあります。
| ポイント | リスクアセスメント | 危険予知活動 |
|---|---|---|
| 目的 | 起こりうる危険を調査・評価し、計画的に対策を立てる | 日々の作業中の危険を予想して注意を促し、事故を防ぐ |
| タイミング | 作業前の準備段階で実施 | 作業中やその直前に行われることが多い |
| 方法 | 文書にまとめて詳しく管理・記録 | 話し合いや現場の点検で気づいたことを共有 |
| 参加者 | 安全管理者や専門家が中心 | 現場作業者全員が参加 |
| 頻度 | 定期的(例:年度ごと)や作業変更時など | 毎日や毎作業ごとに行う |
このようにリスクアセスメントは、しっかり計画的に危険を抑えるための活動であるのに対し、危険予知活動は現場の仲間と一緒に日常的に危険に気づき防ぐための活動です。
どちらの活動もお互いを補いあって安全な環境をつくりだすために欠かせないものです。
なぜ両方が必要?
リスクアセスメントだけでは、起こりうるリスクは予測できますが、実際の作業中に新たな危険が出てくることがあります。
逆に危険予知活動だけだと、毎回の確認はできても長期的にしっかり対策を立てるのが難しいです。
だからこそ「リスクアセスメントでしっかり準備し、危険予知活動で日々気をつける」ことが重要となります。
この組み合わせが安全な作業環境を守るカギと言えるでしょう。
危険予知活動(KY活動)は、現場作業者が毎日自分たちで危険を探し、話し合いながら安全を守る活動です。
面白いのは、ただ危険を見つけるだけでなく、『もしこうなったらどうする?』と未来の危険を予想して対策を考える点です。
この“未来を想像する力”が事故を防ぐカギと言えます。かしこまった話ではなく、みんなの会話から生まれるアイデアなので、気軽に安全意識を高められます。





















