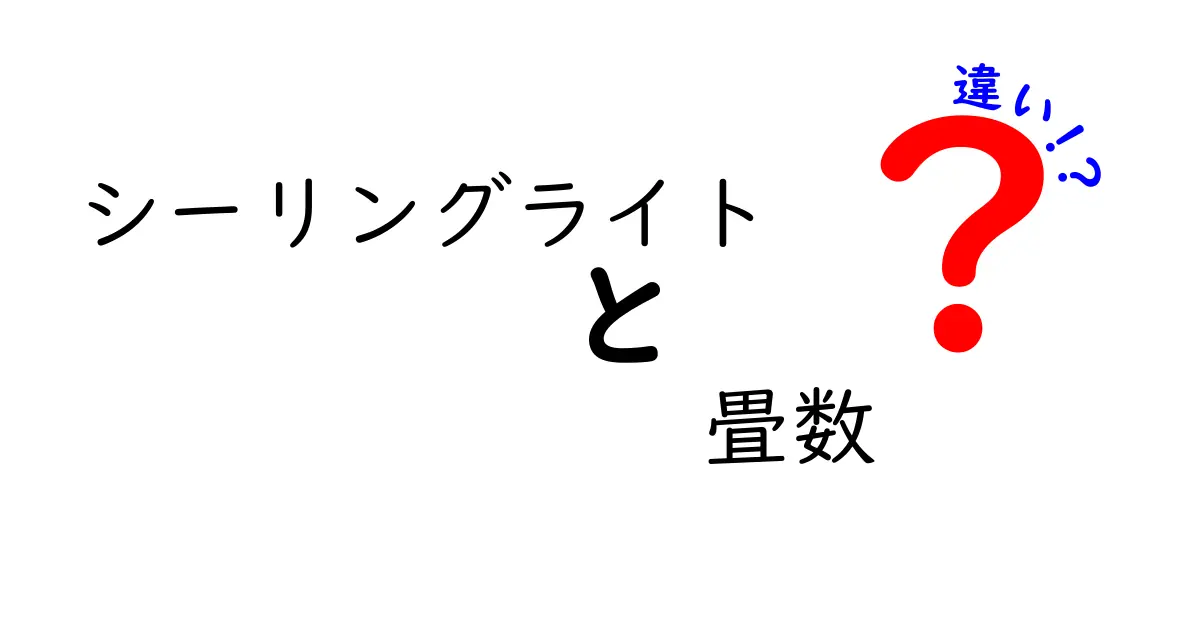

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
シーリングライトの畳数とは何?
シーリングライトを選ぶときに必ず出てくる言葉が「畳数(じょうすう)」です。畳数とは、部屋の広さを示す単位の一つで、1畳は約1.62平方メートルの広さを表します。日本の部屋の大きさを表すのに昔から使われており、家具や家電のサイズを選ぶ目安として便利です。シーリングライトでは、この「畳数」に合った明るさを選ぶことがポイントになります。
例えば6畳の部屋に対して10畳用のライトをつけると明るすぎることもあり、逆に畳数に合わない照明をつけると部屋が暗かったり、光のムラができやすくなることがあります。では、具体的に畳数によってどう違ってくるのか、詳しく見ていきましょう。
畳数ごとのシーリングライトの違い
畳数が違うと、シーリングライトの明るさ(ルーメン)や消費電力、サイズ感などが変わります。下の表は一般的な畳数別おすすめシーリングライトの例です。
| 畳数(例) | おすすめのルーメン(明るさ) | 消費電力の目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ~4畳 | 1500~3000lm | 20~30W | 小さめの部屋向け、コンパクトサイズが多い |
| 6畳 | 3000~4000lm | 30~40W | 一般的な洋室に合いやすい標準的な明るさ |
| 8~10畳 | 4000~6000lm | 40~60W | 広めの部屋に対応、複数の照明器具が不要 |
| 12畳以上 | 6000lm以上 | 60W以上 | 大きな部屋やリビングに最適 |
畳数が大きくなるほど、ルーメンという光の明るさが高くなり、それに伴って消費電力も増えます。逆に、畳数に合わない照明を選ぶと、明るすぎてまぶしかったり、逆に暗くて目が疲れやすくなるため注意が必要です。
畳数に合ったシーリングライトの選び方
シーリングライトを選ぶときは、まず部屋の正確な畳数を知ることが大事です。
次に、部屋の用途や雰囲気も考慮しましょう。たとえば、寝室ならあまり明るすぎない方が落ち着きますし、勉強部屋やリビングは明るくしたいですよね。
また、シーリングライトにも種類があり、LEDや蛍光灯など光の質や寿命も異なります。最近は省エネで長持ち、調光・調色機能が付いたLEDタイプが人気。
最後に、電気代も気になるポイント。消費電力は畳数によって異なるので年間の電気料金を考えて選ぶと良いでしょう。
例えば4畳の部屋に60Wの大きなライトを付けると、もったいない上に電気代も高くなります。逆に広い部屋に小さいライトをつけると暗く感じてしまいます。
このように、畳数に合った明るさ・消費電力を目安に選ぶことが一番のポイントです。
まとめ:畳数とシーリングライトの違いを理解して選ぼう
シーリングライトの「畳数」は、部屋の広さに合わせた照明の明るさや性能を示す大切な目安です。
畳数が大きい部屋には高ルーメンのライトを、狭い部屋には低ルーメンのライトを選ぶと快適な明るさを得られます。
また、用途や好みに合わせて調光機能付きのライトも検討してみてください。消費電力も変わるため、長期的な電気代も考慮しましょう。
正しい畳数の知識と照明の違いを理解すれば、部屋がより快適で明るくなります!ぜひ参考にしてみてください。
シーリングライトの「ルーメン」は明るさの単位ですが、実は物理的な明るさだけでなく、部屋の雰囲気を左右する重要な要素なんです。例えば同じルーメン数でも、ライトの色温度や拡散の仕方によって感じる明るさは変わります。
だから、畳数に合ったルーメンだけでなく、ライトの色や形もチェックするのがおすすめですよ!





















