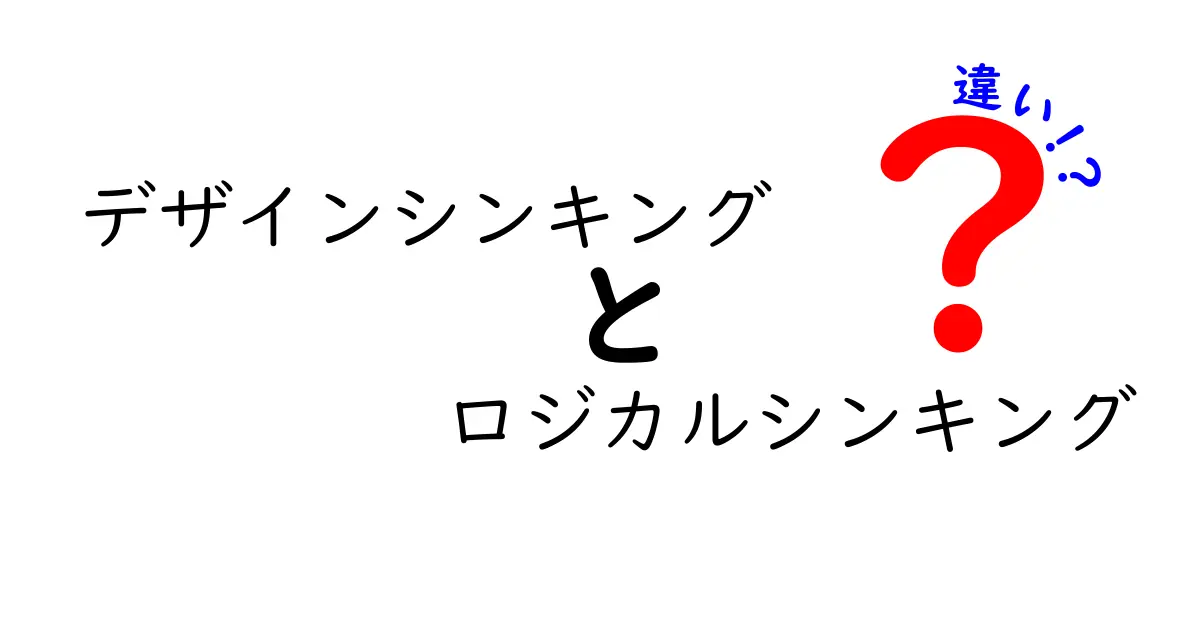

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
デザインシンキングとロジカルシンキングとは?
まずはデザインシンキングとロジカルシンキングがそれぞれ何かを知ることが重要です。
デザインシンキングは、問題解決のために「利用者の気持ちに寄り添い、創造的に考える方法」です。新しいアイデアを生み出したり、使う人の立場から考えたりするのが特徴です。
一方でロジカルシンキングは、論理的に順序立てて情報を整理し、筋道を立てて結論を導き出す考え方です。問題を分析し、原因や結果を明確にしていきます。
どちらも問題を解決するための思考法ですが、その進め方や重視するポイントが違います。
デザインシンキングの特徴とメリット
デザインシンキングは共感・発想・試作・テストを繰り返すプロセスが大きな特徴です。
例えば、何か商品の使いにくさが問題なら、まず利用者にしっかり共感します。なぜ使いにくいのか、どんな困りごとがあるのかを観察やインタビューで深く理解するのです。
次に自由に多くのアイデアを出し、プロトタイプ(試作品)を作って実験します。失敗しても改善しながらユーザーに合うものを見つけていくのが特徴。
チームで協力して創造性を活かし、未来に向けて柔軟に対応できるのが最大のメリットです。そのため、複雑な人間の感情や環境に合わせる問題に強い思考法です。
ロジカルシンキングの特徴とメリット
ロジカルシンキングは情報を分解し、図や表を使って整理することが特徴です。問題を小さな要素に分けて、原因や関係性、結論に結び付けます。
例えば、会社の売上が落ちている問題に対して「どの製品の売上が減ったのか」「原因は価格か広告か」など細かく分析します。
筋道を立てて正確に判断できるため、合理的な意思決定や報告に役立つのがメリット。事実に基づいた説得力のある説明が必要なときに優れています。
ただし、想像力や感情に弱い部分もあり、型にはまりやすいことがデメリットとなることもあります。
デザインシンキングとロジカルシンキングの違いを表で比較
どちらの思考法を選ぶべき?活用のコツ
デザインシンキングは人の気持ちや創造性を必要とする場面で効果的です。例えば、新しいサービスを作ったり、お客様が何を求めているか知りたいときにピッタリ。
一方でロジカルシンキングは情報を整理し、正しい結論を導く場面に最適です。原因をきちんと探したり、上司に説明するときに役立ちます。
実は、両方をバランスよく使うことも大切です。
柔軟に発想しながらも、考えをしっかり整理して相手に伝える。そうすることでより良い問題解決ができます。
ぜひ状況や目的に合わせて、それぞれの良さを活かしましょう!
デザインシンキングの中でも特に面白いのが、“共感”というステップです。単に問題を分析するだけでなく、実際にユーザーの気持ちに寄り添うことで、思いもよらないアイデアが浮かびやすくなります。
例えば、スマホの使いにくさを感じている人に直接話を聞くことで、“こんな機能があったら嬉しい”という発想が生まれます。
この“共感”の力が、デザインシンキングを他の考え方と区別する大きなポイントなんです。
普段なかなか人の気持ちを深く考えない人にも、新しい視点が持てるようになるかもしれませんね!





















