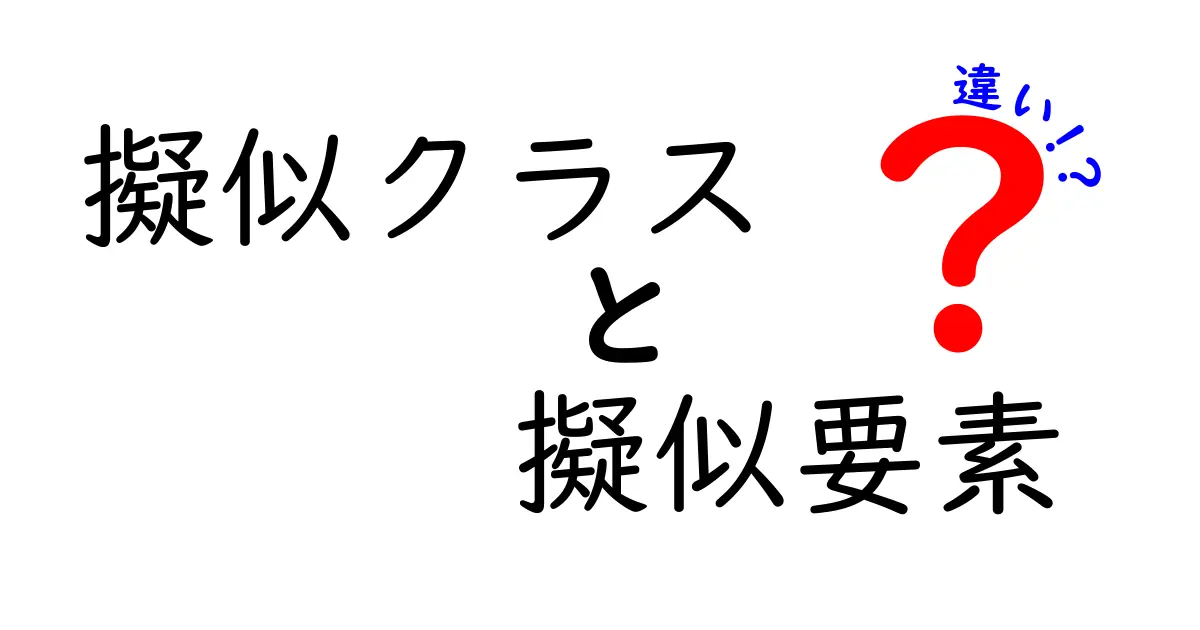

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
擬似クラスと擬似要素の違いを正しく理解するための基礎知識
CSSには「擬似クラス」と「擬似要素」という強力な機能があります。
この二つは似ているようで役割が全く違います。
まず擬似クラスとは、要素がどんな「状態」になっているかを表すセレクタです。
例えば:hoverはマウスが載っている状態、
:focusは入力欄がフォーカスを持っている状態、
:nth-child(3)のように子要素の順番を指すときに使われます。
これらは実際のHTML構造を変えずに、表示の変化を起こす助けになります。
対して擬似要素は、要素の中身自体には存在しない「仮想の要素」を作る機能です。
代表例の::beforeと::afterは、要素の前後に追加の内容や装飾を置くのに便利です。
この二つの違いを正しく覚えると、セレクタの組み合わせによってどう表示が変わるかを予想しやすくなります。
また、擬似クラスと擬似要素は一緒に使われることも多く、例えばa:hover::afterのように、状態を満たす要素に対して仮想の子要素を追加して表示を変えることができます。
このような使い分けを理解すると、CSSのルールを組み立てるときに「どこを変えるのが最小の労力で最大の効果か」を考える力が身につきます。
さらに重要なのは、パフォーマンスと保守性のバランスです。複雑なセレクタを過剰に使うと、ブラウザの描画に時間がかかってしまうことがあります。したがって、目的をはっきりさせ、最小限のセレクタで実現する工夫を心がけましょう。
以下の例と表は、違いを具体的に理解するのに役立つ基本情報です。
実務での使い分けのコツと具体例
擬似クラスは“状態や条件”を表すセレクタなので、リンクの色を変える、フォーカス時の境界線を強調する、リストの奇数・偶数の背景を切り替える、などの場面に適しています。
代表的な例として、:hoverでリンクにカーソルを合わせたときの色を変える、:focusで入力欄が選択状態のときの境界線を強調する、:nth-child()で子要素の順番に応じてデザインを変える、などがあります。
擬似要素は、要素の中身を実際には変更せず、見た目だけを追加する機能です。
例えば::beforeを使ってアイコンを追加したり、::afterで装飾のラインを引いたりする使い方が一般的です。
このように、擬似クラスは状態、擬似要素は見た目の仮想要素を作る、という基本イメージを持つと理解が進みます。
また、「状態を変化させるセレクタ」と「見た目を追加する仮想要素」の組み合わせは作りたい表現によく使われます。
例えばリンクにマウスを乗せたとき、後ろに小さなアイコンを表示するには
このセオリーを覚えると、デザインを考えるときに迷いが減り、コードの再利用性も高まります。
ただしパフォーマンスの観点も忘れてはいけません。複雑すぎるセレクタはレンダリングを遅くすることがあるので、必要最小限の組み合わせにとどめる工夫が大切です。
この章の要点を表にまとめると、理解が一段と深まります。
この表は基礎の違いをさっと振り返るのに役立ちます。
実務では、まず擬似クラスで基本的な変化を適用し、必要があれば擬似要素を追加して補足的な視覚効果を足す、という順序でデザインを構築すると管理しやすくなります。
また、読みやすさと保守性のためには、セレクタの階層を深くしすぎず、意味の明確なクラスやIDを組み合わせて使うことが肝心です。
この考え方を身につければ、複雑なUIでも迷わず作れるようになります。
友達との雑談風に言えば、擬似クラスは“今どうなっているか”という状態のスイッチみたいなもの、例えるならカーソルが乗っているときの表情を切り替えるスイッチ。対して擬似要素は“見た目を追加する仮想の要素”を作る道具で、前後に小さなマークを置く感覚だよ。つまり、擬似クラスで状況を変え、擬似要素でその状況に合わせた装飾を加える、という二段構えのイメージがしっくりくる。これを使い分けられると、HTMLを変えずにデザインをぐっと豊かにできるんだ。





















