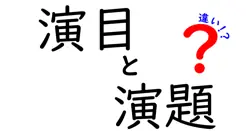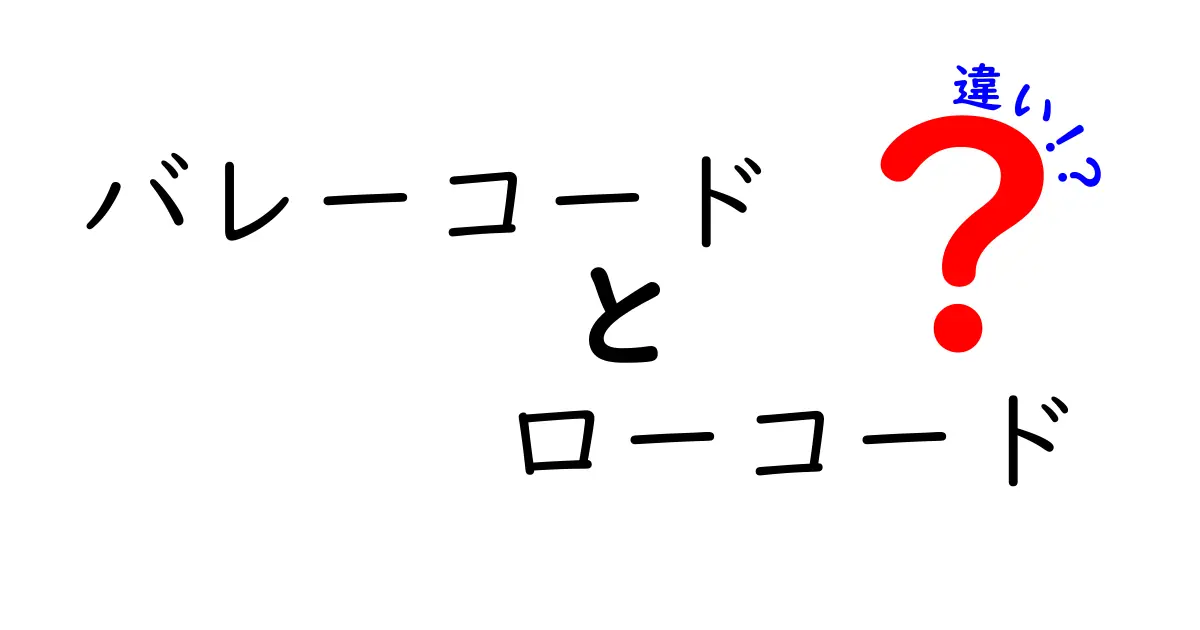

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
バレーコードとローコードの基本を知ろう
ギターのコードにはいろいろな押さえ方がありますが バレーコード と ローコード は特に初心者から上級者まで知っておくと役立つ基本形です。
この二つの大きな違いは「指の使い方」と「押さえる弦の数」です。
バレーコードは一本の指で複数の弦を押さえつけて鳴らすテクニックで、移動して別のキーのコードを作ることが得意です。これにより、同じ形を横にスライドさせるだけで多くのコードを作ることができます。しかし 指先の筋肉と正確な押さえ方が必要になるため、初心者には難易度が高いと感じることが多いです。
一方のローコードは開放弦を使ってコードを作る方法で、押さえる指の数が少なくて済むので、最初の壁を低く感じやすいのが特徴です。
ただし開放弦の都合で 音域の自由度がやや制限されるケースがある点には注意が必要です。
この二つを組み合わせて使い分けると、曲の雰囲気やテンポに合わせて効果的に演奏できます。
実際に教則本や動画を見ながら練習するときは、まずローコードから始めてみると挫折が少ないです。次にバレーコードへ進むと、指の細かい動きやネックの角度、手首の使い方などの感覚が少しずつ身についてきます。
音がきれいに鳴る瞬間を増やすことが練習のモチベーションにつながります。焦らず、毎日少しずつ練習を積み重ねましょう。
この文章を読んでいる中学生のみなさんも、最初は音が揺れて当然だという気持ちで練習を始めてください。
実践のコツと分かりやすい例
ローコードとバレーコードの練習は、実際の曲のコード進行に合わせて練習するのが効率的です。
例えば歌ものの曲では、コード進行が比較的シンプルな場合が多く、ローコードでスムーズに伴奏を作る練習が取り組みやすいです。
難しいキーに進む前に、C G Am F などの基本的な進行をローコードで安定させると、後からバレーコードを組み合わせても指の動きが混乱しにくくなります。
以下の表は、代表的な特徴をまとめたものです。
学習の目安として活用してください。
ここでのポイントは、速度と安定性のバランスを考えながら練習を設計することです。最初はローコードを中心に、次にバレーコードへ段階的に移行すると、指の筋肉の成長が自然と進みます。練習計画を立てる際は、毎日10分でもよいので続けることが大切です。
友人とギターのことを雑談していたときのこと。彼はバレーコードの難しさばかり気にしていて、指がつる痛さを心配していた。私は言った、最初は痛いのが当たり前だから大丈夫と。練習を続けると指の筋肉が鍛えられ、押さえる位置を少しずつ近づけられる。ローコードのときは、開放弦の響きが生きる曲を選ぶと取り組みやすい。すると友人は、コードの移動を練習する代わりに、まず開放弦の音色を楽しむ方法を見つけ始めた。こうして、難しさと楽しさは紙一重だと気づいた。