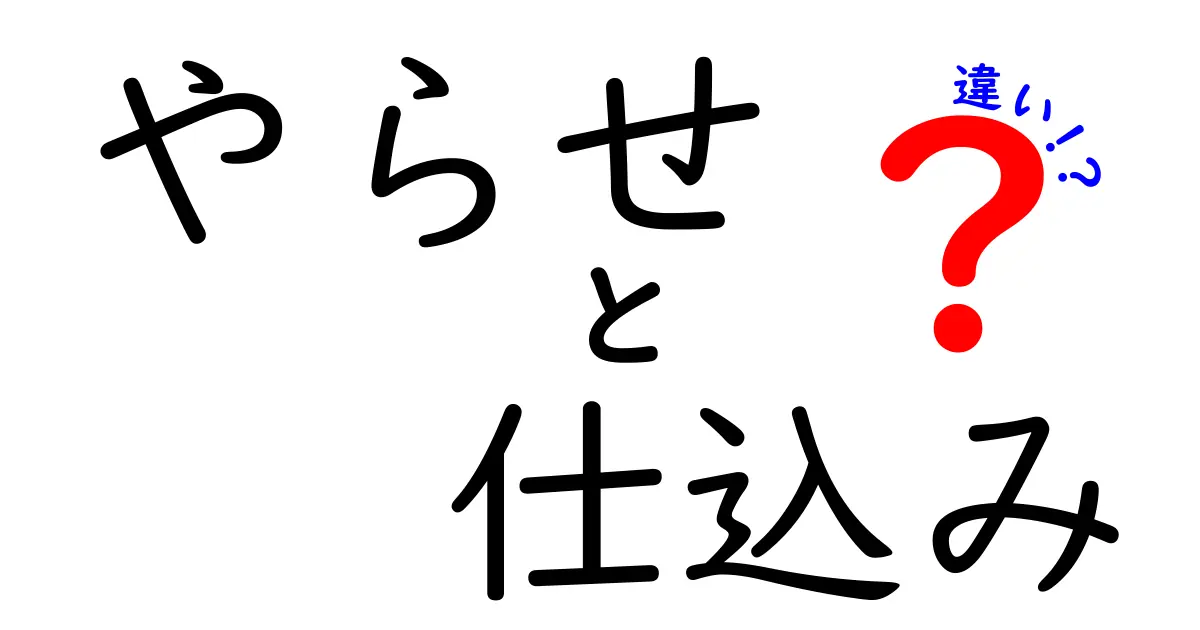

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
やらせと仕込みの基本的な意味の違い
テレビ番組やSNS、ネットの情報などで「やらせ」と「仕込み」という言葉をよく耳にしますよね。
でも、どちらも似ているようで実は明確に違っています。
まずは、その基本的な意味から理解しましょう。
「やらせ」とは、事実とは異なることを最初から意図的に作り出し、その出来事が本当のようにみせかけることを指します。
たとえばテレビで一般の人が出演しているように見えて、その場面がすべて演技だった場合などが挙げられます。
つまり、真実を隠して嘘の状況を演出するものです。
一方で「仕込み」とは、番組や企画の進行をスムーズにしたり、面白さを引き出すためにあらかじめ準備や演出をしておくことを言います。
仕込みは完全な嘘ではなく、演出や準備の意味合いが強いです。動画や番組の流れがわかりやすく、視聴者が楽しみやすいよう工夫するための手法です。
やらせと仕込みの違いを事例で説明
言葉で説明してもなかなか区別が難しいので、具体的な事例を見てみましょう。
これでどちらが問題で、どちらが許される範囲なのかがはっきりします。
- やらせの事例
ニュース番組などで一般の人の意見を聞く場面があるとします。
しかし実は演者にセリフを与えて、本当の意見でないものを伝えている場合は「やらせ」です。
視聴者をだましているので倫理的に問題視されます。 - 仕込みの事例
バラエティ番組でサプライズを成功させるためにスタッフが事前に協力者と連絡を取り合い、進行を準備しておくことがあります。
これは番組を面白く見せるための「仕込み」です。視聴者も楽しむ演出として受け入れられやすいです。
やらせと仕込みの違いをわかりやすくまとめた表
なぜやらせは問題になり、仕込みは許されるのか?
やらせが問題になる理由は真実を隠して視聴者を騙す行為だからです。
ニュースやドキュメンタリーの信頼性や公平性が損なわれ、視聴者の信頼を失います。
一方で仕込みは、番組をより楽しませるため、あるいは効率よく進めるための前もっての準備や演出です。
これは番組制作の一部として視聴者も納得しやすいものです。
例えば、クイズ番組でヒントを分かりやすく用意するのも仕込みの一例です。
このように、やらせは嘘であることを隠すことが問題、仕込みはそれを隠さずに演出として行うことがポイントです。
まとめ
まとめると、やらせと仕込みはどちらも事実とは違う演出や準備を指す言葉ですが、
やらせは嘘をついて視聴者を騙すこと、仕込みは演出や準備で視聴者を楽しませることで大きく違います。
テレビやネットの情報を見るときは、この違いを理解して賢く情報を受け取るようにしましょう。
また、放送や動画でのやらせがあった場合は視聴者の信頼が大きく損なわれるため、制作側も慎重に対応しなければなりません。
仕込みは番組作りの重要な手法として、今後も視聴者を楽しませるために使われていくでしょう。
「やらせ」という言葉は、ただの嘘とは少し違って、テレビやネットの世界で特に使われることが多いです。
例えば、ある番組で“一般人の意見です”と出てきたけど、実は演技していたり事前に台本があってそれを真実だと装っている場合、それがやらせです。
面白さや話題性のためにやらせが使われることもありますが、視聴者の信頼を失う大きな原因になります。
だから、多くの人はやらせを見破ろうと情報を注意深く見るようになりますし、制作者も倫理的にどう見られるかを考えています。
こうした視点から、やらせはただの爪痕を残す演出ではなく、視聴者の信用に関わる大問題ということがわかります。
前の記事: « コンタクトの使用期限の違いとは?正しいケアで快適な視界を保つ方法





















