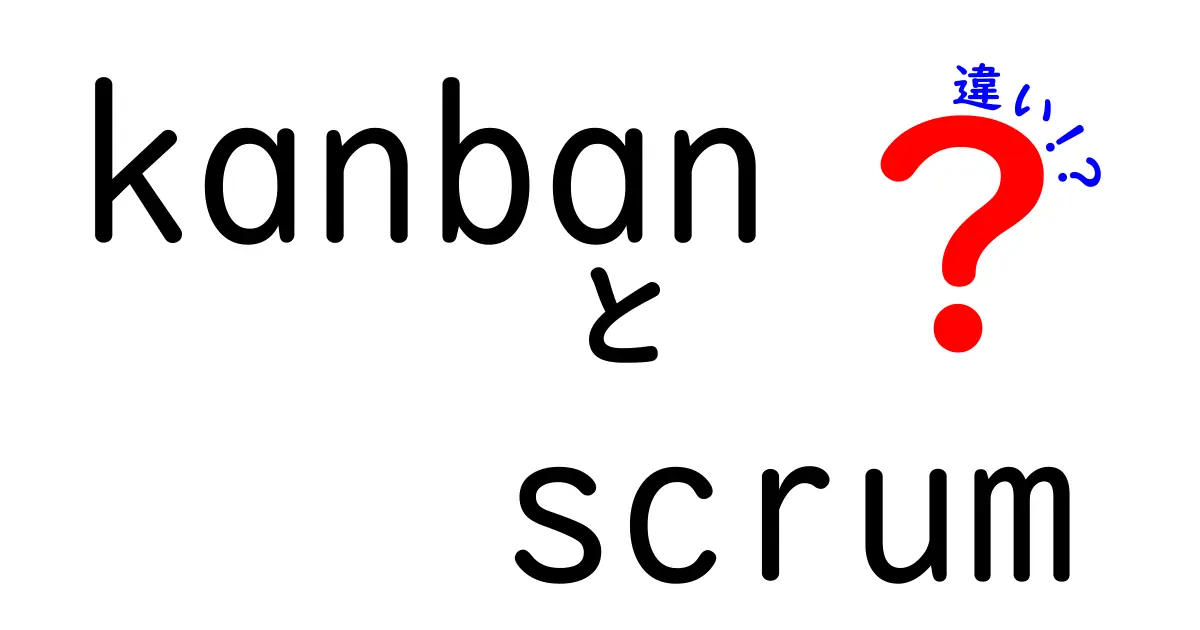

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
kanbanとscrumの違いを理解するためのガイド
現場でよく耳にするkanbanとscrum。どちらも“作業を整える仕組み”ですが、実際には異なる考え方と運用ルールがあります。kanbanは製造業の流れを前提に作業の流れを可視化してボトルネックを解消することを目的とします。作業を「到着→着手→完成」というように連続した流れとして見せ、進行状況を視覚化することが最優先です。scrumはソフトウェア開発の現場で広まったアジャイルの実践法で、短いサイクル(通常は2週間前後)を回して学習と適応を繰り返します。ここで重要なのは、計画と振り返りを定期的に行い、次のサイクルで改善することというリズムです。kanbanは継続的なフローを追求するのに対し、scrumは時期を区切って改善を進めることを重視します。これだけでも大きな違いが見えてきます。さらに言えば、kanbanは状況に応じた柔軟性が高く、scrumは規律とチームの約束を求める傾向があります。最終的には、両方の要素を組み合わせることも現実的な選択肢です。
この違いを理解しておくと、あなたのチームにとって最適なスタイルを選ぶときの判断材料が増えます。
ポイントは自分たちの課題に直結した改善サイクルを作ることです。
歴史と基本概念
Kanbanは日本語の“看板”の意味を持ち、元々はトヨタ自動車などの生産ラインで使われていた管理手法の一つです。作業を示すカードとカンバンボードを使い、現在の作業状況を誰でも一目で把握できるようにします。特徴はWIP制限(同時に手掛ける仕事の数を制限するルール)と継続的な流れ、そして上位の管理者や外部の介入を前提としない自律的な改善の姿勢です。Scrumは1990年代にソフトウェア開発の現場で広まり、Product Backlog、Sprint、Daily Scrumなどの明確なイベントと役割が設定されています。Scrumの中心は短期間の反復と適応であり、計画・実行・検証を回すことで徐々に品質と価値を高めていきます。
この二つは同じ「作業を整える」目的を持ちますが、進め方が根本的に違います。Kanbanが「現状の連続性を保つ」ことを、Scrumが「短期の成果を積み上げること」を意識している点を理解すると、混同を避けやすくなります。
実務での使い分けの具体例
実務では、組織やチームの性質によって使い分けが自然と決まってきます。作業の種類が多く、予測不能な流れを持つ場合はKanbanが向いています。例えば障害対応や日次の新機能投入が頻繁に起こる現場では、WIPを制限しつつ、ボードの各列を「未着手」「着手中」「検証中」「完了」といった自然な流れで保つだけで、ボトルネックと待ち時間が目に見える形で減少します。逆に、新しい機能を一定期間に集中してリリースする必要がある、設計・要件の整合性を重視する場面ではScrumが有効です。Sprint計画で優先順位を決め、完了の定義を明確にすることで、品質の高い成果物を繰り返し届ける力が強まります。もちろん現場では両者を組み合わせた“Scrumban”的な運用を取り入れることも増えています。ここで大切なのは、目的と制約をはっきりさせることと、チーム全体の合意と継続的な改善を大事にすることです。
実際の導入では、最初はKanban的な継続的流れから始め、徐々にスクラムのイベントを組み込んでいくと、抵抗感を減らしやすくなります。
まとめと実践のヒント
この二つの違いを頭の片隅に置きつつ、現場の課題に合わせて選ぶことが重要です。要点は“可視化”と“改善のリズム”をどのように作るかです。Kanbanは視覚的なボードとWIP制限を軸に、現状のボトルネックを見つけて連続的に解消します。一方Scrumはスプリントの期間を区切り、計画・実行・振り返りを回すことで、短期的な価値を安定的に積み上げます。どちらか一方に固執するのではなく、組織の成熟度やプロジェクトの性質に応じて組み合わせるのが現実的です。導入のコツとしては、まず現状の課題を洗い出し、「ボトルネックはどこか」「作業の流れをどこで止めるべきか」を議論します。次に、小さな実験を繰り返すことを約束し、1〜2つのChangeを試してみるのが成功の鍵です。最後に、成果を定期的に共有し、全員で改善の方向性を確認する仕組みを作ると、自然と継続性が高まります。
ねえ、kanbanってただのボードの話だと思ってない?実はflowを日常の作業に落とし込む考え方なんだ。ボードの列を動かすたびに、どこで止まっているかが見える。僕の現場でWIPを減らしたら、待ち時間がぐっと減って作業が回り始めた。自分のタスクの順番を意識するだけで、同僚との協力も自然とスムーズになる。kanbanは小さな改善を積み重ねる“習慣づくりの道具”として最適だと思う。





















