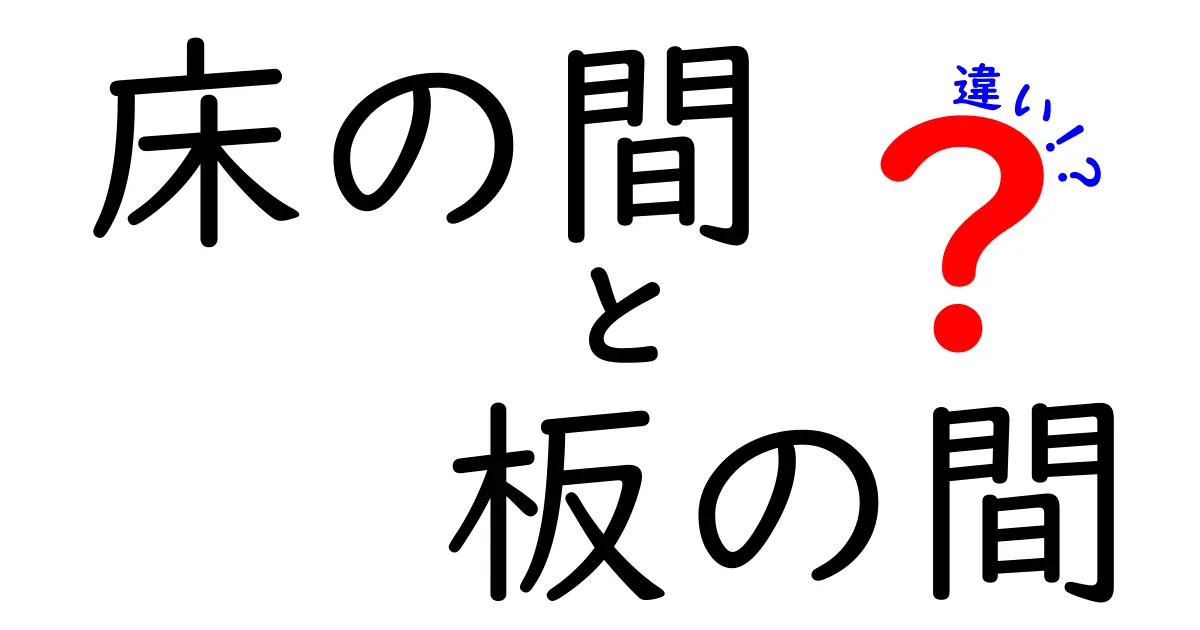

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
床の間とは何か?
床の間(とこのま)は、日本の伝統的な和室に見られる特別な空間のことを指します。主に掛け軸や生け花などを飾るための凹んだスペースで、和室の中でも格式の高い場所とされています。昔の日本家屋では、床の間がある部屋は客間として使われることが多く、季節の花や美しい掛け軸を飾り、訪れた人をもてなす役割がありました。
床の間は日本の伝統美を象徴する場所であり、和室の中心的な装飾スペースとして重要な役割を持っています。建築的には壁が奥に引っ込んでいる構造になっており、床は畳の上げ段になっていることが多いです。
床の間の設置によって、部屋の格式や雰囲気が大きく変わり、日本文化の美意識や季節感を表現する重要な空間となっています。
板の間とは何か?
一方、板の間(いたのま)とは、畳ではなく木の板を床材に使った部屋や部分のことを指します。日本家屋では畳の和室が多いですが、玄関や廊下など足を汚しやすい場所、または日常的な作業をする場所に板の間が使われることが多いです。
板の間は掃除がしやすく、湿気に強いという特徴があり、また家具を直に置いても安定しやすいという利点があります。板の間の木材は多くの場合、丈夫な杉やヒノキが使われ、木の木目や温かみを感じられる空間が特徴です。板の間は和室と洋室をつなぐ場所としても機能し、現代のリビングやキッチンに変化した家屋にも使われています。
つまり、板の間は日常生活の実用的なスペースとして重要な役割をもっています。
床の間と板の間の違いを表でまとめると
| 項目 | 床の間 | 板の間 |
|---|---|---|
| 主な用途 | 掛け軸や花を飾る装飾の場所 格式のある客間の一部 | 玄関、廊下、作業場など実用的な場所 掃除や家具の安定に適している |
| 床材 | 畳の一部または上げ段で畳が敷かれることも | 木の板を床材に使用 |
| 空間の構造 | 壁が凹んでいるニッチ状の空間 特別で美的な構造 | 平らな床の木製スペース |
| 役割 | 美を楽しみ、客人をもてなす | 日常生活の実用性を高める |





















