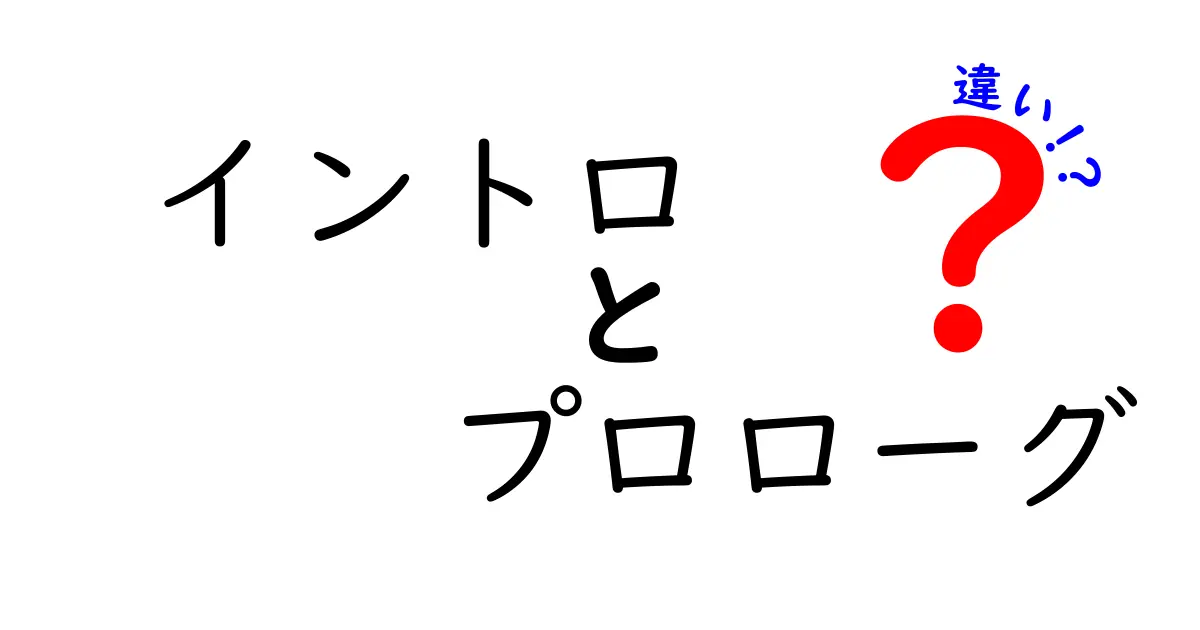

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
イントロとプロローグの違いを知ろう
日本語には「イントロ」と「プロローグ」という言葉がよく使われます。
どちらも“始まり”を示す言葉ですが、使われる場面や意味には大きな違いがあります。
この差を理解することで、文章や映画・ゲームなどの作品を読み解く力が高まります。
まず前提として基本の意味を押さえましょう。
イントロは広く音楽・映像・ゲーム・文章の“導入部”を指します。読み手や視聴者に作品の雰囲気を伝え、これから起こる出来事の予感を作る役割です。
これに対してプロローグは多くの文学作品で使われる用語で、物語の冒頭に置かれる前日譚や背景説明の章を指します。登場人物の動機や過去の出来事を詳しく示すことで、本編の理解を助けます。
この両者は“始まり”を作り出す点で共通していますが、読者の体験としては違いがあります。
例えば映画のオープニングシークエンスをイントロと呼ぶこともあります。ここでは物語の世界観やテーマを提示します。
一方で小説の最初の章がプロローグで、過去の事件が語られ、現在のストーリーが始まる前の布石を作ることが多いです。
ゲームでも「プロローグ」は物語の導入部として、操作方法や世界の背景を学ぶ章が位置づけられることがあります。
このように、媒体によって使い分けが自然に生まれるのが特徴です。
日常的な使い分けと覚え方
日常の会話では「イントロ」と「プロローグ」を別の意味として使うことが少なく、混同されやすいです。
ただし、文章の構造を考えると、イントロは全体の導入、プロローグは物語の背景や動機を説明する章という視点で分けて考えるとわかりやすくなります。
覚えるコツとしては、実例を思い浮かべることです。
例えば映画の予告編はイントロとして機能しますが、小説の冒頭の短い前日譚がプロローグです。
表現の練習として、次のような表を作って整理してみましょう。
このように整理すると、どちらを使うべきか判断がしやすくなります。
読者にとっての“導入”の感覚は人それぞれですが、使い方の目的を意識することが大切です。
例えばニュース記事や教材ならイントロで要点を伝え、長い物語ならプロローグで背景を詳しく説明する使い分けが自然です。
さらに、語彙力を高めたい学習者にとっては、これらの用語の違いを明確に知ることが、文章理解の幅を広げるきっかけになります。
友達と本の話をしていたとき、プロローグって何を指すのかで盛り上がりました。私:『イントロが作品全体の雰囲気づくりなら、プロローグは物語の背後の話、つまり前日譚を語る章だよ。』友達:『前日譚って、すごく面白いけど時系列はどうなるの?』と疑問が湧きました。私は続けて、実例としてある小説の冒頭を挙げました。『プロローグで過去の出来事が短く紹介され、それが現在の事件の動機につながる。だから読者は「この話はこう始まるのか」と期待感を持つのです。』このように、プロローグは物語の核となる“根っこ”を作る役割を担います。読み進めるうちに、登場人物の動機や世界観が自然に理解でき、展開をより深く味わえるのです。
前の記事: « ビットレートと音の違いを徹底解説:どうして音は変わるのか





















