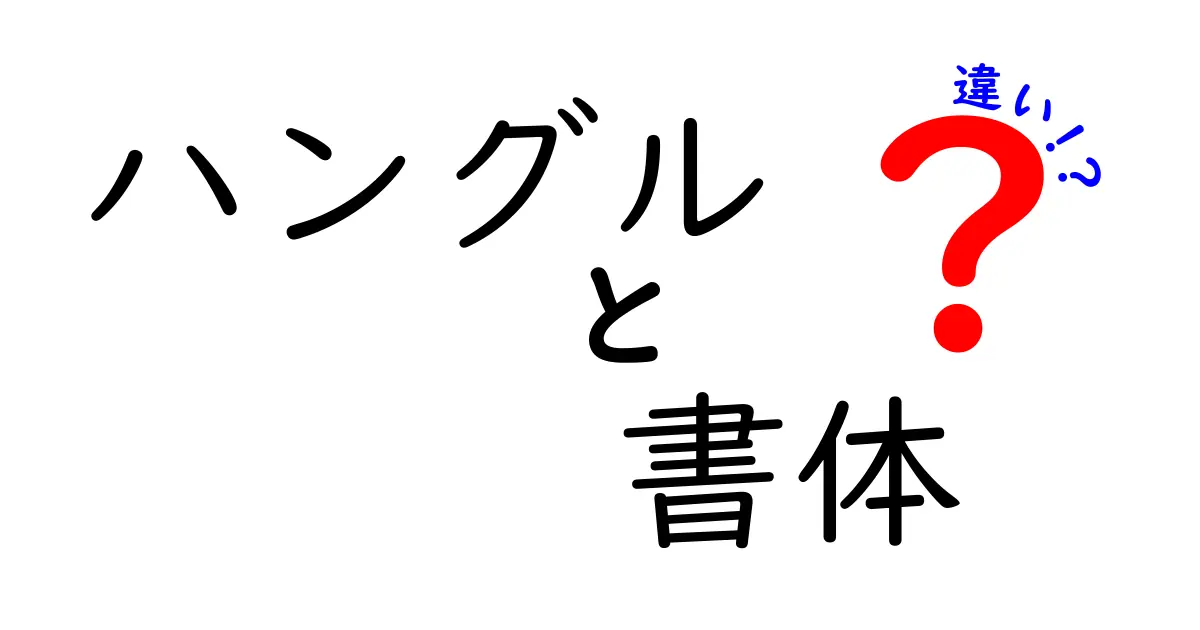

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ハングル書体の基本を理解する
ハングル書体には主に2つの大別があります。ひとつは고딕체サンセリフ、もうひとつは명조체セリフです。고딕체は線がまっすぐで角が鋭く、文字の縦横の比率が整って見えるためスクリーンでの視認性が高い性質を持ちます。日本語のゴシック体と似ていますがHangulの点画が角ばりが強い印象を与えます。学校の教科書やウェブサイトの本文、看板の見出しなど幅広く使われます。一方の명조체は線の終わりが細く、曲線と長いストロークが特徴です。印刷物で特に読みやすく感じられ、長い本文や公式の資料に適しています。印象としては伝統的で落ち着いた雰囲気を作りやすく、ブランドの信頼感を演出したい場面で選ばれることが多いです。
この2つの違いを知ることはデザインの土台を作る第一歩です。色や余白を決める段階でも書体は強い影響力を持ち、同じ文字情報でも印象が大きく変わります。例えば若々しく現代的なイメージを出したい場合は고딕체を選ぶと良いことが多いです。反対に伝統感や信頼性を強調したいときは명조체が適しています。さらにハングル書体を組み合わせるときはリーダビリティのバランスが重要です。本文と見出しのサイズ差をどうつけるか、段組みのガイドラインをどう作るか、どう結びつけるかを考えながら取り組みましょう。
書体の大まかな分類
ここでは書体の大まかな分類と使い分けのヒントを紹介します。まずサンセリフ系の고딕체は主線の幅が均一で、横書きのレイアウトで視線が止まりにくい特性があります。丸みのある角や直線の強さでファッション性も変わり、若者向けの案内やポスターにも適しています。つづいてセリフ系の명조체は筆画の終わりが細く、長い文章を読むときの負担を減らす働きがあります。日本語の明朝体と似た印象を受けるため、信頼感を演出する資料や教育系の教材にもよく使われます。実際のデザインでは두 가지를 조합하여使うケースが多いです。見出しには고딕체を使い本文には명조체を使うといった組み合わせが定番です。
また日常的なデザインでは色と組み合わせたトーンや行間と文字幅のバランス次第で雰囲気が大きく変わります。例えば同じ本文でも太めの고딕체を使えば力強い印象を、細めの명조체を使えば上品で静かな雰囲気になります。紙質がざらつく印刷物では명조체の繊細さが失われることがあるので、実物での確認が大切です。最後に、デザインの目的に合わせて「見出しと本文の組み合わせ」を意識することが、読みやすさと訴求力を両立させるコツになります。
ここまでの話を実際のデザインに落とし込むためには、まず自分の媒体を明確にし、どの程度のモダンさや伝統性を出すのかを決めることが重要です。若者向けのアプリUIなら고딕체に寄せ、教育系の資料なら명조체を中心に組み合わせると自然な印象になります。
実例としての組み合わせのコツは次の通りです。見出しには고딕체の太字系を使い本文には명조체を使うと、視認性と読みやすさの両方を満たせます。ロゴ周りはシンプルな고딕体を選ぶとブランドの現代性を保ちつつ、本文は명조체で重厚感を出せます。小見出しや箇条書きにはバリエーションをつけて読みやすさを保ちましょう。これらの基本を押さえれば、ハングル書体の違いを効果的に活用できるようになります。
印象と使い分けのコツ
デザインの現場で最も大事なのは「目的」を軸に書体を選ぶことです。人に伝えたい情報の性質が公式で堅いのか、親しみやすさを演出したいのかを最初に決めてください。公式文書や教科書の本文には명조체系の細さと連続性が長い文章の読みやすさを高めます。広告やイベントの看板には고딕체の力強さが効果的で、視覚的なアクセントを作りやすいです。さらにウェブは画面解像度や読み手の集中力の持続時間を考慮して字間と行間を広めに設定することが多いです。カラーコントラストや背景色との相性も検討して、読みやすさを崩さないよう注意しましょう。
このように組み合わせ方を意識しながら作業を進めると、見やすさと伝わりやすさの両立が実現します。
実用ガイド:デザインや日常での使い分け
実務での書体選びは、デザインの第一歩としてとても重要です。媒体ごとに適切な書体を選ぶことで、伝えたい情報の性質が読者に正しく伝わります。ウェブサイトでは高い視認性と読みやすさを両立させるために고딕체を主役に据え、本文には読みやすさのための余白と行間を多く取りましょう。印刷物では名入れや本文の長さに応じて명조체を中心に据え、写真や色のパレットと調和させて落ち着いた雰囲気を作り出します。実際のデザイン作業では fonts の組み合わせパターンをいくつか作り、A/B テストを行って最も伝わりやすい組み合わせを選ぶのが効率的です。次に具体的な使い分けのコツをまとめます。まず第一に媒体を決め、対象読者と目的を明確にします。次に雰囲気を揃えるためのテンプレートを作り、見出しと本文のバランスを整えます。最後にカラーとの組み合わせを検討し、コントラストと可読性を意識して微調整を重ねます。
実務での活用例を一つ挙げると、イベントのポスターでは見出しに고딕체の太字を使い、本文に명조체を用いて読みやすさと信頼感を両立させます。パンフレットでは左ページに写真を配置し右ページの本文に명조체を使って読みやすさを保ちつつ、見出しには고딕체の力強さを活かします。最後に、システム上のフォント選択でも同様の考え方が役立ちます。画面読取りの際にはx-heightの大きめなフォントを選ぶと読みやすく、印刷時にはセリフのエッジが美しい명조체系を選ぶと視覚的なバランスが取りやすくなります。
この章のまとめとして、ハングル書体の違いを理解し適切に使い分けることは、デザインの品質を高める基本中の基本です。読者の読みやすさと印象を同時に満たすためには、書体だけでなくレイアウト全体を見渡し、目的と媒体ごとに最適な組み合わせを選ぶことが重要です。
今日はハングル書体の話題を雑談風に深掘りしてみたよ。고딕체は現代的でストレート、명조체は伝統と信頼を感じさせる。僕がデザインするときはまず目的を決めて、見出しには고딕체、本文には명조체を組み合わせることが多いかな。学校のポスターなら고딕체の力強さを活かして目を引き、教科書の本文なら명조체の読みやすさで長い文章も楽に読める。フォント選びはただの美しさだけじゃなく、伝えたい情報の性質を読者に正しく伝える道具だから、場面ごとに適切な組み合わせを試してみてほしい。最後に、フォントはあくまで文の体裁を整える道具。中身がしっかりしていれば、どんな書体でも伝えたいことは伝わるはずだよ。
前の記事: « 明朝体と遊明朝の違いを徹底解説!字の印象が変わる理由と使い分け





















