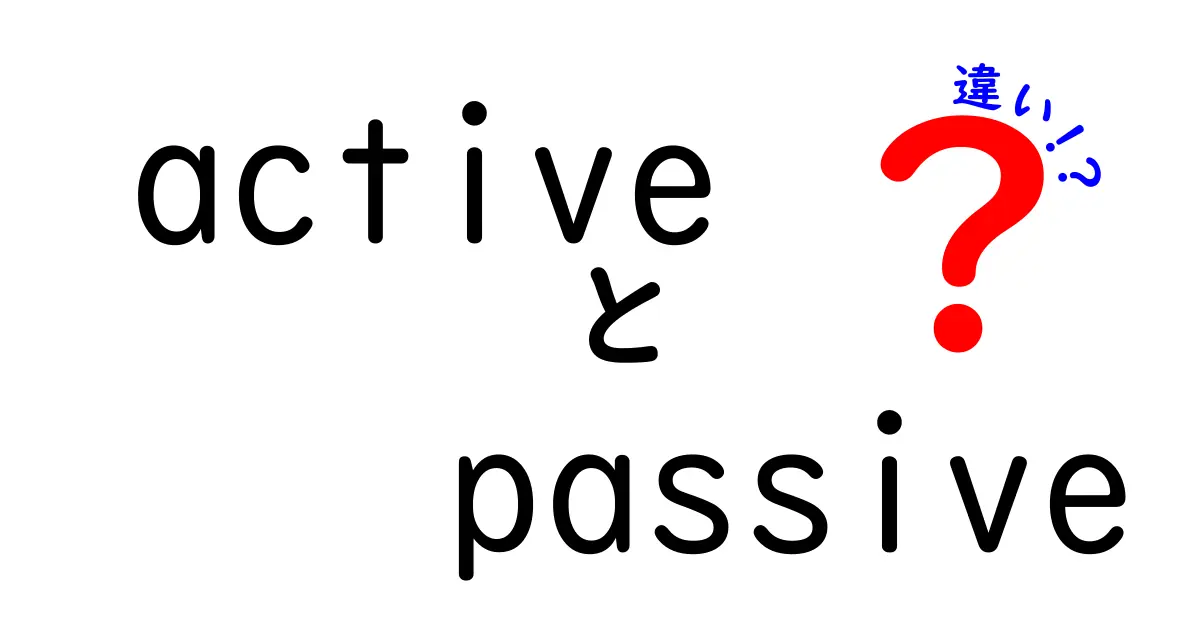

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ActiveとPassiveの違いを、一つ一つ丁寧に噛み砕いて解説する完全ガイド。初心者でも理解できるように、誰が動作の主語になるのか、動詞の形はどう変化するのか、英語と日本語のニュアンスの違い、受け身を使うべき場面と避けるべき場面、そして日常の文章作成に役立つ具体的な例文までを含む完全ガイドです。さらに、受け身にすることで情報の焦点が変わること、能動态と受動态の相互変換の基本ルール、覚え方のコツ、そしてよくある誤解やつまずきポイントを、図や表を用いて視覚的にも理解できる構成にしています。さらに、学習の順序や練習問題の出し方、よく使われる動詞の活用パターンを一覧で示し、後半には実践的な練習問題のヒントと解説を付けました。このガイドを読み終えるころには、日常の文章から難しい英文まで、能動態と受動態を臨機応変に使い分けられる自信がつくでしょう。
ActiveとPassiveの基本の考え方と主体の表現方法、動作の受け手と発信者の観点の違い、動詞の形がどう変化するのかなどを、長い見出しとして展開します。ここでは「主語は誰か」「動詞の活用はどの形になるか」「受動態を使うべき状況と使わない状況」を中心に、初心者にも理解しやすい具体的な説明を含めます。テキストだけでなく、実際の例文の作成手順や、気をつけるポイントを整理して一つの見出しの中に詰め込みます。さらに比較的難易度の低い例文の作成方法、能動態と受動態の変換練習の手順、間違い例を使った注意点、そして授業や自習で使えるチェックリストも含め、読者がすぐに日常の文章で効果を感じられるように配慮しています。
Activeの説明から始めます。主語が動作を行う文が能動態です。例文を日本語から英語へ直訳するのではなく、日本語の意味を崩さずに英語の自然な語順に直すと能動態が基本です。
例えば「太郎がリンゴを食べる」は英語で "Taro eats an apple" となります。このとき主語は太郎で、動作の主体がはっきりしています。
受動態は「リンゴが太郎に食べられる」のように、動作の受け手や結果を強調し、主語が動作を受ける側になります。
受動態の作り方は be動詞 + 過去分詞です。例として "An apple was eaten by Taro." などがあり、文章の焦点を受け手に移したいときに使います。
能動態と受動態を適切に使い分けるコツは、伝えたい情報の中心を決めることです。情報の“誰が”という点を前面に出したいときは能動を使い、情報の“受け手・結果”を前に出したいときは受動を使います。さらに、日常生活の文章、学校の作文、ニュース記事、説明文など、場面に応じた使い分けが求められます。
ここからは具体的な比較表で違いを整理します。
以下の表は、ActiveとPassiveの要点を整理したものです。
注意点として、英語の受動態は常に「be動詞 + 過去分詞」で構成されるわけではなく、時制や語形変化によって形が変わる点にも気をつける必要があります。
また、よくある間違いとして、受動態を作るときに過去分詞の形を間違えたり、be動詞の時制を間違えたりするケースがあります。例として「本は読まれるべきだ」と言いたいときは "The book should be read." のようにモーダル動詞と受動態の組み合わせが必要です。学習のコツは、まず能動態の文を作ってから、それを受け身の形に変換してみる練習です。そうすることで自然な感覚が身についていきます。
この記事を通じて、能動態と受動態の使い分けが自然に身につき、作文や英語のリーディング・リスニングで適切な表現を選べるようになります。
友だちと雑談している時、彼が『受動態って難しそうだよね』とつぶやいた。私は「難しく感じるのは、誰が主語かをはっきりさせる練習をしていないからだよ」と返した。受動態は情報の焦点を変える力があり、文章の主語を入れ替えるだけでニュアンスが大きく変わります。例えばニュース記事や研究の報告では受動態がよく使われ、結果や影響を強調します。一方で日常会話や友人宛のメールでは能動態が読み手に伝わりやすく、動作の主体が明確であるほど理解しやすくなります。この感覚をつかむコツは、まず意味を日本語で頭の中に描き、次に英語文で同じ意味をどう伝えるかを考えること。練習として、普段の生活の中で「誰が」「何を」「どうする」を順番に置き換える練習をするのがおすすめです。





















